記事一覧
15件/4059件

ペースメーカーの仕組みと適応となる疾患
ペースメーカーは脈が少ないことで、脳や全身への血流を確保できない人たちの心機能を補うために装着されます。ペースメーカーの基本的な仕組みと、適応となる疾患を抑えておきましょう。 ペースメーカーの仕組み ペースメーカーは、病的な徐脈を起こした疾患に適応され

がん患者さんの外見変化、どうケアする?
がん患者の外見支援に関するガイドラインの構築に向けた研究班は、「がん患者に対するアピアランスケアの手引き」を発行しました。この本は、治療編と日常整容編の2部に分かれ、エビデンスとともにケアについてまとめられています。 今回は、この本の内容や医療従事者がどのようにかかわる
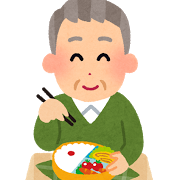
高齢者の栄養管理の現状を聞く!
高齢者はさまざまな要因が重なって、十分な栄養を摂取できなくなるケースがみられます。 また、在宅で療養している患者さんの場合、きめ細やかに食事指導をしても、きちんと実践できるとはかぎりません。 今回は、高齢者看護に携わるみなさんにお集まりいただき、高齢者の栄養管理の現状

CASE11 訪問時の食事を断ったことから認知症が拡大したケース【2】
困難事例11 さらにさまざまな認知症状が出始めたCさん 前回までの経緯 お料理好きで温厚な性格の72歳女性Cさん。糖尿病管理で訪問看護が入っていたが、毎回用意される手料理を受け取れないとお断りしたあたりから、Cさんの態度に変化が現れた。 もともと「誰かに見張られ

植え込み型除細動器(ICD)の仕組みと適応となる疾患
ペースメーカーと似た機器に、植え込み型除細動器があります。適応となる疾患や、仕組みにも違いがありますので、しっかりと区別して覚えておきましょう。 ▼不整脈の看護について、まとめて読むならコチラ 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント 植え込
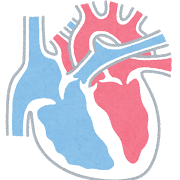
第7回<読み方・対応編⑤>発作性上室頻拍 (PSVT)
関連記事 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント 発作性上室頻拍(PSVT)は、症状の発生も収束も突然で、規則正しい頻脈(心拍数150~250回/分)であることが特徴です。心電図波形上も“突然起こり、突然終了する”一過性の波形が出現します。
胃がん手術―ドレーン管理と観察のポイント
ドレーン留置による疼痛や離床の遅れ、逆行性感染といったデメリット、また、「ERAS」の観点からドレーンを入れないことがあるかもしれません。ですが、縫合不全などの術後合併症を早期に発見でき、適切な処置にもつながることから、胃切除後にドレーンを留置するケースは少なくありません
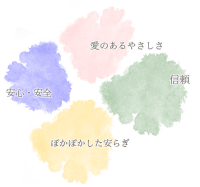
在宅での吸引器の使用と指導について知っておこう!
地域包括ケアの推進により医療依存度が高い方が在宅へ 今までは入院、施設入所が一般的であった状況の患者さんでも、超高齢化社会、2025年問題、地域包括ケア病棟の新設など、病院から在宅へ戻るという選択肢が近年増えて来ました。 国としても2025年に向け、「高齢者の尊厳
第5回 1日に必要なたんぱく質量は?摂取時の注意点は?
たんぱく質制限は画一的に行わない 人間の身体になくてはならない栄養素のうち、特に重要なものと位置づけられている「たんぱく質・炭水化物・脂質」を『三大栄養素』といいます。この中で、炭水化物と脂質は身体を動かすエネルギーとして使われた後、呼気(二酸化炭素)や汗(水)や

【痛みの評価スケール】VAS、NRS、フェイススケール
【関連記事】 ● 術後痛の種類や機序とは▼その他のスケール・指標はこちら● 臨床現場でよく使うスケール・指標の記事一覧 痛みの評価スケールとは 患者さんが抱えている痛みにたいして、どのようにケアをしていくかを決めるためには、患者さんの痛みの評価、アセスメント
第4回 1日のエネルギー摂取量は?その摂取量でないとなぜいけないの?
制限しすぎても腎臓に負荷がかかってしまう CKDでは、エネルギーを摂り過ぎると、糖尿病や脂質異常症の原因となり、腎臓の血管の動脈硬化を進行させます。逆に、蛋白制限を続けていると、エネルギーが不足してしまいがちになり、低栄養状態となります。すると身体のたんぱく質が分
術後回復強化「ERAS」ってなに?
ERASとは? ERASはEnhanced Recovery After Surgeryの頭文字をとった用語であり、術後の患者さんの早期回復を促し、 周術期管理法の改善をめざす取り組みです。オリジナルのERASは北欧発祥で、結腸がんの手術症例に限ったものでした1)。

AYA世代|思春期と若年成人期のがん患者さんが抱える問題
「AYA(アヤ、Adolescent and Young Adult)世代」と呼ばれる10代半ば〜30代のがん患者さんは、学業の継続や就職、結婚、出産などとがんの治療が重なり、その他の世代とは違った困難があります。若い世代のがん患者さんの実態を調査している厚生労働省の研究

CASE11 訪問時の食事を断ったことから認知症が拡大したケース【1】
困難事例11 認知症による妄想が進行していくCさん 72歳女性のCさん。娘は1人いるが遠方に住んでおり1人暮らしである。 始めは糖尿病の血糖値管理を目的に訪問看護が入っていた。もともと料理人のため、手料理で人をもてなすことが大好きで温厚な方であった。 訪問時も「
第3回 糸球体濾過量(GFR)で腎機能を評価する!
腎機能の指標として濾過量を見る まず腎機能とはどういったものか? 腎臓は、電解質や血圧の調節、また造血ホルモンなど内分泌器官としての役割を担うなど様々な機能を持っていますが、簡単に言いますと、「腎臓が血液をどれだけきれいに濾過できるか」ということです。一般的に腎機


