記事一覧
15件/4063件

【胸部に術創がある患者さんの術後リハ】術後のリスクを想定して行う
開胸手術の代表例として肺がんなどの呼吸器疾患、心臓外科、食道がん手術などが挙げられます。今回は肺がんの患者さんについて解説します。 ▼術前・術後の看護について、まとめて読むならコチラ 術前・術後の看護(検査・リハビリテーション・合併症予防など)

ねじ子のモニター心電図をなんとなく見る方法
[1]まずはアラーム設定をきちんとしておく。決してoffのままにはしておかない。 [2]アラーム音がしていなければ、たいていは本当に正常である。「正常なのか、へー」と思いながら、チラ見していればOK。 アラーム音がしている、またはなにか異常結果を吐き出して

高齢者の低栄養を防ぐ! 病棟から地域まで、患者さんに栄養管理を継続してもらう工夫【PR】
高齢者の低栄養状態は、疾患からの回復を妨げ、悪化や再発につながります。そこで最近では、入院患者さんに早い時期から栄養アセスメントを行う医療施設が増えています。 しかし、入院中は良好に保たれた栄養状態も、退院後、在宅に移行するとともに継続が難しくなるといわれます。 ここ
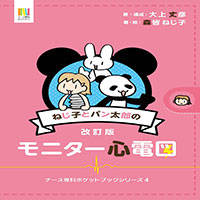
ねじ子とパン太郎のモニター心電図 改訂版が発売!
≫amazonで購入する ねじ子とパン太郎のモニター心電図が改訂されました。さらにわかりやすくなるように、解説や図を新しく追加! ポケットブックの基本がわかる1冊! さらに改訂版では、カバーに心拍数スケールとQTスケールがついていて、心電図に当てればすぐに心拍数

ヒュージョーンズ(Hugh-Jones)の分類
ヒュージョーンズ(Hugh-Jones)の分類 Ⅰ 同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並みにできる Ⅱ 同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並みにはできない Ⅲ 平地でも健康者並みに歩けな

気管切開の種類とタイミング
▼気管切開についてまとめて読むならコチラ 気管切開とは? 気管切開の看護 気管切開の種類を整理しよう! 切開を行う位置が異なる場合も 気管切開とひとくくりにいっても、いくつか種類があります。ここで整理しておきましょう。 気管切
【呼吸・循環編】新人看護師オススメ記事
今回は、多くの人が苦手意識を持ちやすい呼吸・循環関連のオススメ記事を紹介します。最初に、わかりやすく学んで、苦手意識が芽生えないようにしましょう。 新人研修が始まって約1カ月が経つわね。 そうですね。私はこのころにはもうなにがなんだか……。
経腸栄養剤の選択の仕方
経腸栄養剤の種類と特徴 経腸栄養法(enteral nutrition:EN)に用いる製品には、医薬品と食品があります。経腸栄養剤は、原材料から天然濃厚流動食と人工濃厚流動食に分けられますが、ほとんどが人工濃厚流動食です。 人工濃厚流動食は、その組成から成分栄

【術後リハ】術前オリエンテーションを行うメリットは?
今回は術前オリエンテーションを行った結果、術後の離床がうまくいき、早期退院につながった事例を紹介します。 ▼術前・術後の看護について、まとめて読むならコチラ 術前・術後の看護(検査・リハビリテーション・合併症予防など) 事例 術前オリエンテー

修正ボルグスケール(Borg scale)主観的運動強度
「修正ボルグスケール」は0から10の段階で呼吸困難の程度を表すので、簡便でわかりやすく、臨床で使いやすいスケールです。 (『ナース専科マガジン』2014年11月号から改変利用)

座位や歩行が可能なケース、おむつはどう選ぶ?【PR】
排泄用具の種類はさまざまです。 おむつ類(パンツタイプ紙おむつ、テープ止めタイプ紙おむつ、尿とりパッド、布製のアウター)、トイレ(ポータブルトイレ)、尿瓶、集尿器などを利用する人に最も適した組み合わせで選ぶことが大切です。今回は、座位や歩行が可能な人の場合、どのようなも

【術後リハ】術前オリエンテーションを未実施、何が起きたのか?
術直後のリハビリテーションの目的は、術後呼吸合併症の予防、早期離床による早期ADLの再獲得となります。今回は、術前にオリエンテーションを行わなかった事例を取り上げ、解説します。 ▼術前・術後の看護について、まとめて読むならコチラ 術前・術後の看護(検査・リ
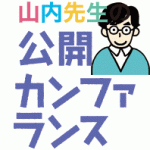
第36回 誤嚥性肺炎で入院、胸痛を訴える患者さん
事例 [Yさん より提供された事例] 80歳代で誤嚥性肺炎で入院してきた男性患者さん。あるとき、胸痛を訴えたため、12誘導心電図、バイタルサイン、その他身体所見を確認しましたが、特に誤嚥性肺炎以外の症状はみられませんでした。 →あなたなら、こんなときどう対応する

手術室での看護の流れ、申し送りはどんなことを伝える?
手術室看護師はどのようなことを行っているのでしょうか。手術室は閉鎖された空間と言われ、手術室内での実態はあまり明らかにされていないことが多いように思います。そのため、手術室看護師はいったいどのような看護をしているのかわかりにくい状況にあります。今回は、手術室看護師がど

ショック時の輸液(輸液蘇生)
輸液反応性とはなにか ショック時には、輸液の急速投与を行います。これは、輸液によって一回拍出量が増えることにより、心拍出量が増えて、結果、酸素供給量が増えることを期待するためです。 一回拍出量、そして心拍出量が増えるのは、心臓の前負荷が影響します。前負荷と


