「注目ピックアップ」の記事一覧
15件/338件
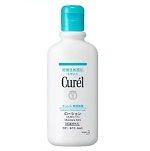
冬こそ実践! スキンケア
寒さが厳しい真冬は、空気の乾燥が特に気になります。室内は暖房でさらに湿度が低い状態になりがちです。患者さんはもちろん、看護師のみなさんも肌がガサガサして、粉がふいたり荒れてしまうことはありませんか。 秋冬の肌の乾燥・肌荒れを予防したり、やわらげるためのスキンケアについて
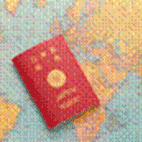
第8回 オーストラリアで国際正看護師として働こう!
看護師さんの為の海外留学最新情報をお届けする、海外留学エージェントのワールドアベニューです。 今回は、ワールドアベニューの海外正看護師資格取得プログラムによって見事、オーストラリアで正看護師資格を取得された方が、現地でどのように働かれているかを紹介させて頂きます。 ま
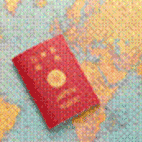
第7回 海外留学に踏み出す上での不安要素 トップ3を解消!
看護師さんの海外留学最新情報をお届けするワールドアベニューです。 気が付けばすっかり秋色。コスモスが風にゆられる季節になりましたね。今年も残すところ3ヶ月。来年3月末に退職を控える方にとっては、次の進路と真剣に向き合わなければならない時期に来たのではないでしょうか。
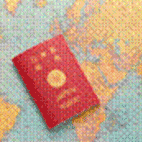
第6回 夏開催 短期体験看護留学の3つのポイントを一挙公開!
夏休みも終わり、通常業務に戻られるころではないでしょうか。 さて、以前、ナース専科でもご紹介させて頂いた「2週間で体感するオーストラリアの看護現場体験留学」。 ●現地総合小児病院での見学の際に見た、「病院のように見せたくない」という配慮に感動… ●世界中から
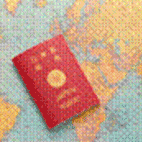
第5回 気になる『留学Before/After』 ケース3
看護師さんの海外留学最新情報をお届けするワールドアベニューです! 海外留学というとついつい敷居を高く感じがちな方も少なくありません。憧れの海外ドラマでの生活や国境なき医師団などの海外での活躍など、憧れはあるものの、私には夢のまた夢…英語もできないし…。そんな風に考えていら
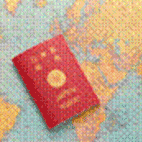
第4回 2013上半期 海外留学人気留学ランキングTOP5
毎月、看護師だからできる海外留学をサポートするワールドアベニューより、皆様に最新の留学情報をお届けさせて頂いておりますが、早いもので、既に4回目となりました。いくつかの留学プランを今までもご紹介させて頂きましたが、今回は、2013年も半分が経過したところで、2013年上半
第3回 20代しかできない! ワーキングホリデーでリフレッシュ
日本で毎日頑張る看護師の皆様に人気なリフレッシュ方法の1つが「海外旅行」ではないでしょうか。多くの方が実際に海外旅行で感じるのは、もっと英語を話せたら世界が広がるのにという英語力の悔しさと、もっと腰を落ち着けて憧れの海外で生活をしたいという夢があるということです。 海外
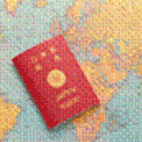
第2回 2週間で体感するオーストラリアの看護現場
医療現場でも必要なグローバル化への対応 近年日本でもEPA(経済連携協定)制度などにより海外からの看護師や介護士の受入れが始まり医療現場でも国際化が進んでいる。また、海外からの外国人誘致も進み外国人の患者も増えていっているのが現状だ。海外の文化や英語でのコミニュケーショ
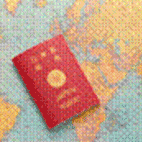
第1回 20代で是非チャレンジしたい 海外医療現場での有給インターンシップ
看護インターンシッププログラムのポイントを、参加者の看護師に直接インタビューしました。 看護インターンシッププログラムのポイント ●英語力『0』からでも大丈夫。憧れの英語がペラペラに!? 生活や仕事の中でヨーロッパ人の友達やアジアの友達ができた。みんなと喋れ

第4回 口腔トラブル中の栄養摂取方法
協賛:サンスター株式会社/主催:ナース専科 がん化学療法に伴い、高い頻度で発生する副作用である口腔粘膜炎や知覚過敏。これら口腔トラブルへのケアを学ぶ「明日から実践! がん化学療法時の口腔ケア」セミナーのレポート第4回は、静岡県立静岡がんセンターの山下亜依子先生がレクチャ

第3回 口腔ケアの具体的スキル
協賛:サンスター株式会社/主催:ナース専科 がん化学療法に伴い、高い頻度で発生する副作用である口腔粘膜炎や知覚過敏。これら口腔トラブルへのケアを学ぶ「明日から実践! がん化学療法時の口腔ケア」セミナーのレポート第3回は、北海道がんセンターの江戸美奈子先生がレクチャーする

第2回 口腔トラブルが起こるメカニズムとケアのエビデンス
協賛:サンスター株式会社/主催:ナース専科 がん化学療法に伴い、高い頻度で発生する副作用である口腔粘膜炎や知覚過敏。これら口腔トラブルへのケアを学ぶ「明日から実践! がん化学療法時の口腔ケア」セミナーのレポート第2回目は、静岡県立静岡がんセンターの大田洋二郎先生がレクチ

第1回 がん化学療法時の口腔ケア
協賛:サンスター株式会社/主催:ナース専科 がん化学療法に伴い高い頻度で発生する副作用の一つに口腔粘膜炎、口腔乾燥、知覚過敏など口腔トラブルがあります。これらのトラブルは、患者さんのQOLを低下させ、がんの治療にも影響を与えます。 2012年12月8日、口腔外
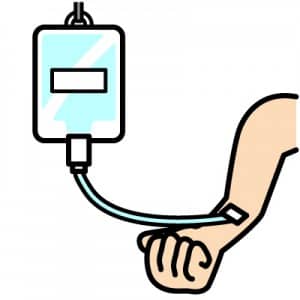
第24回 栄養管理の重要性
『看護師のための輸液管理』というテーマで24回、連載させていただきました。その最終回のタイトルは『栄養管理の重要性』としました。輸液管理は、ある意味、栄養管理の一環として行う、ということでもありますから。 輸液管理とリスクマネジメント ナースにとって、日常業務の中
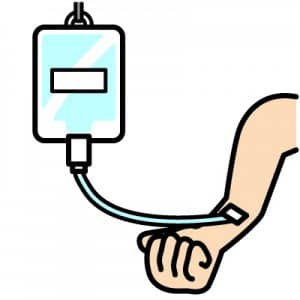
第23回 本物のNSTとは
NST(栄養サポートチーム・栄養管理チーム)とは NSTとは、Nutrition support teamの略語です。日本語では栄養サポートチーム、栄養管理チームと表現されています。この連載を読んでおられる方は、NSTとはなんぞや、という質問には容易に答えることができる


