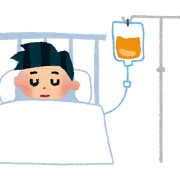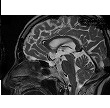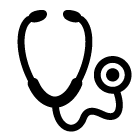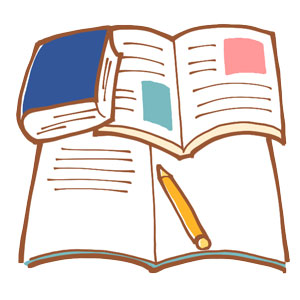うつの職員も働きやすい環境づくりとは?
うつの職員も働きやすい環境づくりとは?
- 公開日: 2012/6/17
健康管理に気をつけていても、さまざまなストレスから体調を崩してしまうことはあるのではないでしょうか。そんなとき、周囲が不調のサインをしっかりとキャッチして、ケアをしていくことも大切です。今回は、どのように環境を整えておけば、不調のサインを早期に発見できるのかを考えていきます。
Q. うつで退職する職員も増えていますが、そうしたスタッフにも働きやすい環境づくりの実際はどのようになっているのでしょうか。
A. 不調のサインを早期に発見できる環境を整えることが推進されています。
職場環境を整えることも対策の一つ
年間の自殺者が3万人を超える現在の日本。働く人の6割以上が仕事への強い不安やストレスを抱えているというデータもあり、働く環境の改善は待ったなしの状況といえます。こうした実態を受け、厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、メンタルヘルス対策を適切・有効に行うよう各事業所に示しています。
そこでは職場における対策として、
- ●セルフケア
- ●ラインケア
- ●事業所内の産業保健スタッフなどによるケア
- ●事業所外資源によるケア
という4つの柱を基本にメンタルヘルスケアを継続かつ計画的に行うことが推進されています。

いざというときに相談できることも安心感につながる
このうち[1]セルフケアは、これまでの項で触れてきたように、スタッフそれぞれがストレスと上手に付き合うことを示します。
[2]ラインケアは、働きやすい職場づくりのポイントになります。管理監督の立場にある人だけでなく同僚同士もお互いの状態に日頃から目を配ることが、スタッフの変化の早期発見につながります。いつもと違う行動や、ちょっとでも気になる言動のあるスタッフがいたら「少し元気がないね」「疲れていない?」など積極的に声をかけましょう。
声かけは相談しやすい雰囲気づくりにもつながり、気にかけられたことで相手が楽になるケースもあります。相談を受けるときには、相手の気持ちや考えを尊重しながら時間をとってじっくり聴くことが大事です。ただし、解決が難しい問題は一人で抱え込まず、師長や精神科などへの相談を勧めたり、本人が言いにくい場合は代弁することも必要です。
上司に直接相談しにくい場合は、リエゾンナースや産業保健医などの[3]事業所内の産業保健スタッフなどによるケア、職場内での相談自体に抵抗がある人は、電話相談や公共の相談窓口、クリニックなどの[4]事業所外資源によるケアもあるので、一人で悩まず積極的に活用しましょう。家族や友人を含め、いざというときに相談できる先をいくつももっていることが安心感につながるはずです。

次回からは、患者さん・家族との関係について考えていきます。
(「ナース専科マガジン」2010年5月号より転載)