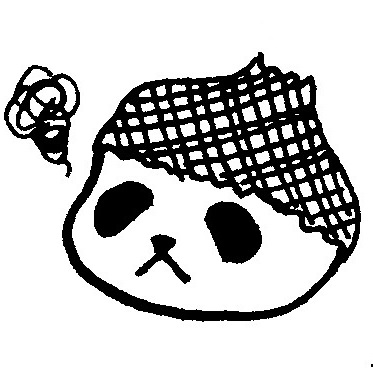 ヘパリンロックとは? 正しい手順・量・フラッシュについて
ヘパリンロックとは? 正しい手順・量・フラッシュについて
- 公開日: 2014/3/26
留置針を使用しないときには、血液が固まるのを防ぐために、ヘパリン生食でルート内を満たす必要があります。
ヘパリンロックの正しい手順について解説します。
1 必要物品

患者さんにヘパリンロックについて説明をします。
説明例「点滴の管がつまらないようするためのお薬を入れます。」
この記事を読んでいる人におすすめ
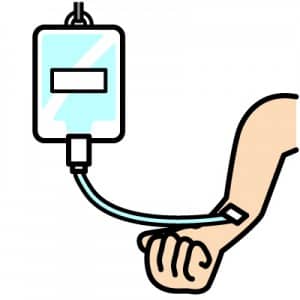
第11回 ヘパリンロックと生食ロックについて
日常の輸液管理において、やはり、へパリンロックについての知識は必要です。というか、問題となっているのは、へパリンロックをしなくても生食でロックしておけばいいのではないか、ということですね。ナースの方々もこの問題については興味があると思います。今回は、へパリンロックか、生食での

簡単! わかる! 点滴の滴下数計算方法
点滴の滴下数計算の基本 点滴の滴下計算は日々の看護業務において行われており、患者さんの状態に応じて正確な輸液管理が求められるため安全に調整、管理する能力が必要となります。基本的な計算方法を理解し、実際の臨床において対応できるようにしておくことが、より安全な看護業務に繋

希釈液の濃度計算を攻略する!
【関連記事】 * 簡単! 楽ちん! 点滴の滴下数計算 2つの方法 * リンゲル液、乳酸リンゲル液、酢酸リンゲル液の違いは? * 【問題2】抗生剤と生食50mlを、30分間 成人用ルートで投与する時、1分間の滴下数はいくつ? 希釈液の濃度を求めるのは、%やm

輸液の看護|輸液とは?種類、管理、ケア
輸液ケアを行うときに、知っておきたい知識が得られる記事をまとめました。 輸液ケアとは 輸液ケア(輸液療法)の目的には、主に蘇生、生命の維持、栄養の補給の3つがあります。輸液は開始後ずっと同じものを投与しつづけるわけではなく、病態や疾患の悪化・回復に合わせて、
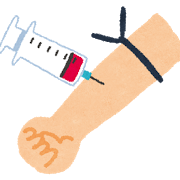
血管が見えない患者さんと硬い患者さんの穿刺のコツ
ルートキープが難しい患者さんへの対応のキホン ルートキープ(静脈路確保)とは、静脈内に針やカテーテルを留置して輸液路を確保することです。薬剤投与を行うためのルートキープは、患者さんの治療にかかわる重要な手技です。特に、急変時などクリティカルな場面では、迅速に薬剤を投




