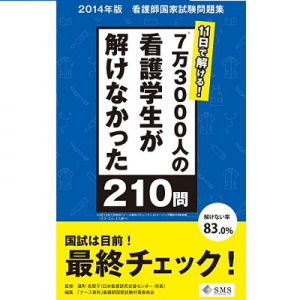【座談会】褥瘡ケアに必要なことは?
【座談会】褥瘡ケアに必要なことは?
- 公開日: 2014/5/8
褥瘡ケアに関して、現場の看護師はどのようなことを知りたいと思い、指導する立場の看護師は何を伝えたいと考えているのでしょうか。
超急性期から慢性期までさまざまな病期の患者さんを看る、褥瘡ケアのエキスパートに集まっていただき、話を聞きました。
褥瘡ケア用品を使いこなすには?
――現場スタッフは、日々どのような思いで褥瘡ケアを行っているのでしょうか。認定看護師として感じることを聞かせてください。
渡邊 看護師には、褥瘡に対して「治さなければ、よい方向へ向かわせなければ」という強い使命感があると思います。経験が少ない看護師は、ついドレッシンング材(ここでは閉鎖性ドレッシング材を指す、以下同じ)や除圧用具を知ることがよいケアにつながると考えがちです。一方で、ベテラン看護師は知識や技術がある分、なかなか治らない創を前にすると「これでいいのだろうか」という疑問から、やはりドレッシンング材や外用薬の選び方や使い方に目がいくようです。
斎藤 受け持ちの患者さんに褥瘡があったとしたら、何とか治したいという思いはみんな同じですよね。現場は、「何を使ったらいいですか」と質問されることが多いのですが、何をどう使うかより先に看るべきことがあります。ですから、一言では伝えられないのが正直なところです。
清野 訪問看護の場合、ご家族の「痛そうだから早く治して」という切実な思いにも何とか応えたいという気持ちになります。ところが、褥瘡について詳しい主治医ばかりではないので、外用薬やドレッシング材を変えたいと思ったら、自分から医師に提案したり、交渉しなければなりません。そのためにもそれらの知識や情報は必要になってきますね。
廣川 確かに当院でもその傾向があります。たとえ入院していても、褥瘡担当の医師がいつでもすぐに診察できるわけではないですよね。早く治してあげたい、という気持ちから、この創に何かできないかと考える人は多いようです。
次ページでは、「ケア用品の知識を得る前にやるべきこと」について話します。