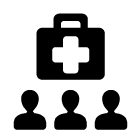【連載】看護学原論に立ち戻って考える!KOMIケアで学ぶ看護の観察と看護記録
 第7回 看護にとって「病気」とは? ―看護のものさし④生命力の幅を広げる援助
第7回 看護にとって「病気」とは? ―看護のものさし④生命力の幅を広げる援助
- 公開日: 2015/11/18
そもそも「看護」って何だろう?何をすれば看護といえるのだろう?本連載では、看護とはどのようなことであり、どのような視点で患者を観察し、また記録するのかについて、ナイチンゲールに学びながら解説します。
さて本連載の第6回で「生命力を消耗させているものや状態」がどういう性質を持つものなのかが見えてきたでしょうか。このことは同時に「その人の体内でどんな力が発動して修復過程が営まれているか」と観ていく視点と重なります。
今回は“看護のものさし”の4番目「生命力の幅を広げる援助」についてお話ししますが、このプラスの発想を実現するためには、「生命の法則」のあり方をしっかりと学ぶことが重要になってきます。
看護の法則=生命の法則
人の身体内部では、いつでも障害を乗り越え、克服し、バランスのとれた状態に修復させようと働いている力があります。
その「修復の力」=「持てる力」を活用して、生命力の幅が広がるように導くのが看護の“ものさし”④の考え方です。
乱れた生命体の内部を復元させようとして発動するシステムは、人体に宿る生命の法則に依拠しています。看護はその時々にこの力を見据えて、この力に力を貸すことが肝心です。
また、生命力の幅を広げるためには、その人に今残された力や健康な力を見極めていく取組みも大事な要素となります。この発想はものさし⑤とも連動します。
どのような患者でも生きている限りは必ず「残された力・健康な力」があります。その力を見出して活用する方策を考えていくのが看護師の大きな役割です。