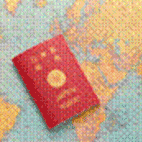[診療報酬] バイオ後続品、患者への情報提供など評価を 厚労省
[診療報酬] バイオ後続品、患者への情報提供など評価を 厚労省
- 公開日: 2019/9/20
厚生労働省は18日の中央社会保険医療協議会・総会で、次回診療報酬改定に向け、個別事項の「その1」の「医薬品の効率的かつ有効・安全な使用」の中でバイオ後続品について課題と論点を示した。
バイオ後続品で薬価収載されているのは、まだ9成分にすぎず、使用も進んでいない。論点では、バイオ後続品を患者に推奨する場合の情報提供、バイオ後続品の新規導入や新薬からの切り替え時の説明や症状の観察などを評価することを提示した。
バイオ後続品の使用割合は、2016年度でエポエチンが67%、フィルグラスチムが66%と高いが、9成分全体としては32%程度にとどまっている。一方、医療機関や薬局の備蓄は、病院が54%、薬局でも30%となっている。病院ではDPC病院で備蓄している割合が高い。
また、バイオ後続品の認知率は、生活者全体では19.1%で、関節リウマチ患者は34%、糖尿病患者は26.5%となっている。その中で、関節リウマチ患者の37%、糖尿病患者の44.4%が、使用したいと回答した。
これらを踏まえて、厚労省は、▽バイオ後続品を知らない患者にバイオ後続品を推奨する際の情報提供▽新たにバイオ後続品を導入、または現在使用しているバイオ医薬品をバイオ後続品に切り替える場合の患者への説明や症状の観察等-について評価することを論点として提示した。
議論では、日本医師会常任理事の松本吉郎委員が、患者への情報提供や説明などバイオ後続品の使用促進の前提として、「医師への情報提供や安定供給の確保などの環境整備がまず最重要」と指摘した。他の委員からの意見はなかった。
厚労省は、松本委員の意見を踏まえながら、提示した論点の方向で対応を進めることになるとみられる。
(厚生政策情報センター)
カテゴリの新着記事

[予定] 注目される来週の審議会スケジュール 2月9日-2月14日
来週2月9日(月)からの注目される厚生行政関連の審議会は以下の通りです。2月9日(月)15:00-17:00 第26回 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会2月10日(火)未定 閣議2月12日(木)13:00-15:00 第64回 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会
-
-
- [医療提供体制] 医療費不払い外国人、報告基準額「1万円以上」に引き下げ
-
-
-
- [医療改革] サイバーセキュリティ、医療システムはクラウドネイティブ化へ
-
-
-
- [医療費] 25年度4-9月の医療保険医療費、75歳未満で前年比1.4%増
-
-
-
- [医療改革] 新たな定期接種ワクチン、副反応疑い報告基準案を提示 厚労省
-