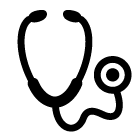第3回 年齢によって「死」の捉え方は どう違うか(前編)
第3回 年齢によって「死」の捉え方は どう違うか(前編)
- 公開日: 2011/8/2
親をはじめ、子どもにとって大切な人が亡くなる場合、そのことを事前に知らせることは、子どもの発達の面からも大切です。死を伝えることで、決して悲しみが軽くなるわけではありませんが、残された時間を意識しながら一緒に過ごし、子どもなりのお別れができるからです。「子ども」と一言でいっても、年齢によって死についての理解力も、患者さんや医療者とのかかわり方も異なります。
今回は、「大切な人を亡くす子ども」へのかかわりを考える際に大切な、子どもの年齢に応じた死の捉え方について学んでいきましょう。
死んだ人も生き返ると幼児は考える
死に対する子どもの認識や理解を明らかにしようと、これまでいくつかの研究が行われています。なかでも、ハンガリーの心理学者ナギーが行った、3~10歳の子どもの死の認識に関する研究(1948)は、子どもの年齢に応じた死の理解を読み解く上で、基礎となる考え方です。
これによると、3~5歳では死が逆戻りできないこと、つまり、死んでしまったら二度と生きている状態に戻らないこと(不可逆性)や、肉体的な生の終わり(身体機能の停止)であることが理解できないとしています。そのため、子どもは、『死んだ人が目を覚ます』、あるいは『電池が切れたおもちゃのように再び元に戻せる』、と考えるとしています。
5~9歳では、死を敵として、擬人化して捉えるとしています。子どもが死を人のように捉えると、死から回避することも可能だと考えます。そのため、「家族みんながお母さんと仲良くしているから、お母さんは死なない」というように捉えることがあります。