「不整脈・心電図の異常」の記事一覧
15件/46件
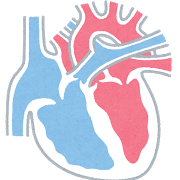
第13回<読み方・対応編⑪>洞不全症候群(SSS)
第3回目で洞性頻脈という不整脈を勉強しましたね。 これから勉強する洞不全症候群も「洞性」という言葉が含まれていますよね。「洞」=洞房結節なので、洞房結節が不全、つまりうまく働いていない疾患群という意味です。もっとかっこよく言うと、「洞不全症候群とは、洞房結節における
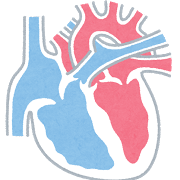
第12回<読み方・対応編⑩>完全房室ブロック
【関連記事】 心電図でみる房室ブロック(AVブロック)の特徴 ペースメーカーの仕組みと適応となる疾患 ▼不整脈の看護について、まとめて読むならコチラ 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント みなさんは房室ブロックという言葉を知っていますか?
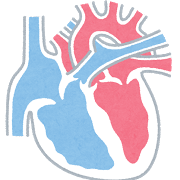
第11回 <読み方・対応編⑨>心室細動(VF)
心房細動は第5回目ですでに勉強しました。心房のいろいろな部分が小刻みに震えているのでしたよね。 心室細動も同様で、心室のいろいろな部分が小刻みに震えている状態です。 心房細動の場合、この小刻みに震えた心房でも、そのうちの何回かの電気刺激が刺激伝導系を伝って心室にた
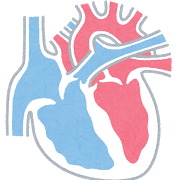
第10回<読み方・対応編⑧> トルサード・ド・ポアンツ(TdP)
トルサード・ド・ポアンツ。舌がもつれてしまいそうな名称ですよね。 読み方もトルサード・ド・ポアントとかポアンなどいろいろあます。 もともとの意味は、「棘波の捻れ」を意味するフランス語のようです。 私にはポアンと聞こえますが、特徴的な発音なので、だいたいどれでもみ
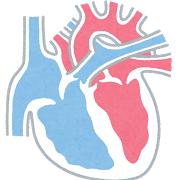
第9回 <読み方・対応編⑦>心室頻拍(VT)
▼関連記事 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント (1)心電図波形の特徴 第8回目で心室性期外収縮(PVC)を勉強しましたが、このPVCが3連発以上続く場合を心室頻拍(VT)(図)といったり、Short run(ショートラン)といったり
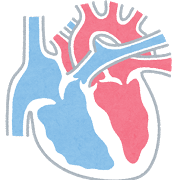
第8回<読み方・対応編⑥>心室期外収縮 (PVC)
(1)心電図波形の特徴 まずは期外収縮の意味を思い出してください(第4回参照)。 期外収縮とは、なんらかの理由で心筋の異常興奮が起こり、その結果、本来の収縮周期よりも早く収縮が起こることでしたよね。異常興奮の発生場所が心室の場合を心室期外収縮といいます(図1)

ペースメーカーの仕組みと適応となる疾患
ペースメーカーは脈が少ないことで、脳や全身への血流を確保できない人たちの心機能を補うために装着されます。ペースメーカーの基本的な仕組みと、適応となる疾患を抑えておきましょう。 ペースメーカーの仕組み ペースメーカーは、病的な徐脈を起こした疾患に適応され

植え込み型除細動器(ICD)の仕組みと適応となる疾患
ペースメーカーと似た機器に、植え込み型除細動器があります。適応となる疾患や、仕組みにも違いがありますので、しっかりと区別して覚えておきましょう。 ▼不整脈の看護について、まとめて読むならコチラ 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント 植え込
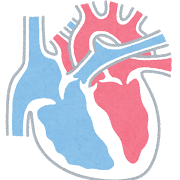
第7回<読み方・対応編⑤>発作性上室頻拍 (PSVT)
関連記事 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント 発作性上室頻拍(PSVT)は、症状の発生も収束も突然で、規則正しい頻脈(心拍数150~250回/分)であることが特徴です。心電図波形上も“突然起こり、突然終了する”一過性の波形が出現します。
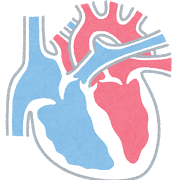
第6回<読み方・対応編④>心房粗動(AFL)
▼不整脈の看護について、まとめて読むならコチラ 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント 心房の興奮が250~350回/分のものを心房粗動、350回/分以上のものを心房細動といいます。 心電図を勉強し始めた学生時代、私は一文字違いの心房粗
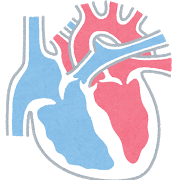
第5回<読み方・対応編③>心房細動(AF)
▼不整脈の看護について、まとめて読むならコチラ 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント (1)心電図波形の特徴 心房細動。読んで字のごとく、心房が細動している状態をいいます(図1)。 図1 心房細動 これは目に見えて、実際心
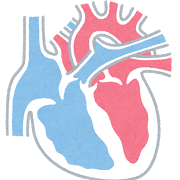
第4回<読み方・対応編②>上室性期外収縮(SVPC)または心房性期外収縮(PAC)
(1)心電図波形の特徴 みなさんは、期外収縮という言葉に馴染みがあるでしょうか。 期外収縮とは、次に出現する正常な間隔の波形よりも早く現れるものを指し、別名を早期収縮といいます。今回はこの期外収縮について、QRSの幅から上室性(心房性)を見分ける方法をお話しし
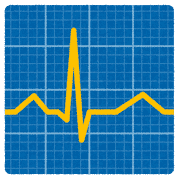
心電図でみる心房期外収縮(APC)の特徴とは?
心電図で見る特徴 洞調律よりも早くにP波が出現し、形がほかと異なる(異所性P波) 心房期外収縮(APC)についてまとめました どんな不整脈? 本来の洞結節からの電気的興奮より早く、心房内および房室接合部付近に起こる異常興奮です。加齢とともに
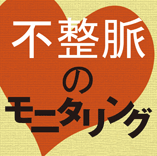
ジギタリス中毒、脚ブロックで見られる特徴的な波形
今回は、疾患以外で見られる特徴的な波形、ジギタリス効果で見られる波形と脚ブロックで見られる波形について解説します。 ジギタリス効果(ジゴキシン) 心筋の収縮力を高め(陽性変力作用)、徐脈を生じさせるため(陰性変時作用)、主に心不全及び頻脈性不整脈に対して用いら

疾患で特徴的な波形(QSパターンや異常Q波、冠性T波、STの変化)
不整脈の原因は加齢のほかに、遺伝的な疾患や心疾患があります。こうした疾患の心電図では、特徴的な波形がよくみられます。 心電図では、波形の異常と不整脈が合わさった波形が描かれることもあるので、不整脈とともに波形の異常も把握しておきましょう。 急性心筋梗塞 急


