「教育・指導」の記事一覧
15件/32件

日本看護学教育学会第34回学術集会 共催セミナー「基礎教育と継続教育が連動した職業的アイデンティティの形成支援 -看護に価値をおき、いきいきと働く新人看護師育成-」
2024年8月19日、日本看護学教育学会 第34回学術集会において、「ナース専科 就職」との共催セミナー「基礎教育と継続教育が連動した職業的アイデンティティの形成支援 -看護に価値をおき、いきいきと働く新人看護師育成-」(東京都新宿区・京王プラザホテル)が開催され、新人看護師の職
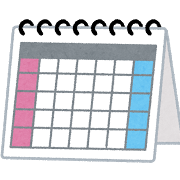
看護教育研究学会 2024年度研修会 開催のお知らせ
看護教育研究学会は、看護および看護教育に関する研究を発信し、看護学の発展に寄与するとともに、看護職者の資質の向上を図ることを目指しています。 テーマ 発達障害傾向のある人を理解し、看護教育に生かす 日時 2024年9月14日(土)9:30-16:00
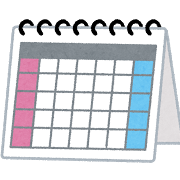
看護教育研究学会 第16回看護教育研究学会学術集会開催のお知らせ
看護および看護教育に関する研究を発信し、看護学の発展に寄与するとともに、看護職者の資質の向上を図ることを目指して2006年に設立された看護教育研究学会は、看護実践力や技術力,教育指導力の向上を目指す学会です。 日時 2022年10月22日(土)9:30-17:00(予
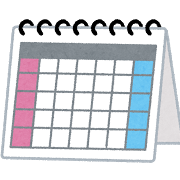
看護教育研究学会 2022年度研修会開催のお知らせ
看護および看護教育に関する研究を発信し、看護学の発展に寄与するとともに、看護職者の資質の向上を図ることを目指して2006年に設立された看護教育研究学会は、看護実践力や技術力,教育指導力の向上を目指す学会です。2022年の研修会開催が決定しました。 日時 2022年9月

看護におけるリフレクション
ここでは看護におけるリフレクションについて、基本的な知識について解説します。 【関連記事】 ● リフレクションの活用 準備編● リフレクションの活用 実施編 リフレクションとは リフレクション(reflection)は、「振り返り、反省、内省」と

いつでも・どこでも・誰でもレクチャー~認知症対応力向上を目指した院内教育ガイドの作成~
※「2.院内教育ガイドの作成」以下の閲覧はログイン(登録無料)が必要です。 1.認知症対応力向上を目指した院内教育ガイド作成の経緯 日本の後期高齢者人口、認知症高齢者人口が急増するなかで、療養場所を問わず、看護師には、加齢に伴う認知機能障害や認知症について知

どうすればうまくいく? 看護学生への教え方
組織の中心となって実習指導をする中堅看護師が、普段の指導内容を振り返り、問題や課題を解決する糸口になるような「教え方」のポイントを紹介します。また、これから実習指導を行う人は、実習指導に向けての心構えや準備の参考にし、実習指導のスキル向上に役立てていきましょう。 ※

中堅・ベテラン看護師への指導術3つのポイント
※「ポイント2:「相談」という形でお願いする」以下の閲覧はログイン(登録無料)が必要です。 行動変容を促すための3つのポイント すでに独自のやり方をもっている中堅・ベテラン看護師に対し、行動変容を促すことは容易ではありません。まずは話を聴き、信頼関係を構築し

3つのステップでわかる! 中堅・ベテラン看護師への指導術
プライドが高く、よかれと思って助言しているのに、全く聞く耳をもたない・・・・・・。そんな中堅・ベテラン看護師への指導に苦労している人も多いのではないでしょうか。ここでは、明日から活用できる中堅・ベテラン看護師への具体的なかかわり方と、指導者自身の成長にもつながるような、指

シャドウイングの実施と指導のポイント
シャドウイング(シャドーイング)とは シャドウイングは、ロールモデルの後ろを影のようについて同行する学習方法です。実際の現場における経験からしか学べないことを学習するために行われます。経験と知識を結び付けることにより、学びが深まることが期待できます。 シャ

CKD看護にあたってコーチングを学んでみたいあなたへ
※「研修を受けたら即、使えるわけではない」以下の閲覧はログイン(登録無料)が必要です。 看護師がコーチングのスキルを身につけるには 資格認定制度とスキルの獲得 CKD患者の生活を支えるための指導には、専門的な知識・技術・コミニュケーションス

【スタッフへの指導】パニックになるスタッフ
Q. 少しのアラームでパニックになるスタッフや精神的に弱いスタッフをどのように指導していけばよいでしょうか? 苦手意識が強く、少しのアラームでもパニックになるスタッフがいます。ナースコールやイレギュラーな処置が重なってもパニックになってしまいます。 また精神的

【新人・後輩指導】失敗を繰り返す、叱るとむくれる新人・後輩
Q. メモをとらず、同じ失敗を繰り返してしまう新人看護師や叱るとむくれてしまう後輩看護師には、どのように対処すればよいですか? 患者によい看護を提供するためには、まずは新人や後輩看護師への指導が大切だと思っています。 しかし、最近の新人は、何度も説明したうえで

12.看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則が活かされる医療現場
看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則のまとめ 前回の「11.看護と看護師のQOL向上と看護師に今後求められる能力とは」では、AIにより発展する今後の医療においても、看護と看護師のQOL向上が必要な理由を述べ、その中で看護師に求められる能力は、より個別的で多

10.看護師のQOL向上に重要な自己効力感を高める教育側のかかわりと対策
看護師自身のQOL向上に重要な自己効力感 前回の「9.相互作用で看護を高めあう人的技術方略と組織的な取り組み」では、相互作用で看護を高めあう人的技術方略として、カンファレンスなどのグループ討議で重要なファシリテーターによるファシリテーションスキルの研鑽が大切である


