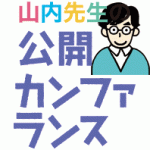第34回 「大丈夫ですか」の一言もなく淡々と…看護師としてどう思う?
第34回 「大丈夫ですか」の一言もなく淡々と…看護師としてどう思う?
- 公開日: 2016/4/8
- 更新日: 2021/1/6
医療者が患者の治療・ケアを行ううえで、患者の考えを理解することは不可欠です。
そこで、患者の病いの語りをデータベースとして提供しているDIPEx-Japanのウェブサイトから、普段はなかなか耳にすることができない患者の気持ち・思い・考えを紹介しながら、よりよい看護のあり方について、読者の皆さんとともに考えてみたいと思います。
患者さんが外来で初めて診断名を聞く。次に入院してこられるときには、既に治療の目的がはっきりしている状況です。
外来看護の機能や相談支援の充実が図られている昨今ですが、この間どのような心情を経験しているのか、患者さんの語りには示唆に富むものが多く含まれています。
自分のとった行動に意識的でありたい
病気の説明を受けた直後の場面について、ある方は次のように話しています。
27歳で乳がんの診断を受けた女性(インタビュー時33歳)
(前略)その手足がかたかた震えだして、涙はやっぱり出ないんですけども怖くて怖くって、もう手がすごく震えだしたのを覚えています。で、そうしていたら、看護師さんが入ってこられたので、少し、ほっとして。あ、看護師さんがきっと慰めてくれるんだろうと思って、期待して待っていたんですけど。「10日後に手術がもう決まりましたので、今から入院説明を始めます」っていう、「大丈夫ですか?」の一言もなく、ほんとに淡々と説明が始まったので、自分も「はい、はい」って聞いてはいたんですけど、全く頭に入らなくて。で、一通り説明が終わって、で、看護師さんがおっしゃったのが「今は、動揺しているでしょうから、あとで、この紙、読んどいてください」って置いていかれて、そのまま、またいなくなられて。で、「あれー?」って、「慰めてくれるもんじゃないんだな」とそのときすごく感じたのを覚えています。
「NPO法人 健康と病いの語り ディペックス・ジャパン > 乳がんの語り」より
私は、この語りを聞いてショックを隠せませんでした。そして、少なからず自分のかかわった病名説明の場面、また自分が患者として受療した際の同様の場面を思い起こしました。
私は、看護師の方々とこのような患者さんの語りを読みあって、思いを共有する活動を行っています。その際看護師から出てくる言葉は、「かかわりたくても時間が無い」「継続できないなら(踏み込むことを)あえてやめておこうと思ってしまう」などの後悔、反省が少なくありません。あらためて現場の苦しい気持ち、悩みつつ前に進もうとする気持ちを共有させていただけることに力強さを感じるとともに、気持ちを分かち合うことで何か解決の糸口が見いだせないかを考えます。
私も以前、「患者さん、今どう思っただろう」「来週の外来までどうやって過ごすだろう」と後ろ髪をひかれつつ、機械的・あとまわしの対応となったことがいくつもあります。自分の力量に自信がなかったり、継続してケアを行うシステムが充分でないなどと他の理由をつけたりしていたことも否めません。
私たちにとってそれは多数のうちの一場面であっても、患者さんにとって同じ時間、同じ場面は二度とないと言えるでしょう。看護とは一回性の営みであり、私たちのかかわりが瞬時瞬時の積み重ねであるゆえんであると思います。
病名を知った時、またその後日常生活を続ける中で、患者さんがどのように思い病気と向き合っているかを知ることは簡単なことではありません。それは、自分の気持ちもそうであるようにずっと一定であるものでもありません。交代勤務の中で、常により良い方法を考え、一定の質を保ちつつメンバー間でそれらを共有することは、本当に難しいことです。
しかし、その後のかかわりや効果的なケアが可能かどうかはさておき、自分の取った行動がどうであったかについては、意識的でありたいものです。あえて関わらなかったのか、残念ながら“今日は聞き流す”結果となってしまったのか、そこにスタッフ間でどんなケアの判断があったのか…などについて、私たちは振り返ることを忘れてはならないと思います。
おそらく先の当事者の方然り、多くの方はこの時に抱いた感情を私たちに教えてはくれません。“苦情申し立て”のような場を容易にもたない私たちは、これら届かない患者さんたちの声に、どうすればアクセスできるでしょうか。
自分の関わり方を振り返る材料として、患者さんの語りや闘病記に触れながら、ギャップを埋めることに少しでもつながらないか、考えあぐねる日々が続きます。
「健康と病いの語り ディペックス・ジャパン」(通称:DIPEx-Japan)
英国オックスフォード大学で作られているDIPExをモデルに、日本版の「健康と病いの語り」のデータベースを構築し、それを社会資源として活用していくことを目的として作られた特定非営利活動法人(NPO法人)です。患者の語りに耳を傾けるところから「患者主体の医療」の実現を目指します。