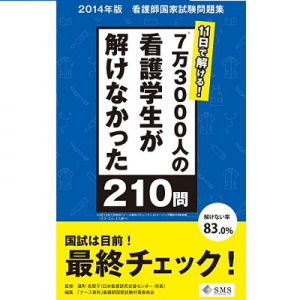持続的導尿とは? 知っておきたいポイント
持続的導尿とは? 知っておきたいポイント
- 公開日: 2016/11/26
導尿は、尿道口から膀胱内にカテーテルを挿入して尿を排出させるケアです。導尿には持続的導尿と間欠的導尿があります。ここでは、持続的導尿について、その目的やケアを行うにあたり知っておきたいポイントを解説します。
持続的導尿とは?
持続的導尿は、尿閉などの排尿困難が続く患者さんや手術や処置などで安静が必要な患者さんに対し、膀胱内に貯留している尿を持続的に排泄させるために行います。また、排泄した尿は蓄尿バッグにたまるため、尿量の測定や水分出納の厳密な管理が必要な場合にも行われます。
それに対し、一時的に排尿させることをある時間をおいて繰り返すことを間欠的導尿と呼びます。これは、尿閉、無尿などの排尿困難がある場合や尿閉の鑑別が必要な場合などに行われます。在宅などで患者さんや介護者が行う導尿もほとんどが間欠的導尿です。
持続的導尿も間欠的導尿も、カテーテルにより尿を排泄するためのルートをつくることには変わりありません。ただし、持続的導尿では、持続的にカテーテルを膀胱内に留置する必要があるため、先端にバルーンがついた膀胱留置カテーテルを用います。
患者さんの羞恥心に配慮する
導尿は患者さんにとって、羞恥心や苦痛を伴うケアであることをよく認識しましょう。
患者さんに声をかけるときは、周囲に聞こえないようにし、ケアを行う前にはカーテンなどでベッドサイドを覆って周囲から見えないようにします。また、ケアの際はなるべく露出部分を少なくするなど、患者さんの羞恥心に十分に配慮しましょう。
清潔・不潔区域を認識し無菌操作で行う
持続的導尿、間欠的導尿ともに、尿路感染を防ぐためにカテーテルの挿入は無菌操作で行います。そのため、清潔・不潔区域をしっかりと区別し、ケアを行う必要があります。また、ベッド上の作業スペースの確保と必要物品の配置にも注意しましょう。
物理的な尿道粘膜損傷を避ける
尿路は粘膜であり、また目で確認できないため、損傷しやすい部位です。尿路の損傷は、感染の要因ともなります。正しく適切なカテーテルの操作や固定法を習得し、十分に注意してケアを行いましょう。そのためには、尿路の構造など解剖生理の正しい知識をもつことも必要です。
カテーテルの挿入中や留置後は患者さんの観察を怠らないようにします。もし挿入が困難だったり、出血などの異常がみられたら、操作を中断し、医師に報告しましょう。
尿路感染の発生を防ぐ
持続的導尿では、持続的にカテーテルが留置されているために、尿の停滞や逆流から尿路感染のリスクが高まります。尿路感染は、尿路結石、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎などを生じさせる原因となります。以下に、カテーテル留置中における感染予防と感染の早期発見のためのポイントを挙げていきます。
尿路を不潔にしない
シャワー浴、もしくはシャワー浴ができない場合は1日1回、陰部の洗浄を行い、陰部を清潔に保ちます。
蓄尿バッグは床につかない位置に設置し、歩行可能な患者さんには蓄尿バッグやカテーテルが床につかないように移動することを伝えます。
カテーテルと蓄尿バッグの交換は必要に応じて行う
かつて、膀胱留置カテーテルは1週間、あるいは2週間ごとに定期的に交換することが推奨されていました。しかし、現在ではカテーテル交換が微生物の新たな侵入の機会となり、むしろ感染のリスクを高めることがわかってきました。
CDCガイドラインでは、「膀胱留置カテーテルとそれにつながる回路(接続チューブや蓄尿バッグは定期的な交換をすべきではなく、回路汚染や感染徴候が確認された場合に適宜交換すべきである」と勧告しています。
使用期間ではなく、患者さんの免疫力の状態や尿の性状をよく観察し、状況に応じて適切な時期に交換することが大切です。
感染徴候を見逃さない
感染を早期に発見するために、発熱などの症状や尿の性状の異常などを見逃さないようにします(表)。
| 尿の性状 | 尿混濁、浮遊物、血尿 |
| 患者さんの観察 | 発熱、外尿道口の発赤、浮腫、分泌物 |
| 患者さんの訴え | 下腹部の違和感、下腹部痛、陰部の掻痒感・不快感、排尿痛、頻尿、残尿感 |