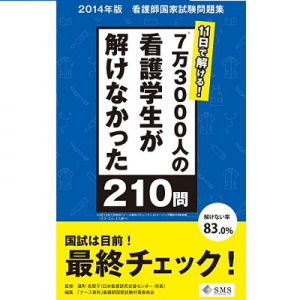8.看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則を活かすための看護教育風土づくり
8.看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則を活かすための看護教育風土づくり
- 公開日: 2019/10/9
看護の臨床現場での具体的な看護教育風土づくりとは
前回の「7.看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則の活用方法~トレーニングの実際~」では、看護教育の役割担当者のオフ-ザ-ジョブ-トレーニングで具体的に何をトレーニングするとよいのかについてお伝えしました。
また、日々のオン-ザ-ジョブ-トレーニングとして、「看護を考え抜く力」を活用して研鑽することが重要だということをお伝えしました。
今回は、看護の臨床現場で、看護のQOL向上のWIN-WINの法則を活かすための具体的な看護教育風土づくりとして、時間の概念と個々の価値観の見直しの重要性とその方法、効果的な集団教育対策について考えたいと思います。
時間の概念と個々の価値観の見直しを支援するような看護教育風土づくりが重要
第7回までの連載の中で、QOL向上のWIN-WINの法則を活かすためには看護教育風土が重要だということを、何度かお伝えしました。
しかし実際の看護業務では、同時に複数の患者さんに対応する場面に直面したときも、優先順位を考えて行動し、安全な看護を提供しなければならない多重課題への対応が必須です。そのため日々業務に追われることが多く、業務を行う中で安全を守るための対策が話し合われるという教育方法がとられることがほとんどであるといえます。
この方法では、十分な教育とはいえず、新人看護師は自分で「上手な時間の使い方」を身につけていくことが必要になってきます。
その一方で、看護業務を実施するうえで、「他の人の力をうまく借りられるか?」「効率よい進め方がほかにないか?」「どうやったら緊急度と重要度をうまく判断できるのか?」などに対する答えを、看護の初心者が業務をしながら見出すことがいかに大変なのかは、学生の実習指導や新人教育の中で痛感してきました。
私自身の経験でも、業務に追われながらそれを見出すことは容易ではありませんでした。
私は、教えてもらえる機会が少なく、自分で身につけることが求められる「上手な時間の使い方」を教育や研修として話し合い、見出す機会も重要だと思います。また、個々の価値観により人の行動は左右されますが、自らの行動の特徴は容易には理解できないため、先輩や教育担当者が助言することなどが大切だと思います。
ただ、このような教育や研修を実施した経験のある職場もあると思いますが、「上手な時間の使い方」はすぐに身につき、改善できるものではないため、効果的な研修だという評価を受けにくく、教育や研修の内容としてふさわしいものとして浸透しない場合もあると感じます。
教育や研修以外に教えてもらえる機会として、ある程度の年月が経って現場でも信頼を得た状況のときに、自然と先輩たちが自分たちの「コツ」を教えてくれることがあります。また、そのくらい経験を積めば先輩の仕事ぶりを参考にしてマネをする余裕もできます。
近年では、この視点に注目して「コツ」を簡単に教えてくれる教育風土の職場もあり、そのほうが比較的早く「時間の使い方」を身につけ、業務ができるようになる様子です。
一方、早く業務ができるようになると「時間の使い方」を自分で苦労して身につけないから簡単に離職するのではないかという考えもあり、現在は「教えてくれる教育風土」と「自分で苦労して身につける教育風土」に二極化している傾向ではないかと感じます。
しかし私は、「コツ」を簡単に身につける、もしくはすべて自力で見出すという両極端の対策よりも、時間の概念と個々の価値観の見直しを支援されるような教育風土で、業務のコツ以外に何が重要であるのかを自分で見出すような能力を身につけるほうが、専門職として重要ではないかと考えます。
見直しの方法と意図的な集団教育の必要性
時間の概念については、第1回の連載において、看護のQOLは「丁寧=長時間」と考えられがちですが、物理的な時間の長さが看護のQOL向上につながるわけではないということを、臨地実習で遭遇する事例を通して具体的にお伝えしました。そして、丁寧とは何をもって「丁寧」と考えるのか……によって、“看護のQOL向上=時間がかかる”という既存の概念が崩れ、看護と看護師のQOLの向上も相反しないのではないかということをお伝えしました。
この概念の見直しでは、長時間かけないケアやかかわりを受けた患者さんのQOLが向上したかどうかを慎重に見極めることが重要となります。
QOLの向上には、適切なかかわりやケアがその患者さんに合ったタイミングで行われることが重要であり、看護師自身が個々の患者さんのペースに合わせることを意識して、自分の時間の使い方やタイミングを見直すことが対策となります。
また、どんな人間にも「自分の行動には癖がある」ことを念頭におくことが大切だと思います。行動に癖があるということは、時間の使い方にも「自分の癖がある」ことを意識して、見直す必要があります。
個々の価値観の見直しも同様です。「自分の行動には癖がある」のですから、行動するときの優先順位をつける思考・判断にも自分の癖があります。それを意識することが重要です。
これには、どのような方法があるかというと、普段の自分の行動が仮に100とし、その割合が80:20となる場合の20を優先するように意識すると効果があるとされています。これは、「仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出している」1)というパレートの法則にのっとったものであり、経済学的にも社会現象学的にも見直されている内容です。
医療従事者として、時間の概念と個々の価値観の見直しを行い、より客観的に自分を見つめることで、行動が変化して、患者のQOLの向上を考えながらも看護師のQOLの向上につながるのではないかと思います。
また、見直しを行うときに留意したい点の提案があります。私は新人看護師のころ、一日の自分の行動を詳細に記述する「24時間タイムレコード」をつけ、それを見直すような集団教育を受けた記憶があります。
しかし、このときはタイムレコードをつける目的や見直す意味がわからなかったため、この集団教育は私の時間の概念と個々の価値観を見直す機会にはなりませんでした。
このように、集団教育を行うときは、時間の概念と個々の価値観を見直す理由を、集団教育の目的として明確にしてから実施するほうが効果的だと思われます。

引用文献
1)リチャード・コッチ:増補リニューアル版 人生を変える80対20の法則.仁平和夫,他訳.CCCメディアハウス,2018,p.21-78.