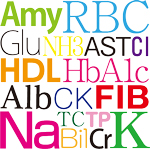第6回 造影CTを用いた病変の精査
第6回 造影CTを用いた病変の精査
- 公開日: 2015/11/5
造影されるものとされないもの
今回も前回に引き続きCT検査について述べたいと思います。単純CTと造影CT、皆さんは患者さまに造影剤を使うときには同意書を作成すると思います。その時に、”造影剤を使って詳しく調べます”であるとか、”病変を詳しく調べるためには、造影剤を使う必要があります”などと説明されているのではないでしょうか。
では、CTで造影剤を使うと何をどのように詳しく調べることができるのでしょうか。今回はその辺りについて少し書いてみようと思っています。
図1は a, b どちらも単純CTでは非常によく似た、均一な内容の腫瘤性病変として描出されています。前回解説した“X線の通りぬけにくさ”を示すCT値は、どちらも6.0程度と、ほぼ水と同様の値となっています。
図2はこれらののう胞性病変の精査のために、造影剤を急速静注して撮像したものです。a の病変の中には造影されるような部分は認められませんが、 b の病変の中には、壁の一部に、よく造影されるやや厚い部分があることがわかります。
“造影される”ということはどういうことでしょうか。造影剤は末梢の静脈から投与されたあと、肺動脈、静脈を通った後に動脈に入り、体内をめぐります。血管からはその透過性に従って血管外に染み出して、組織に分布します。
つまり”造影される”ということは、そこに血流があって、そこに分布している血管からは、ある割合で造影剤が血管から染み出しているのだ、ということに他なりません。壁が厚く、そこに造影効果があるということは、そこには、細胞の死骸や汚いものが沈殿していたりしているのではなくて、血流を受けて活動している細胞がある、ということを意味しています。
そして、この症例の場合は腎細胞がんです。造影するのは、単に”見やすくする”どいうことではなくて、造影することによってわずかに存在する異常な細胞を見つけだすことができて、それは病変の性質の評価の重要な鍵になるからなのです。