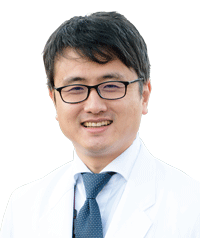チーム医療で支える在宅自己注射(喘息)【PR】
チーム医療で支える在宅自己注射(喘息)【PR】
- 公開日: 2022/6/15
ひたちなか総合病院呼吸器内科では、デュピクセントによる治療を行う場合、在宅自己注射の導入を基本としています。
デュピクセントによる治療が決まると、医師、看護師、薬剤師などの多職種を含むチーム医療体制で、治療内容の説明~自己注射の導入~導入後のフォローまでを行っています。なかでも看護師は患者さんとの接点が多く、チーム医療体制の中で大きな役割を担っています。
そこで今回は、ひたちなか総合病院呼吸器内科の山田英恵先生、外来看護師の戸辺幸江先生、中央処置室看護師の清水洋子先生にお話を伺い、自己注射によるデュピクセントの導入~フォローの流れとそのポイントについて、ご解説いただきました。
参考になった
-
参考にならなかった
-