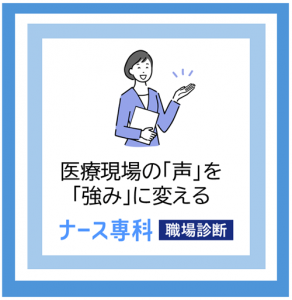1要因実験計画|“実験計画”の考え方①
1要因実験計画|“実験計画”の考え方①
- 公開日: 2025/4/3
この記事はPDFでもご覧いただけます。ダウンロード、保存等して、お役立てください。
PDF版はこちらからご覧ください。
1.実験とは
看護研究と言えば、どのような研究方法が思い浮かぶでしょうか。研究対象者へインタビューを行ったり、アンケートを配布したり、もしくは実際のフィールドで観察をしたりすることがイメージしやすいのではないでしょうか。今回、本稿で紹介するのは実験研究についてです。実験に対して、さまざまなイメージを持たれると思いますが、実験の実施において、必ずしも大掛かりな装置は必要ではありません。また、実験の目的によっては、そのデータ収集方法として、インタビューやアンケートを利用する場合もあるでしょう。
実験は、原因と結果の関係を探るための実証的な研究方法です。実験研究の大きな特徴としては、原因と思われる変数(これを独立変数と呼びます)を操作することが挙げられます。実験者は、独立変数を操作することで、得られた結果(これを従属変数と呼びます)がどのように変化するのかに関心があります。独立変数と従属変数の因果関係を明確にするためには、従属変数に影響を与える可能性がある他の変数(これを剰余変数と呼びます)を統制することが必要です。どのような独立変数を操作し、どのような従属変数を測定し、そしてどのように剰余変数を統制するのか、これらについて考えられた設計図が実験計画です(図1)。
図1 実験研究とは

2 1要因の実験計画を考える
2-1 独立変数を操作し、従属変数を測定する
独立変数の設定とは
実験計画の仕組みを理解しやすくするために、ここでは1つの例を考えてみましょう。例えば、看護師のユニフォームの色によって、患者さんなどの他者に与える印象の違いについて興味を持ったとします。この場合、実験の方法としては、色が異なるユニフォームをいくつか用意し、実験参加者にその印象(好感度など)を評定してもらう方法が考えられます。この例では、独立変数に当たるのが「色」であり、この独立変数である「色」は要因とも呼ばれます。つまり、「色」という1要因の実験計画を立てることになります。
次に、ユニフォームの色として白・ピンク・紺を用意したとしましょう。色要因に含まれるそれぞれの色は水準と呼ばれます。つまり、色という1つの要因に、白・ピンク・紺という3つの水準を含む実験デザインということになります(図2)。実験では、この3色について実験参加者に呈示することになりますが、このような手続きが「独立変数を操作する」ということになります。実際の研究では、選定した色の組み合わせによって、得られるデータが変わる可能性があります。そのため、どのような水準を設定するのか、そして、水準をいくつ設定するのかについては、先行研究や実験が想定する現場の実情などを参考に検討する必要があります。
図2 実験デザイン

従属変数の測定とは
このような実験計画のもと、従属変数として、そのユニフォームを着ている看護師への好感度を測定するとしましょう。好感度はやや抽象的な概念ですので、本来はその定義をあらかじめ考えておく必要があると思いますが、ここでは参加者がイメージやすいように一般的な理解としての「好感度」を従属変数とします。好感度の測定として、例えば、各色に対して1つずつアンケート(5段階評価など)に回答してもらう方法が考えられるでしょう(図3)。通常、ヒトの反応にはゆらぎがあるため、個人内であっても毎回同じ回答が得られるとは限りません。研究の目的や方法により、同一条件について繰り返し測定することもあります。また、個人間でも反応にばらつきがあるため、複数の参加者に回答してもらうことが必要です。
図3 ユニフォームの色による看護師への好感度測定
ここでは、ひとまずアンケートで好感度を評価してもらうことを例に話を進めます。白色のユニフォームについて評価した後に、ピンク色のユニフォームを評価した場合、白色の評定がピンク色の評定に影響してしまう可能性が拭いきれません。そこで、そのような順序効果を相殺するために、実験の各試行において評価する色の呈示順序を変えつつ、各色に対するデータを取得する必要があります。
2-2 剰余変数を統制する
条件を等しくする
この実験では、1要因3水準の実験操作をし、従属変数を測定していきます。もし、色によって評定の違いがあった場合、それは本当に独立変数の影響によるものと言えるでしょうか?
実験操作以外の他の要因の影響がなければ、その評定の違いは色の違いによって生じたと考えられますが、この「条件を等しくする」状況を作り出すことは容易ではないのです。実験者は、従属変数に影響を与える可能性がある剰余変数を最大限取り除くことができるように、実験計画を立てる必要があります。
例えば、白色のユニフォームはワンピースタイプを用意し、ピンク色や紺色のユニフォームではパンツスタイルを用意してしまうと、ユニフォームの好感度に影響したのが、色の違いなのか、型(スタイル)の違いなのかわからなくなります。そのため、このユニフォームのスタイルについては、研究目的(実験操作の対象)に含まれていないのであれば、どの色においてもスタイルを同じにしておく必要があります。もし、このスタイルの違いによる影響についても関心があるのであれば、次稿で説明する2要因の実験計画を立て、色要因とスタイル要因を実験操作することになります。また、細かいことに感じるかもしれませんが、実験参加者にどのような場所で評価してもらうのかについても考えなければなりません。暗い部屋で評価する場合と、明るい部屋で評価する場合では、印象が変わってしまう可能性があるからです。実験のたびに部屋の明るさが変わってしまっては、その影響により、実験結果の解釈が出来なくなりますので、こうした実験を実施する環境も統制する必要があります(図4)。このような点に留意しながら、剰余変数の影響を統制し、3色のユニフォームはすべてパンツタイプに統一し、実験環境は毎回同じ部屋で同じ明るさになるようにセッティングしたとします。
図4 不適切な実験条件

評価する際の注意点
それでは次に、実験参加者にユニフォームを評価してもらう際、どのようなことに気を付けたらよいでしょうか。実験計画では、1 人の実験参加者にすべての条件を実施してもらう場合(参加者内計画)と、各条件で別の実験参加者に実施してもらう場合(参加者間計画)があります。
参加者内計画
まず、参加者内計画の場合、実験参加者は白・ピンク・紺のユニフォームのすべてを評価することになります。参加者内計画の良い点は、参加者個人の特性が同一である人物から得られるデータから、条件ごとの比較検討ができることにあります。もし、色への関心が強く、服飾のデザインにこだわりがある人と、全くこだわりがない人がいたとします。こだわりがある人は呈示されたユニフォームから、色ごとに異なる好感度を示すかもしれませんし、こだわりがない人は特に考えることなくすべての色において似たような好感度を示すかもしれません。参加者内計画では、1人の実験参加者がすべての条件を実施するため、こうした個人要因を統制することに繋がります。ただし、1人の参加者がすべての条件を実施するため、最初に呈示された色の評定が、次の色の評定に影響が出てしまう可能性があります(ピンクや紺の後に白を呈示されると地味に見えて、評価が下がってしまうなど)。もし、実験参加者全員に対して、同じ順番でユニフォームを呈示してしまうと、そのような順序効果を排除できないことになります。そのため、ある参加者は白→ピンク→紺の順、別の参加者は紺→ピンク→白の順のようにユニフォームを呈示する順序に偏りがなくなるように入れ替えていきます。このような手続きを実験条件のカウンターバランスを取ると表現します。
参加者間計画
次に、参加者間計画の場合、それぞれの参加者は、3 色のうちの1 色だけを評価することになります。多くの条件があったり、1条件の実施の負担が大きい実験であったりする場合は、参加者間計画の方が参加者への負担は少ないでしょう。しかし、先ほど例に挙げたように、ある色を評価する実験参加者群の中に、色へのこだわりが強い人(あるいは、こだわりがない人)だけが偶然集まってしまうと、つまり、参加者の特性が群内で偏ってしまうと、その色への好感度を適切に評価することができなくなってしまいます。それでは、このような実験参加者の偏りを最小限にするためにはどのようにしたらよいでしょうか。今回の場合は、実験参加者を白・ピンク・紺の3つの条件に割り当てるわけですが、その代表的な方法として無作為化(ランダム化)が挙げられます。文字通り、参加者をランダムに各条件に割り当てるという方法です(似ている言葉として、無作為抽出という用語がありますが、両者は異なることを表しています)。しかし、実験参加者の数が多くはない場合、無作為化をしたとしても、実験参加者の特性に偏りが出てしまう場合もあります。そうした場合は、従属変数に影響がありそうな実験参加者の特性について事前に測定しておき(色へのこだわりなど)、その特性が同程度の参加者を各条件にランダムに割り当てるという方法も考えられます(図5)。
図5 参加者内計画と参加者間計画

その他にも、実際の研究場面では、研究目的に合わせて、どのような対象者を選ぶのか(通院頻度の高い高齢者に限定するなど)を検討する必要があります。研究期間や予算の制約といった問題もあるかもしれません。また、ここで紹介した剰余変数以外にも、実験者が気づかない剰余変数もあると思われます。
このように剰余変数を統制するということは容易ではありませんが、可能な限り統制しようとすることが、実験研究の精度を左右することでしょう。
3 まとめ
実験研究においては、原因となる独立変数の操作、結果となる従属変数の測定、そして従属変数に影響をおよぼし得る剰余変数の統制、それらの方法を十分に検討し、計画を立てることが重要です。ここでは1要因という比較的シンプルな実験計画を例に挙げましたが、2要因以上の実験計画を理解する上でも、こうした基本的な考え方を理解することが大切です。
この記事はPDFでもご覧いただけます。ダウンロード、保存等して、お役立てください。
PDF版はこちらからご覧ください。
参考文献
●南風原朝和:心理統計学の基礎-統合的理解のために.有斐閣,2002.
●高野陽太郎・岡隆,編:心理学研究法-心を見つめる科学のまなざし〔補訂版〕.有斐閣,2017.
●古谷野亘・長田久雄:実証研究の手引き-調査と実験の進め方・まとめ方-.ワールドプランニング,1992.
●天野成昭:心理実験のキーポイント.日本音響学会誌 2018;74(12):641-48.