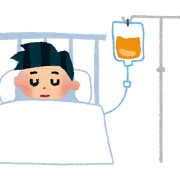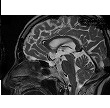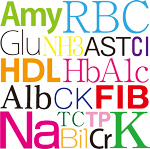 【肝炎】メカニズムと検査値編
【肝炎】メカニズムと検査値編
- 公開日: 2014/3/22
臨床の現場で検査値を活用していくためには、疾患のメカニズムとのかかわりを念頭に置きながら読み取っていくことが大切です。臓器の働きや疾患がどのようにして起こるかを確認し、検査値の動きと読み取るためのポイントを解説します。
肝炎のメカニズム
肝炎は80%が肝炎ウイルスによって発症する、びまん性の肝の炎症です。病型には、発症からおよそ4〜6週間で完治する急性肝炎、6カ月以上の肝機能異常とウイルス感染を維持する慢性肝炎があります。
ウイルス性肝炎は、ウイルス自体が肝細胞を破壊するのではなく、肝臓に侵入した肝炎ウイルスに対して体内の免疫システムが働き、ウイルスが定着している肝細胞を破壊してしまうことで起こります。
肝炎ウイルスには、A型、B型、C型、D型、E型のウイルスがあり、そのうち急性肝炎のみを発症するのはA型とE型で、それ以外は慢性化することがあります。特にC型肝炎の慢性化とB型肝炎の劇症化には注意が必要です。
治療は、急性肝炎→慢性肝炎から、肝硬変→肝がん・肝不全への進展を阻止することを目的に行われます。
このほか、自己免疫性肝炎、薬剤やアルコールが原因になる肝炎があります。
自己免疫性肝炎は中年以降の女性に多く、慢性に経過する肝炎です。自己抗体の関与により肝細胞が障害されると考えられています。
薬剤性肝炎は、薬剤が直接的に肝細胞に炎症を生じさせる場合、薬剤の代謝過程で肝細胞障害を生じる場合、アレルギー性に炎症が生じる場合などがあります。
肝臓は代謝・解毒機能を担う臓器なので、さまざまな酵素を合成しています。肝臓に炎症が起きることによって、AST(GOT)とALT(GPT)が発症初期から血液中へ逸脱し、高値を示します。急性肝炎では通常AST(GOT)、ALT(GPT)の順に下降して約2カ月で正常化します。
肝臓は何をしている臓器か?
- ●中間代謝(糖代謝、脂質代謝、蛋白質代謝)
- ●胆汁の合成・分泌
- ●薬物代謝・解毒
- ●ビタミン・鉄の貯蔵
- ●循環血液量の調節
- ●血液の浄化

ウイルス攻撃のメカニズム
続いては、「肝疾患を疑うときに行う検査と検査値」についてです。
“肝疾患”で行う臨床検査
- ●血液生化学検査
- ●尿検査
- ●画像検査(腹部エコー、CT、MRI、上部消化管内視鏡)
- ●ICG(インドシアニングリーン)試験
肝炎を示す検査値
UP
高度上昇
- ●AST(GOT)
- ●ALT(GPT)
- ●LD
軽度~中等度上昇
- ●ALP
- ●γ-GTP
DOWN
- ●Alb
- ●ChE
所見
- ●HAV 抗体(IgM-HA 抗体)
- ●HBs抗原
- ●HBe 抗原
- ●HBe 抗原
- ●HBV 抗体(IgMHBc抗体、HBe 抗体、HBs 抗体)
- ●HCV 抗体
- ●HCV 抗体
- ●HDV 抗体
- ●HEV 抗体
判断のカギ「AST(GOT)」「ALT(GPT)」「ChE」
AST(GOT)とALT(GPT)は、細胞が破壊されたときに血中に逸脱して血中濃度が上がる、代表的な逸脱酵素です。
AST(GOT)は心筋、骨格筋などにも存在するため、AST(GOT)の高値=肝障害とはいえないので、肝臓に特異性の高いALT(GPT)と合わせて見ることが大切です。
肝炎であればAST(GOT)とALT(GPT)はそろって高値を示しますが、AST(GOT)が高くても、ALT(GPT)が低ければ、肝臓以外の臓器の障害である可能性が高くなります。
また、これらの値は細胞がどの程度壊れているかを示すもので、肝機能そのものの障害を示すものではありません。肝臓は実質細胞が3縲怩S割程度残存すれば、その機能をほぼ保つことができます。
肝機能については、肝臓が何をしている臓器かを考えることが重要です。
肝臓では蛋白質をはじめとする物質の合成や代謝などを行うので、蛋白合成能が低下したときに低値を示すChEやアルブミン、総コレステロール値などによって機能を評価します。
これらの数値の低下は、肝機能の低下を意味します。AST(GOT)やALT(GPT)はそれほど高値ないにもかかわらず、ChEやアルブミンなどが明らかに低下している場合には、肝疾患はかなり進行し、肝硬変に移行していると考えられます。
次回は「肝硬変のメカニズムと検査値」について解説します。
(『ナース専科マガジン』2012年8月号から転載)
カテゴリの新着記事

自己免疫性肝炎の重症度分類
自己免疫性肝炎の重症度分類は何を判断するもの? 自己免疫性肝炎の重症度分類は、自己免疫性肝炎の重症度を臨床所見と臨床検査所見から評価するスケールです。 自己免疫性肝炎は中年以降の女性に発生する頻度が高く、初発症状として倦怠感、黄疸、食思不振などを認めます。適切な治療を