記事一覧
15件/4080件

第47回 治療の決め手になるもの
医療者が患者の治療・ケアを行ううえで、患者の考えを理解することは不可欠です。 そこで、患者の病いの語りをデータベースとして提供しているDIPEx-Japanのウェブサイトから、普段はなかなか耳にすることができない患者の気持ち・思い・考えを紹介しながら、よりよい看護のあり
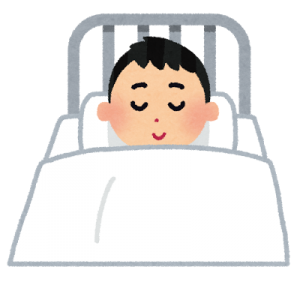
第1回 ある日気づいたタオル類の処理に潜む、院内感染のリスク【PR】
企画協力:株式会社エラン 入院時に必要な物品がまとまったCS(ケア・サポート)セット。株式会社エランが提供するこのサービスを全面的に導入し、感染予防をはじめ、看護師の業務効率の改善、患者さん・家族の負担軽減に大きな効果があった嘉麻(かま)赤十字病院の事例を、

CASE06 患者さんのために臆することなく積極的に医師との連携を!
困難事例6 下肢の難治性褥瘡を疼痛コントロールしているターミナルのケース 脊髄損傷から寝たきりのAさん(70歳、女性)。 長年、誤嚥性肺炎を繰り返し、治療を続ける間に、ほとんどの抗生剤に耐性がついてしまい難治性肺炎となった。 病院からは「入院していても肺炎に関し
口腔粘膜炎があるときの食事の工夫は?
▼がん化学療法についてまとめて読むならコチラ がん化学療法とは?副作用の出現時期や症状別の看護 口腔粘膜炎の重症度に合わせて食形態を変える 口腔粘膜炎で痛みがあっても、栄養状態が悪化しないようにするためには、できるだけ経口摂取を行うよう努めます
【フライの倫理原則】看護倫理を考える5つのチェックポイント
5つのポイントをチェックしよう ジレンマの原因がどこにあるのか、それらが倫理的にどのような問題を含んでいるかを見極めるためには、それぞれの行為が倫理的に正しいかどうかを点検してみる必要があります。その方法にはいろいろありますが、この連載では、フライの倫理原則に
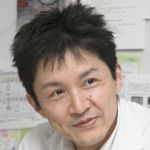
第30回 摂食嚥下障害の臨床Q&A「剥離上皮(痂皮)の取り方を教えてください」
上顎に剥離上皮がついているのですが、乾燥していてなかなかとれません。時間を掛けずに取る方法を教えてください。 上顎(以下、口蓋)に着く汚れには痂皮、剥離上皮、痰などがあります。痂皮は血液成分、滲出液、膿などが再生上皮の角質層に移行し凝固・固着したものです。剥
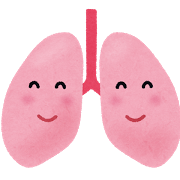
【呼吸ケア・看護まとめ】呼吸の検査、評価・観察項目など
呼吸ケアとは 呼吸ケアとは、人工呼吸器装着患者さんのケア、吸引、体位ドレナージなど多岐にわたります。また、呼吸ケアを行うにあたっては、血液ガスデータをみたり、呼吸音を聴診したりとさまざまな技術や知識が必要となります。 普段から何気なく行っている呼吸ケアですが、

第30回 たんぱく質と塩分制限をされている患者さん
[macoさん から提供された事例] 2型糖尿病で肝硬変(腹水あり)が既往にある患者さん。さらに糖尿病性腎症3期があり、医師からの指示ではたんぱく質1.0g/kg・塩分7gと制限されていました。理解力はあったため、良質たんぱく質の具体例・塩分制限・食後の安静などを指
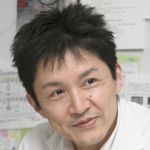
第29回 摂食嚥下障害の臨床Q&A「口腔内が全体的に白っぽいのですが、どうすれば良いですか?」
誤嚥性肺炎後の87歳女性、誤嚥性肺炎の治療後から口腔内が全体的に白い膜のようなものが出るようになりました。それと同時に口角炎が両側にも出て、出血することもあります。どのような口腔ケアの方法が良いのでしょうか。 誤嚥性肺炎の治療の多くは薬物療法で、抗生剤を

バイタル記録業務を自動化!時間外勤務が減り、看護の質も向上【PR】
看護の質の向上には、多忙化する看護業務の効率化が課題 岐阜県総合医療センター [後方] 左:久世看護師長 右:石原主査 [手前] 左:田垣看護部長 右:山中副看護部長 久世看護師長: 当院では平成18年11月に電子カルテを導入しましたが、バイタル測
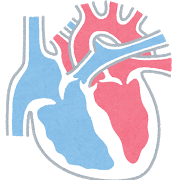
第5回<読み方・対応編③>心房細動(AF)
▼不整脈の看護について、まとめて読むならコチラ 不整脈の看護|検査・治療・看護のポイント (1)心電図波形の特徴 心房細動。読んで字のごとく、心房が細動している状態をいいます(図1)。 図1 心房細動 これは目に見えて、実際心

第46回 認知症の人を介護する家族の体験:葛藤からの自己変容
医療者が患者の治療・ケアを行ううえで、患者の考えを理解することは不可欠です。 そこで、患者の病いの語りをデータベースとして提供しているDIPEx-Japanのウェブサイトから、普段はなかなか耳にすることができない患者の気持ち・思い・考えを紹介しながら、よりよい看護のあり
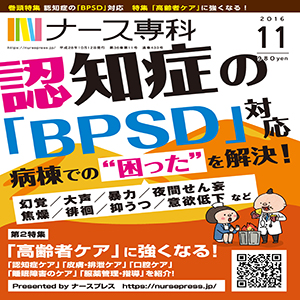
ナース専科2016年11月号『認知症の「BPSD」』対応
1冊まるごと高齢者ケア 巻頭特集のテーマは「BPSD」対応。認知機能が低下することで生じる、思いがけない症状や行動への対応の仕方を解説します。第2特集では、看護職のための専門情報サイト「ナースプレス」のなかから、「高齢者ケア」に役立つ記事をたっぷりご紹介しま

CASE05 難治性の褥瘡の治療法について模索する
困難事例5「順調に縮小傾向にあった褥瘡が一瞬で悪化してしまった」ケース イレウスで寝たきりの80歳男性。 半年前まではプリンやヨーグルトを1日半分程度は食べていたが、それさえ飲み込めなくなり、現在は完全に水分のみ摂取。 栄養は高カロリー輸液で補っている状態である
がん化学療法による口腔粘膜炎へのケアと注意のポイントは?
▼がん化学療法についてまとめて読むならコチラ がん化学療法とは?副作用の出現時期や症状別の看護 がん化学療法開始前の注意点 がん化学療法のレジメンが決まり、口腔粘膜炎が発症しやすい薬剤を用いる場合には、化学療法の開始前に口腔粘膜炎のリスク要因をでき


