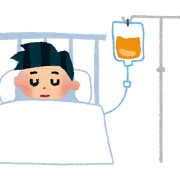排尿誘導の間隔はどうやって決める?
排尿誘導の間隔はどうやって決める?
- 公開日: 2016/4/11
- 更新日: 2021/1/6
ナース専科コミュニティ会員にアンケートを実施し、排便や排尿にかかわることで実際に困っていることを集め、皮膚・排泄ケア認定看護師に解説してもらいました。
排尿誘導の間隔はどうやって決める?
排尿パターンを把握して決める
排尿誘導は、膀胱・尿道機能に異常がなく、ADLや認知機能が低下し尿失禁を起こす場合に行います。排尿の自立が困難な患者さんに対して、失禁で汚染したままの状態を防ぐことを目的とするなら、2~4時間ごとの排尿誘導をします。尿失禁の改善を目指すならば個別の排尿パターンを把握し、パターンに沿って排尿誘導をすることが必要です。
尿意があいまいな患者さんについては、まずは排尿日誌をつけましょう。そして、どのくらいの間隔でトイレに行きたいと言っているのか、1回の尿量はどのくらいなのか、その際に失禁はあるのか、水分はどのくらい摂取しているのかなどをきちんと記録しておきます。この排尿日誌をつけることで患者さんの排尿パターンがわかるため、時間ごとがいいのか、あるいは朝・昼・晩でいいのかなど、間隔や回数を決めることができます。
頻回に尿意を訴えていても1回の排尿量が少ない患者さんについては、泌尿器疾患が原因で頻尿になっている場合もあるため、泌尿器に問題がないかどうかも見ていく必要があります。
また、尿意が全くない患者さんに対しては、当院では初めに2~3時間で排尿誘導をして排尿日誌をつけ、そのときに排尿量がどの程度あるかによって誘導時間を決めています。基本的に1回の排尿量は500cc以上溜まるようにはせず、500cc以上の排尿があった場合には2時間より早く誘導します。逆に100ccほどであれば、もう少し間隔をあけて誘導するといったように、排尿日誌を見ながら考えています。
【関連記事】
* 【尿失禁の看護】 尿失禁の種類・原因とアセスメント
(『ナース専科マガジン』2015年12月号より転載)