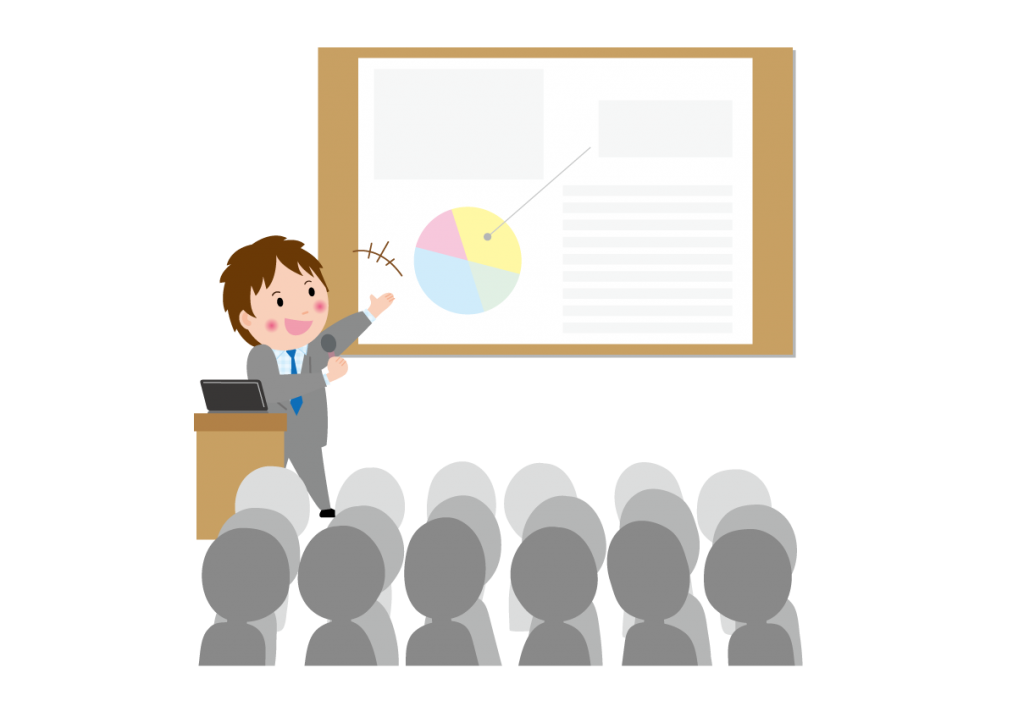摘便とは|適応・禁忌・手順・コツ〜根拠がわかる看護技術
摘便とは|適応・禁忌・手順・コツ〜根拠がわかる看護技術
- 公開日: 2018/2/17
【関連記事】
●グリセリン浣腸の目的と手順【マンガでわかる!看護技術】
●第8回 腹部膨満を訴える患者さんのアセスメント(排ガスの有無など)
摘便とは
摘便とは、自然排便ができない患者さん、麻痺があるなど何らかの理由で腹圧がかけられない患者さん、脊損や直腸機能障害のある患者さんに対して、便を用手的に排出するケアです。特に、肛門の手前で硬い便が蓋をしてしまって排泄ができないといった嵌入便のケースでよく実施されます。
摘便の適応・禁忌
便の貯留があり、自然排便ができない患者さんを対象として、直腸・肛門に出血や潰瘍がないなど、障害がみられない場合に行います。肛門周囲に病変がある、炎症性疾患、疼痛や出血がある患者さんには禁忌です。
ただし、痔核や直腸瘤などが原因で自然排便できず、肛門付近に便が嵌入し苦痛が強い場合は、ケアを優先し実施することもあります。禁忌がみられない場合でも実施の際には、必ず医師に確認します。
摘便ケアで注意したいこと
腹部のアセスメント
実施前には、必ず腹部を触診し、便が貯留しているかを確認します。左下腹部の斜め横方向を触診し、固く触れれば便が貯留していると推測できます(図)。

摘便は、患者さんの苦痛と羞恥心を伴うケアであり、また手技によっては直腸や肛門を損傷させてしまう危険性もあります。安易に行わないようにしましょう。
本来ならば、レントゲンで便の貯留や位置を確認してから行うのが望ましいケアですが、実際の臨床の場では難しいのが現状です。しかし、そのくらいの慎重さが必要だということを意識して、腸、肛門の解剖生理をよく理解したうえでケアに臨みましょう。
関連記事
* 腹部の観察、腹部の聴診法|消化器のフィジカルアセスメント(1)
* 腹部の触診、肝臓・腎臓の打診|消化器のフィジカルアセスメント(2)
無理にケアをしない
無理に便を取ろうとせず、愛護的なケアを心がけましょう。特に陥入便では、便が硬く無理に掻き出そうとすると、腸や肛門を損傷させてしまいかねません。硬い便は、指でつぶして柔らかくしていから排出するようにしましょう。
便が柔らかければ、直腸壁に刺激を与えるだけでも筋肉が緩み、自然と便が出てきます。これは、ふだん直腸の筋肉が緊張していることによって禁制が保たれているからです。摘便は、便を掻き出すケアではなく、「直腸の自然な動きを促す」「栓となって塞いでいる便を取る」という意識でケアを行うとよいでしょう。
ケアに時間をかけない
とかく便を排出することに集中してしまいがちですが、患者さんの苦痛や羞恥心に配慮し、できる限り短い時間でケアを終了するように心がけましょう。目安としては、準備から片づけまで約10分間以内で終わらせるようにします。
ケアのタイミング
食後しばらくして1時間以内、腸管が動くタイミングに合わせて摘便を実施すると効果的です。
便が触れないとき
摘便は、直腸に指を入れて便を排出させるケアです。指が届く範囲(肛門口から約4cm)まで、便が下りてきていないと排出することはできません。もし便が触れなければ、浣腸など別の処置を考慮しましょう。
また、浣腸したあとに滴便を行うケースもあります。その際に、直腸を損傷させてしまうと、グリセリンが入り込み、有害事象を引き起こすリスクがあります。よって、正しい手技で安全に滴便を行うことは非常に重要です。
摘便の手順
物品の準備
・潤滑剤は、お尻ふきにある程度の量を出しておきます。そうしておくと、滴便中に潤滑剤を付け直すときに容器を汚さずにすみ、またケアが効率的に行えます。
看護師の準備
1 実際に処置をする看護師とお腹に圧をかける介助をする看護師、二人で行うことが望ましいです。
2 感染対策のため、スタンダードプリコーションのもと、マスク、ビニールエプロン、手袋を着用します。
3 手袋は二重にすると、破損したときの汚染防止になるとともに、次の処置にすぐに移行することができます。
関連記事
* スタンダードプリコーション(標準予防策)の基本知識
患者さんの準備
1 周りの患者さんにも配慮して、カーテンでプライバシー空間を確保し、摘便を行うことを説明します。
ただし、摘便といっても患者さんはわからないので、具体的に説明します。また、便秘の苦しみをとるケアであることも伝えます。
声掛け例:「つまっている便を出すことによって、今のつらさがなくなるかもしれません。まずは、お尻に手を入れてみて便がつまっているかどうか確認しますね」
2 患者さんを左側臥位にし、膝を少し屈曲してもらいます。
どうして?:下行結腸以下のS状結腸や直腸は、左側臥位にて自然な解剖学的位置になり排便しやすくなります。
3 臀部を露出します。患者さんの臀部以外には、タオルをかけるなど、できる限り露出を少なくして、患者さんの羞恥心に配慮します。
4 おむつを臀部の下に敷きます。
5 尿器もしくは尿取りパッドを配置します。
どうして?:腹圧をかけるため、尿を排泄する可能性があるためです。予期せぬ排尿により、シーツなどの汚染を防ぐとともに、患者さんの羞恥心や罪悪感を軽減することにもつながります。