 環境整備とは|看護師が行う意義と目的、方法~根拠がわかる看護技術
環境整備とは|看護師が行う意義と目的、方法~根拠がわかる看護技術
- 公開日: 2018/4/5
【関連記事】
* 第10回【環境管理編】環境整備の実施回数は多いほどいい?
* 清拭の目的と看護師が行う意義、手順
* ベッドメイキング 見直そう! 5つのポイント
環境整備の意義・目的
病室は、患者さんの治療の場であるとともに生活の場です。患者さんが安全で安楽に過ごすことができるように環境を整えるのは、看護師としての責務です。
特に臥床状態にある患者さんでは、自分で環境を整えることができません。自分で動くことができる患者さんであっても、不快な環境はストレスの原因となります。また患者さん自身が環境を整えてしまうと、余計な体力を消耗させることにもなります。
看護師が個々の患者さんにとって適切な環境をアセスメントし維持することで、患者さんは余計な体力を消耗せずに、自身の力を疾患の治癒に注力することができます。患者さんが回復していくためにも、環境整備は重要なのです。
環境整備のキホン
環境整備における大切な要素
環境整備で大切な要素は、空気(清浄さ、室温、湿度)、明るさ、音、においです。これは、フローレンス・ナイチンゲールの『看護覚え書』で示されている看護の要素、「新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、静かさを適切に整えること」1)そのものです。
これらに加えて、患者さんに生活を感じさせるような配慮も必要です。回復過程において、患者さんは治療中心の生活から日常の生活へと戻っていくためです。
例えば、患者さんがみることができる位置にカレンダーや時計を置き、現在の時間や日付がわかるようにします。患者さんが日時をわかるようにすることは、せん妄予防においても重要です。
また、壁にホワイトボードが掛けられれば、日付とその日のスケジュール(リハビリや入浴の時間など)を書いておくのもよいでしょう。
さらに理想的なのは、“患者さんらしさ”を反映できるものを病室に置くことです。患者さんが趣味で作ったものや好きな写真や絵など、治療に差支えのない範囲で置くとよいでしょう。
患者さんの感覚に合わせる
環境整備を実施するときの基本は、“患者さんの身になって考えること”です。温度にしても、ベッドで寝ている患者さんと始終動き回っている看護師では感じ方は異なります。しかも、患者さん個々によって、その感覚はさまざまです。
1日の時間による変化を考慮する
看護師が訪室する時間帯だけではなく、患者さんが24時間にわたり、快適に過ごせるように適宜、環境を調整する必要があります。
例えば、季節や時間帯、部屋の位置によって、窓からの彩光の状態は変化します。患者さんが眩しさなどを感じることがないように、時間帯によってカーテンで調整する必要があるでしょう。
患者さんの経時的な変化を考慮する
日々、患者さんの状態は変化していきます。臥床状態から歩行が可能になった場合は、ベッド柵の位置を変更するなど、患者さんのADLに合わせて、環境を調整していくことが大切です。
また、不要になった物品を病室にそのまま置いておくのではなく、片づけることも重要です。
整理整頓の重要性
病室は治療の場です。特に急変時、すぐに治療態勢がとれるように、整理整頓されている必要があります。
環境整備とともに安全も確認する
環境を整えるとともに、患者さんの安全が保たれるように配慮しましょう。一番重要なのは、ナースコールの位置です。患者さんの手元になければ命にかかわります。
また転倒や転落のリスクを考え、ベッド柵や履物の位置は適切か、動線上に余計な障害物はないか、床が濡れていないかなどを確認しましょう。
患者さんに害を与える可能性はないか、患者さんの行動をイメージするとともに先を読む力が必要となります。
環境整備の実施
環境整備のアセスメントのポイント
この記事を読んでいる人におすすめ
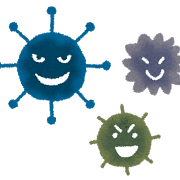
第9回【環境管理編】環境整備のとき、消毒薬使用は必須?
多剤耐性菌や感染性胃腸炎などに罹患している患者さんとそうでない患者さんの病室の環境整備を行う際、どのような区別をしていますか?消毒薬を使い分けたりする必要があるのかどうか迷ったことはありませんか? 今回は、そんな病室の環境整備を行う際の消毒薬の使い分けについて解説してい
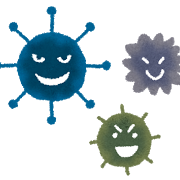
第10回【環境管理編】環境整備の実施回数は多いほどいい?
ベッド柵や床頭台などの清拭などは1日に何回していますか? こういった環境整備の実施回数が感染対策にどの程度効果があるのかを知って、過不足なく実施できるようになりましょう。 Q. 環境整備を頻回にすることは感染対策上有効な方法ですか? ※A. NO

ベッドメイキング 見直そう! 5つのポイント
基本的な看護技術であり、日常的な看護業務でもあるベッドメイキング。でも、あなたがつくるベッドは患者さんにとって本当に心地よいものでしょうか。いま一度、ベッドメイキングの重要性を見直してみませんか。 【関連記事】 【図解】ベッドメイキングの手順とコツ~根拠がわかる

【図解】ベッドメイキングの手順とコツ~根拠がわかる看護技術
ベッドメイキングには、新しくベッドをつくる方法と患者さんが寝ている状態でベッドをつくる(シーツ交換)方法があります。ここでは基本形として、新しくベッドをつくるための手順を紹介していきます。 (2017年5月24日更新) ベッドメイキングを行う前に知っておき




