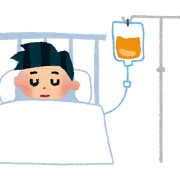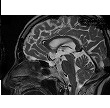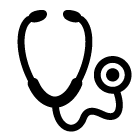7.看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則の活用方法~トレーニングの実際~
7.看護に関するQOL向上のWIN-WINの法則の活用方法~トレーニングの実際~
- 公開日: 2019/9/25
WIN-WINの法則を臨床現場に活用するトレーニングの実際とは?
前回の「6.看護師の言語表現のあり方を見直そう」では、看護師の言語表現は、必要とされる頻度の高さにより、「語る力」のスキルに違いが出るという特徴があることについてお伝えしました。
また、看護師の言語表現のあり方は、病棟文化や教育体制も影響する「看護の力」の表れであり、職場全体の「語る力」の能力を高めることは患者さんによりよい看護を提供することにつながり、看護のQOL向上に大きく影響するため、「語る力」の見直しは重要なのだということについても述べました。
今回は、看護の臨床現場に、QOL向上のWIN-WINの法則の内容を具体的にどのように活用するのかという提案の第一弾として、トレーニングの実際についてお伝えしたいと思います。
QOL向上のWIN-WINの法則を活用した看護教育風土づくりと組織運営
第1部での、WIN-WINの法則の内容を具体的にどのように活用するとよいのか、その第一弾目としては、看護教育風土づくりと組織運営に取り入れるトレーニングがよいと思います。
連載第2回目の「2.看護業務内容と職場風土」では、“参加型の職場風土でケアする看護師たちが業務を改善し、「看護を考え抜く力」を使って対象のQOL向上を短時間で実践化することが、看護師のQOL向上にもつながるのではないか”という視点を、組織的に取り入れて運営をすることが大切だということをお伝えしましたが、この看護教育風土とは、職場風土のうえに成り立っており、大きく影響を受けると思われます。
そこで、看護教育について、現状として臨床現場で行われている日々の看護教育をオン-ザ-ジョブ-トレーニングとし、特別に非日常で研修を受けることをオフ-ザ-ジョブ-トレーニングとして、分けて考えていきます。
オン-ザ-ジョブ-トレーニング方法として、病棟教育委員や院内教育委員が行う研修による教育や、プリセプターシステムなどを導入した看護師個人の実践能力開発を目的とした、直接的なアプローチが行われることが多いと思われます。
しかし、これには「よい選手が、よい監督になれるのか」に似た「よい看護をする看護師が、よい看護師の教育ができるのか」という、看護の経験のみで教育できる限界が潜んでいます。
この限界の回避策として、オフ-ザ-ジョブ-トレーニングに励む看護師が多く、これは自己教育力によるものともいえます。
ところが、現場の看護師の集団特性(集団レディネス)や個人の看護師の実践能力を的確に判断して教育するスキルは人材育成の要素が多く、今までの看護経験とは異なる内容であり、オフ-ザ-ジョブ-トレーニングでも容易に身につくスキルではないため、臨床教育が充実されない状況が看護のQOLに影響する可能性も否めないと考えます。
看護教育を任されているであろう、中堅看護師の感じる役割ストレスや業務負担感が、離職と関係していることも示されています1)。
このため、個人の看護師に役割として任せる以外にも、看護教育風土づくりを組織的に取り組み、参加型の職場風土で「看護を考え抜く力」の向上を促し、集団の相互作用効果で看護実践能力が自然と研鑽できるような状況づくりが必要であると考えます。
参加型の職場風土づくりのためのオフ-ザ-ジョブ-トレーニング
「看護を考え抜く力」の向上を促す参加型の職場風土づくりは、カンファレンスなどを意図的にスーパーバイズして運営すると効果的だと思います。
このスーパーバイズは、大抵が慣習的に中堅看護師や看護教育の担当者が実施する場合が多いのですが、役割が曖昧なままであるとストレスを感じるため、役割として誰が実施するのかを明確にしておきましょう。
役割担当者は、その時期に病棟で一番考えたほうがよい看護内容や事例をテーマとして選定する能力、多様な意見を出しやすくするための雰囲気づくり、意見の言語化不足に気づかせるような助言を何気なく伝える能力など、「看護を考え抜く力」を導くうえで自己の不足な能力に焦点化してオフ-ザ-ジョブ-トレーニングを受ければよいでしょう。

研修運営の実際と日々の「看護を考え抜く力」の重要性
このように、医療従事者における教育は専門領域に関する経験に頼らざるをえません。しかし、教育的な役割担当者になったとしても、認識論・行動科学・教育心理学などを専門的に学び、教育スキルとして身につけているわけではないため、いまだオフ-ザ-ジョブ-トレーニングに頼るしかない状況にあります。
そのため前に述べたように、看護教育の役割担当者は、あたりまえのようにオフ-ザ-ジョブ-トレーニングを受け、看護教育においての研修をしています。
しかしこれには、医療や看護でない新しい分野の学習が必要です。しかも対象者の学習レディネスは経験的知識や価値観もさまざまであるため、個々のレディネスを引き出してそれに沿った学習環境をつくることは、非常に困難なことといえます。
役割担当者に頼った現在の看護教育を変えるために、各病院では、自分たちの病院の学習レディネスの特徴に沿った既存の方法を探すか、または独自の方法を探し出してオフ-ザ-ジョブ-トレーニングの研修を運営していますが、テーマをもって継続的に研修を行い、その後の学習成果分析と看護実践力比較を適切に実施し、「病院内教育の構築」まで達成することは難しいようです。
また、たとえ達成に至ったとしても、構築までには大変時間を要するため、構築したプログラムを使用したいときには人材が入れ替わっていて学ぶ側のレディネスの相違があったり、時代の変化で新たな教育が必要になったりするなど、プログラム自体がうまく機能しないことが多く、それに沿った研修も効果的であるのか疑問だと漏らしていた指導者がいたことを思い出します。
参加型の職場風土で「看護を考え抜く力」の向上を促し、集団の相互作用の効果で看護実践能力を上げていくことは、このような大がかりな病院内教育構築の縦軸として、日々のオン-ザ-ジョブ-トレーニングとして研鑽することが重要でしたが、横軸である病院内教育の構築が難しい現状である今、さらに重要なオン-ザ-ジョブ-トレーニングであるといえます。
引用文献
1)瀬川有紀子:中堅看護師の離職意図の要因分析 役割ストレスと役割業務負担感の関連から.大阪市立大学看護学雑誌 2013;6:11-8.