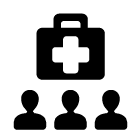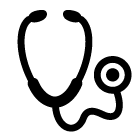第2回 口腔トラブルが起こるメカニズムとケアのエビデンス
第2回 口腔トラブルが起こるメカニズムとケアのエビデンス
- 公開日: 2013/2/28
協賛:サンスター株式会社/主催:ナース専科
がん化学療法に伴い、高い頻度で発生する副作用である口腔粘膜炎や知覚過敏。これら口腔トラブルへのケアを学ぶ「明日から実践! がん化学療法時の口腔ケア」セミナーのレポート第2回目は、静岡県立静岡がんセンターの大田洋二郎先生がレクチャーする、口腔トラブルが起こるメカニズムとケアのエビデンスをレポートします。
第1回はこちら
* 第1回 がん化学療法時の口腔ケア
口腔トラブルのメカニズムとケア介入のエビデンス
まず、正常な細胞であっても、骨髄、毛母細胞、消化管粘膜などの代謝が盛んな細胞組織に、がん化学療法時の副作用が現れやすいこと、抗がん剤の種類や治療計画によって副作用の発現する部位や時期が異なることなど、化学療法と副作用の基礎知識についての説明がありました。
丁寧な観察と、病態に合ったケアの提案が大切
静岡がんセンターの大田洋二郎先生からは、「がん支持療法としての口腔有害事象への対処とその考え方」と題し、(1)口腔有害事象を発症する仕組みと口腔ケアの重要性、(2)口腔ケア介入のエビデンスと介入の考え方、(3)国際多職種がん支持療法学会(MASCC)の口腔有害事象のガイドラインという3点について講義がありました。
最初に、がん化学療法時の口腔トラブルの特徴として、口腔には無数の細菌が恒常的に存在し、粘膜バリアの破綻が敗血症に拡大する危険性があることなどに触れ、がん化学療法を受ける患者さんの40%に発生する口腔トラブルのうち、半分は口腔粘膜炎が問題となって治療が中断したり、投与量の変更が行われていると説明。包括的な口腔ケアの重要性を指摘しました。

口腔粘膜炎の発症部位がほぼ決まっていることを解説する大田先生