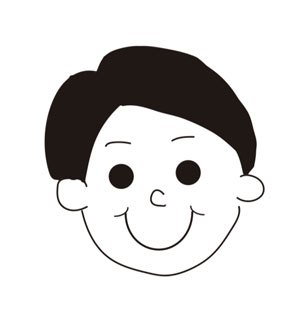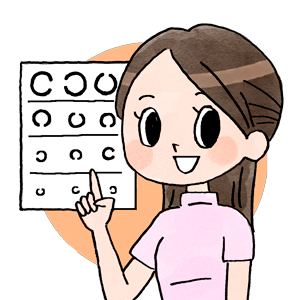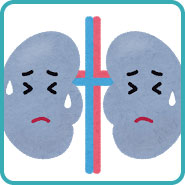黄斑疾患治療に新たな選択肢! 投与間隔延長で患者負担軽減へ
黄斑疾患治療に新たな選択肢! 投与間隔延長で患者負担軽減へ
- 公開日: 2025/5/26
ものが見える仕組み
人間は、情報のほとんどを視覚によって獲得しています。眼から入った光は角膜を通って水晶体で屈折し、硝子体を通って網膜で像を結びます。そして、網膜で得た情報が視神経を介して脳に伝達され、ものが見えるようになります。この道筋のどの部分が障害されても、ものが見えにくくなります。
加齢黄斑変性とは
網膜は眼の全体に分布しています。網膜のどの部分に光が当たっても、光があること、ものがあることを認識できますが、文字を読んだり、あるいは形をはっきりと見るのには、網膜の中心にある黄斑が重要な役割を担っています。
加齢に伴い黄斑に障害が生じ、視力低下を引き起こすのが加齢黄斑変性です。滲出型(新生血管型)加齢黄斑変性と萎縮型加齢黄斑変性に分けられ、日本では滲出型加齢黄斑変性がほとんどを占めます。
滲出型加齢黄斑変性は脈絡膜から新生血管が発生し、そこから出血や血液成分の漏出が起こって正常な構造が破壊され、萎縮型加齢黄斑変性は網膜色素上皮が徐々に萎縮して網膜が障害され、視力が低下します。いずれも、視界の中心部がゆがんではっきり見えない、あるいはその部分が全く見えないという症状がみられます。
かつては加齢黄斑変性に対する有効な治療法はなく、1年後にはほとんどの患者さんが失明に至っていました。発症頻度が高いにもかかわらず、治療法がないという極めて厳しい疾患だったのです。
糖尿病黄斑浮腫とは
糖尿病は、国民病といわれて久しい疾患です。以前は、糖尿病患者さんの平均余命は短かったため、長期的な予後を考えることはありませんでしたが、健康な人と同じように生活できる患者さんが増えた結果、より長く、視力を守らなければならないという新たな課題が出てきました。
糖尿病の初期は症状が乏しいために無治療の患者さんも少なくありませんが、そのまま放置していると糖尿病網膜症の発症につながります。限られた部分が障害される加齢黄斑変性に対し、糖尿病網膜症では網膜の全ての部分から出血や血液成分の漏出などが起こり、単純網膜症、増殖前網膜症、増殖網膜症と段階を追って進行していきます。
この糖尿病網膜症に合併して起こるのが糖尿病黄斑浮腫です。糖尿病網膜症の病期にかかわらず発症するもので、単純網膜症や増殖前網膜症の段階で糖尿病黄斑浮腫が出現し、社会的失明に至ることもあります。
加齢黄斑変性では視界の中心部が見えにくくなりますが、糖尿病黄斑浮腫では全体がかすんで見える、あるいはかすみは少ないものの、ゆがんで見えると訴える患者さんが多い傾向にあります。
黄斑疾患がもたらす問題
加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫といった黄斑疾患により視覚障害を抱えると、さまざまな問題が生じます。まず、予期しない転倒や転倒に伴う骨折などの危険性が高まり、医療費や死亡リスクが上がります。また、視覚障害は精神状態にも影響を及ぼし、不安やうつが非常に強く出る患者さんもいます。仕事を休んで病院に付き添うなど、家族のケアも不可欠になるため、視覚障害は患者さん本人だけでなく、家族にとっても大きな問題となります。
黄斑疾患の治療目標と患者さんのニーズ・実態
黄斑疾患の治療について、バイエル薬品と参天製薬のみなさんと話し合うなかで、「Sustainable Disease Control(SDC)」という考え方が生まれました。具体的にいうと、「疾患活動性を示す血管新生や血管透過性亢進などの病態を持続してコントロールし、長期的に視力低下を防ぐことが重要であり、SDCとはその治療達成をめざした治療目標」であり、言い換えれば、黄斑疾患とうまく付き合うということです。
アメリカで、加齢黄斑変性と糖尿病黄斑浮腫の患者さんを対象に行われた調査があります。治療に関連する5つの属性(視力の変化、治療費、治療薬剤の適応、治療頻度、保険会社が支払う治療費)のうち、患者さんにとって最も重要な属性は何かを調査したもので、結果として、視力の変化が最も重要な属性であると示されました1)。つまり、良好な視力を維持することが、黄斑疾患患者さんにとって最も高いニーズになっているということがいえます。
日本においても、黄斑疾患患者さんを対象に、日常生活でどのようなことに困っているか調査したものがあり、「移動」「ものの見分け方」「アクティビティ」「相手の顔や表情」「デジタル機器の利用」「眼と動作の連動」「気分や気持ち」の7つの項目について、視力が低下するほど、それぞれの負担も増えるというデータが出ています2)。個人的に興味深かったのは、若い人だけでなく高齢者も、視力低下によるデジタル機器の利用に不安を感じていると明らかになったことです2)。
黄斑疾患の治療方法
滲出型加齢黄斑変性については、抗VEGF薬治療(硝子体内注射)が第一選択です。糖尿病黄斑浮腫の標準治療でもあります。
VEGFは血管新生を促進するタンパク質で、傷口を治すメリットがある一方、不要な血管を生じさせて、そこから出血させるという負の側面をもちます。黄斑疾患では負の側面が強く出るため、この因子を弱めることで治療をするというのが抗VEGF薬治療の原理です。
ただ、症例によっては、光線力学的療法を行うこともあります。滲出型加齢黄斑変性のなかでも、ポリープ状脈絡膜新生血管や網膜血管腫状増殖など異なる病因のものがあるため、疾患タイプ、治療への反応、患者さんや家族の希望などを加味しながら、治療法や薬剤を使い分けています。
新たな治療薬「アイリーアⓇ8mg」
抗VEGF治療の良好な点を維持しながら、薬剤の投与間隔を延長し、患者さんや医療従事者の負担を軽減することを目的に開発されたのが「アイリーアⓇ8mg」です。既承認のアイリーアⓇ2mgより高濃度のアフリベルセプトを含み、より高容量で硝子体内投与を行う製剤です。
滲出型加齢黄斑症の患者さんを対象に、アイリーアⓇ8mgの有効性に関する臨床試験が行われました。アイリーアⓇ2mg8週間隔投与群、アイリーアⓇ8mg12週間隔投与群、アイリーアⓇ8mg16週間隔投与群に割り付けて、それぞれの投与回数の平均値を調べたところ、48週目では2mg8週間隔投与群で6.7回、8mg12週間隔投与群で5.9回、8mg16週間隔投与群で5.1回でした。96週目では、2mg8週間隔投与群で11.9回、8mg12週間隔投与群で9.2回、8mg16週間隔投与群で7.8回となり、これまで最も使われてきたアイリーアⓇ2mgと比較し、アイリーアⓇ8mgでは明らかに少ない注射回数で、疾患の活動性をコントロールすることが期待できる結果となりました3)。
また、糖尿病黄斑浮腫でも同様の試験が行われており、48週目では2mg8週間隔投与群で7.7回、8mg12週間隔投与群で5.7回、8mg16週間隔投与群で4.9回、96週目では2mg8週間隔投与群で12.9回、8mg12週間隔投与群で8.6回、8mg16週間隔投与群で7.5回でした。糖尿病黄斑浮腫においても、アイリーアⓇ2mgと比べ、アイリーアⓇ8mgでは少ない注射回数で疾患のコントロールが可能であることが示されました4)。
医学の進歩により、眼科疾患の多くが治療可能になりつつありますが、多くの患者さんがその恩恵を受けるには医療や社会の工夫が必要です。新しい治療や試みにより患者さんや医療従事者の負担を減らすことは、疾患とうまく付き合うSDCという考え方においても重要であると考えています。
引用文献
2)Ozawa Y,et al:Recent daily life burdens associated with neovascular age-related macular degeneration involve difficulties in use of electronic devices.Scientific Reports 2024;14:14181.
3)バイエル薬品社内資料[日本人を含む第Ⅲ相国際共同試験:PULSAR試験]承認時評価資料.電子添文改訂時評価資料(96週).(2025年5月15日閲覧) https://www.eylea.jp/ja/product_8mg/safety/namd/reduced-burden
4)バイエル薬品社内資料[日本人を含む第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験:PHOTON試験]承認時評価資料.電子添文改訂時評価資料(96週).