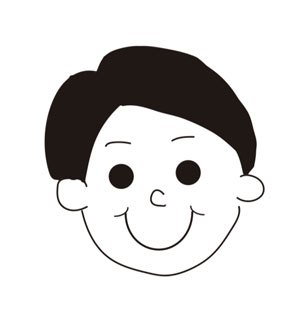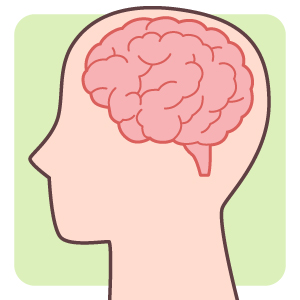新薬で広がる! アトピー性皮膚炎の治療選択肢
新薬で広がる! アトピー性皮膚炎の治療選択肢
- 公開日: 2025/5/1
アトピー性皮膚炎患者さんのアンメットニーズについて
中原剛士先生(九州大学大学院医学研究院 皮膚科学分野 教授)
アトピー性皮膚炎とは
アトピー性皮膚炎は、『増悪・寛解を繰り返す、掻痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くは「アトピー素因*」を持つ』と定義されています1)。
非常に頻度の高い皮膚疾患で、「皮膚のバリア異常」「皮膚の炎症」「痒み・掻破」の3つの要素が相互に作用しながら、アトピー性皮膚炎の病態ができあがってくると考えられています。
*①家族歴・既往歴(気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは複数の疾患)があること、または②IgE抗体を産生しやすい素因1)
アトピー性皮膚炎の症状
アトピー性皮膚炎の症状の特徴は、強い痒みです。繰り返し痒みが出現することで、夜も眠れないという患者さんもいます。症状の発症・経過には個人差がありますが、ほとんどの患者さんは、5歳くらいまでに症状が現れます。
年齢別の皮膚症状の特徴ですが、まず乳児期では、口のまわりや頬にただれが出て、首や手足のしわの部分に赤みや痒みが目立つようになります。もう少し大きくなって、幼児あるいは小学生くらいになると、全体的に皮膚の乾燥が強くなり、肘や膝のくぼみの部分に発疹がみられるようになるほか、耳の付け根の部分が切れてしまう「耳切れ」が生じることもあります。思春期または成人以降では、下半身よりも上半身でよく発疹がみられようになり、顔や首、前胸部、上背部に強く出る傾向があります。
アトピー性皮膚炎の経過
アトピー性皮膚炎は、乳幼児期に発症して短期間で改善するか、遅くとも小学生くらいには改善することがほとんどでした。しかし最近では、ゆっくりと治癒が進み、なかなか治らない場合があります。また、一旦は治癒しても受験や就職などをきっかけに再発するケースや、思春期や成人になって初めて発症するケースが徐々に増えてきています。
アトピー性皮膚炎の治療
痒みと掻破行動により皮膚炎は悪化し、皮膚炎の悪化はさらなる痒みを生じさせます。そのままにすると重症化して治るものも治らなくなり、生活への影響も大きくなるため、適切な治療でこの悪循環を断ち切ることが重要です。
『アレルギー性皮膚炎診療ガイドライン 2018』では、アトピー性皮膚炎の治療目標(ゴール)ついて、「症状がないか、あっても軽微で、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、それを維持する。また、このレベルに到達しない場合でも、症状が軽微ないし軽度で、日常生活に支障をきたすような急な悪化が起こらない状態を維持する」としています2)。
アトピー性皮膚炎の治療ですが、炎症が強く、痒みも出ている患者さんがいた場合、まずは炎症や痒みがほとんどない状態までもっていく寛解導入を行います。寛解導入により改善がみられれば、できるだけ薬を減らしながら寛解を維持し、スキンケアをする程度でいいような状態までもっていくという流れになります。
ただ、これまでの治療では、どうしても症状をコントロールできない重症の患者さん、副作用が出てしまうため薬が使えない患者さん、忙しさなどを理由に薬を十分に塗ることができていない患者さんがいました。こういった患者さんは治療目標を達成できず、悪化を繰り返してしまっていましたが、近年はアトピー性皮膚炎の病態の理解が進み、細胞間で行われる情報伝達を抑制して、炎症や痒み、皮膚のバリア異常を抑える治療薬が出てきています。特に、2018年にデュピルマブという注射薬が出たことを皮切りに、外用薬や内服薬などさまざまな治療薬が登場し、多くの患者さんが治療目標を達成できるようになってきました。
十分とはいえない治療満足度
2024年1月に、アトピー性皮膚炎患者さんと一般生活者(アトピー性皮膚炎に罹患していない人)を対象とした意識調査を行いました。直近3カ月でアトピー性皮膚炎の治療のために通院した人をアトピー性皮膚炎患者さんとし、新薬を使用している人と使用していない人に分けています。
患者さんの困りごと・悩みごととして、「外用薬を塗るのに時間がかかる」「保湿に時間がかかる」「外用薬がベタベタする」が上位となりました。また、一般生活者と大きく差が出た項目に、「人目が気になる」「日用品の素材に気を遣う」「おしゃれができない」などがあり、一般生活者が何気なくできていることが、アトピー性皮膚炎の患者さんの多くで困っていて、あきらめざるを得ない状況にあるということは、着目すべきポイントであると考えています。
治療満足度についても聞いてみたところ、「非常に満足している」「やや満足している」を合わせて全体で44%と半分に届かず、これは医師としてはショックな結果でした。中でも、医師に困りごとを伝えられている患者さんとあまり伝えられていない患者さんでは満足度に差がみられ、医師としっかりコミュニケーションを取ることが満足度を上げているといえると思います。加えて、新薬を使用している患者さんのほうが、医師とのコミュニケーションに対する満足度が高く、医師と十分コミュニケーションを取ることで新薬を含めた治療の選択肢が得られているということがいえるかもしれません。
アトピー性皮膚炎による困りごとは多く、人生の大事なイベントや楽しみをあきらめてしまう患者さんもいます。困りごとについて医師に伝え、積極的にコミュニケーションを取れるような状況を作り、それぞれの患者さんとって最適な治療選択につなげていくことが必要であると考えています。
アトピー性皮膚炎治療の新たな選択肢イブグリースⓇについて
板倉仁枝さん(日本イーライリリー株式会社研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部)
レブリキズマブとは
レブリキズマブ(イブグリースⓇ)は、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対する新しい治療薬です。IL-13に結合するIgG4モノクローナル抗体であり、IL-13受容体複合体(IL-13Rα1/IL-4Rαヘテロ二量体)の形成とその後のシグナル伝達を阻害します。
レブリキズマブの用法・用量
レブリキズマブは通常、成人及び12歳以上かつ体重が40kg以上の小児には、初回と2週後(2回目)に1回500mgを投与し、3回目以降、つまり4週以降は1回250mgを2週間隔で投与します。なお、患者さんの状態に応じて、4週以降は1回250mgを4週間隔で投与することも可能なため、レブリキズマブを用いることで 、2週間隔投与での投与に加え、4週間隔投与が新たな治療選択肢になります。
治療負担軽減
レブリキズマブの臨床開発プログラムとして実施された主な第Ⅲ相試験は6つあり、日本単独ではADhere Jという試験が行われています。
ADhere Jでは、導入期・維持期において、レブリキズマブ2週間隔投与+局所コルチコステロイド(TCS)投与群(レブリキズマブQ2W+TCS群)、レブリキズマブ4週間隔投与+TCS投与群(レブリキズマQ4W+TCS群)、プラセボ+TCS投与群(プラセボ+TCS群)で効果の比較が行われました。その結果、投与16週時のベースラインからのDLQIスコア*4ポイント以上改善達成率は、レブリキズマブQ2W+TCS群では68.8%(66/96例)、レブリキズマブQ4W+TCS群では53.3%(32/60例)であり、いずれもプラセボ+TCS群における20.6%(13/63例)に比べて有意に改善していることがわかりました3)。
また、投与16~68週時のDLQIスコア4ポイント以上改善維持割合は、レブリキズマブQ2W/Q2W+TCS群で77.8%(14/18例)、レブリキズマブQ2W/Q4W+TCS群で83.3%(15/18例)、レブリキズマブQ4W/Q4W+TCS群で72.2%(13/18例)となり3)、効果が維持されているといえます。
導入期からの効果と長期に持続する効果を通して、アトピー性皮膚炎の症状のみならず、治療負担の軽減に貢献できればと考えています。
*皮膚症状がQOLに及ぼす影響をスコア化して評価する指標。10の質問で構成され、30点満点で評価する。点数が高いほど、QOLが低下していることを示す
引用文献
1)日本皮膚科学会,他:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018.日本皮膚科学会誌 2018;128(12):2432.2)日本皮膚科学会,他:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018.日本皮膚科学会誌 2018;128(12):2454.
3)N Katoh,et al:Efficacy and safety of lebrikizumab combined with topical corticosteroids in Japanese patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a phase 3, double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial (ADhere-J).Current Medical Research and Opinion 2025;41(1):1-12.