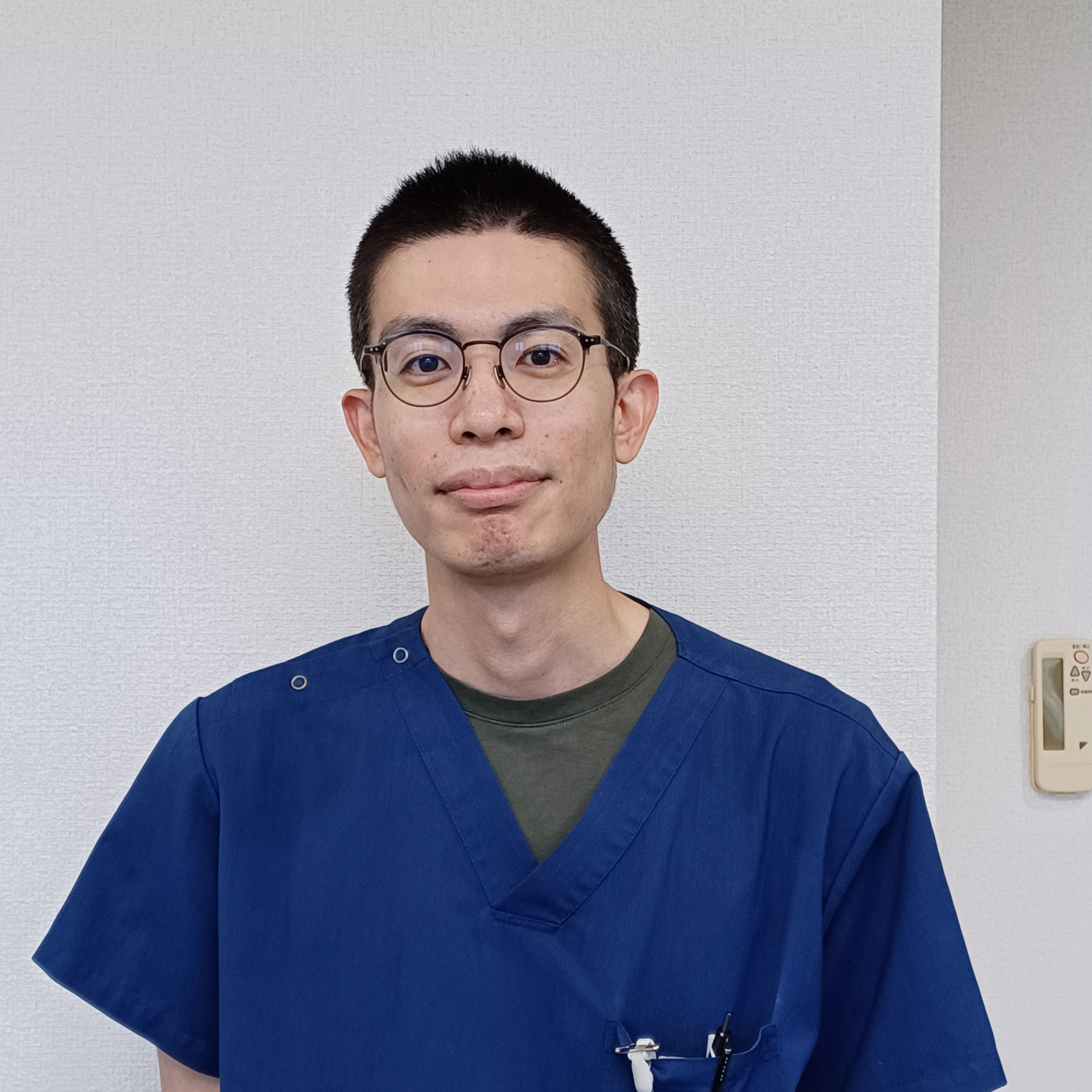【連載】てんかんケア完全ガイド|基礎から応用知識を現場で活かす!
 小児てんかんの看護│原因、発作の特徴、発達との関係、支援のポイント
小児てんかんの看護│原因、発作の特徴、発達との関係、支援のポイント
- 公開日: 2025/10/2
小児のてんかんとは
てんかんとは、大脳の神経細胞が一時的に過剰に興奮し、てんかん発作という症状を繰り返す慢性的な脳の疾患です。てんかんは全年齢でみられますが、特に小児期と高齢期に多く、小児期の発症は3歳以下に多いとされています。
小児てんかんは、通常、出生から18歳未満に発症するてんかんを指します。脳の成長・発達が起こるのは、この小児期に特有の現象であり、このタイミングでてんかんを発病すると、てんかんと脳の発達の間でさまざまな相互作用が生じます。
成長とともにてんかんが治ることもあれば、てんかんの発病により脳の発達に影響が生じることもあります。また、小児てんかんの原因は、成人発症のてんかんとは異なり、先天的な異常や周産期の問題に起因することが多くなります。
このように、生物学的な側面だけをとっても、小児てんかんは特別な知識が必要な分野です。年齢によって多様な病型や発作型がみられ、神経発達症との関連もあります。
小児てんかんの病因
小児期に発症するてんかんには、生まれつきの体質や遺伝的な素因が関与していると考えられる「素因性てんかん」が多くみられます。ただし、生まれつき何らかの脳の原因病態が推測されても、具体的な原因までは特定できないものも少なくありません。
例えば、遺伝子異常といっても、単一遺伝子変異ではなく、複数の遺伝子がさまざまな程度で発病に関与していることが推測される場合などが挙げられます。また、体細胞モザイクという、身体の中で脳だけに遺伝子変異が起こっている場合、一般的に行われる血液を用いた遺伝子検査では、脳の遺伝子変異はみつけられません。
さらに、周産期の低酸素性虚血性脳症(仮死、臍帯巻絡など)、感染性脳炎・インフルエンザ脳症、自己免疫性脳炎などが原因となることもあります。一方で、高齢者にみられるような脳卒中や神経変性疾患(小児期に発症するものは除く)などによるものは少ないといえます。
小児に多いてんかんの病型・症候群
成人後に発病するてんかんは、主に焦点てんかんであるのに対して、小児期には、焦点てんかんと全般てんかんのどちらも発症する可能性があります。例えば、焦点てんかんが59%、全般てんかんが29%1)を占めるという報告もあります。
また、以下のようにてんかん症候群と診断できるケースが多いのも小児てんかんの特徴です。
表1 小児期によくみられるてんかん症候群の例
| 症候群名 | 発症時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 小児欠神てんかん*1 | 通常4−10歳 | 短時間の意識消失発作(欠神発作)が毎日みられる 女児に多い |
| 若年欠神てんかん*1 | 通常9−13歳 | 欠神発作がみられるが(必須)、発作頻度は日単位よりも少ない 欠神発作のときの意識障害の程度が不完全なことがある 全般強直間代発作は9割にみられる |
| 若年ミオクロニーてんかん*1 | 通常10−24歳 | 覚醒後1時間以内に後発するミオクロニー発作(必須)と全般強直間代発作(9割以上)を認める |
| 中心側頭部棘波を示す自然終息性てんかん(中心側頭部棘波を示す小児てんかん、良性ローランドてんかん)*2 | 通常4−10歳 | 睡眠中に好発し、喉や舌、口から顔面下部の筋のピクつきや強直などの焦点発作を呈する 焦点起始両側強直間代発作になることもある |
| 乳児てんかん性スパズム症候群(West症候群を含む)*3 | 1−24カ月 (3−12カ月にピーク) |
てんかん性スパズムという発作(必須)、発達の遅滞・退行、特徴的な脳波異常(ヒプスアリスミア)のうち2つ以上みられるものをWest症候群という 脳波で典型的なヒプスアリスミアがみられないとき、乳児てんかん性スパズム症候群の用語が好まれることもあった |
*²日本てんかん学会分類・用語委員会,編:小児期に発症するてんかん症候群の国際抗てんかん連盟(International League Against Epilepsy)の分類と定義:ILAE 疾病分類・定義作業部会の公式声明.「てんかん研究」 2024;41(3):616-65.をもとに作成
*³日本てんかん学会分類・用語委員会,編:新生児・乳児期に発症するてんかん症候群の国際抗てんかん連盟の分類と定義:ILAE 疾病分類・定義作業部会の公式声明.「てんかん研究」 2024;41(3):561-615.をもとに作成
このように、小児期から若年成人にかけて発症するてんかんは、それぞれ特定の年齢に発症しやすいという特徴があり、これを「年齢依存性」といいます。
年齢依存性と発達との関係
小児てんかんは、脳の発達と密接に関連しており、成長とともに症状の現れ方が変化することがあります。例えば、年齢が上がるとともに薬剤の服用を中止しても発作が再発しないまま、寛解するケースもあります。中心側頭部棘波を示す自然終息性てんかんなどは、「自然終息性焦点てんかん」に分類され、成長とともに症状が消失する代表的な疾患とされています。
一方で、新生児期から幼児期に発症し、薬剤抵抗性を示す難治性の年齢依存性てんかん性脳症(乳児てんかん性スパズム症候群など)では、発作に加え、発作がないときの知能・運動機能の発達にも障害を併発し、成長とともに障害が明らかになるものもあります。
また、乳児期や小児期には脳の広範囲に異常な興奮がみられていたものが、成長とともに範囲が限定され、発作焦点部位が明確になっていくケースもあります。このように、小児のてんかんは年齢と発達の影響を大きく受けるのが特徴です。
神経発達症の併存とその影響
てんかんをもつ小児では、神経発達症を併存するケースがみられます。以下は小児てんかんによくみられる神経発達症とその併存割合を示したものです。
表2 小児てんかんにみられる神経発達症と併存割合
| 併存する神経発達症 | 併存割合 |
|---|---|
| 知的障害 | 40% |
| ADHD(注意欠如・多動症) | 33% |
| 自閉スペクトラム症(ASD) | 21% |
また、知的障害のある小児のうち、約22%はてんかんを併発しているとされており、知的障害の程度が重いほど、てんかんの有病率が高まる傾向も報告されています2)。
このような神経発達症の併存は、てんかんの経過や治療方針に影響を与えることがあります。例えば、てんかんと知的障害を併存していても、てんかんの治療によって発作がコントロールされることで、情緒が落ち着いたり、言葉が出るようになったり、通学できるようになったりする子どもがいます。
一方で、発作は落ち着いても、知的障害の症状は改善せず残るケースもあり、その経過はさまざまです。なかには、てんかん発作よりも併存症のほうが生活の質に大きな影響を与えていることもあり、包括的なケアが欠かせません。
小児てんかんの発作の特徴
小児てんかんでは、焦点発作と全般発作がみられる可能性があり、発作症状の見極めが重要です。特に、小児期は年齢(あるいは脳の発達の程度)が発作症状の現れ方に影響するため、成人とは異なる特徴があります。
例えば、全般強直間代発作は、ある程度成熟した脳でないと起こりにくく、厳密な評価を行うと新生児や乳児期ではまずみられません。一方で、小児は発作が脳全体に広がりやすく、意識障害を伴う発作になりやすい傾向があります。こうした背景から、焦点意識保持発作が少なかったり、焦点発作が全般発作にみえやすいこともあります。
また個人差はありますが、発作の頻度が1日に100回、あるいは一晩に10回以上など、成人や高齢者に比べて、非常に多いことがあるのも特徴です。
小児でみられる発作のタイプ
小児てんかんでは、年齢やてんかんの病型によって発作の現れ方が異なります。ここでは特に臨床でよくみられる発作のタイプを紹介します。
欠神発作
(定型)欠神発作は小児てんかんによくみられる発作のひとつで、短時間の意識消失がみられます。突然動作が止まり、ぼんやりと一点を見つめ、虚ろな表情・目つきになります。呼びかけにも反応しません。まぶたのピクつきや眼球の上転を伴うこともあります。
発作が軽い場合には、それまで行っていた動作をゆっくり続けたり(保続)、簡単な質問には返事をすることもあります(特に若年欠神てんかん)。
発作の持続は短時間(平均10秒、多くが4~20秒の範囲)で、すぐに通常の状態に戻るため、周囲が気づかず見過ごされることも少なくありません。特に緊張しているときよりも安静時に起こりやすく、欠神発作で代表的な小児欠神てんかんでは1日に何十回も生じることがあります。
また、過呼吸で容易に誘発される傾向があり、脳波室で風車を吹いてもらって脳波検査中に発作を捕捉することが診断に有効です。
ミオクロニー発作
ミオクロニー発作は、筋肉の電撃様・ショック様の突然の収縮(0.2秒未満)を特徴とする発作です。「ピクッとする発作」と表現します。典型的には、両側性・対称性・上肢優位とされますが、左右差がある場合もあります。
発作中の意識は通常は保たれますが、ときに発作の自覚がありません。足に出ると転倒することがあります。患者さんや家族がこの症状をてんかん発作として認識していない場合があるので、医療者が積極的に聞き出すことが重要です。
なお、学校の授業中に居眠りをしてビクッと動くのは、生理的なミオクローヌスであり、てんかん発作ではありません。
全般強直間代発作
前触れなく突然意識を失い、典型的には両側対称性の強直相(筋肉の持続性の収縮)と引き続く間代相(筋肉が一定のリズムで短時間収縮する)が起こる発作です。
表情は開眼し、しばしば開口します。強直の初期には、叫び声や泣き声のような発声がみられることもあります。強直相(10~20秒以上)では、両上肢外転挙上、股関節屈曲といった「屈曲期」に続いて、四肢伸展の「伸展期」へと移行します。その後、この姿勢を維持しながら、小刻みに震える時期(vibratory tonic)を経て、両側性の間代相に移行します。
間代のリズムは、最初は速く徐々に遅くなってきます。頻脈や顔色の変化(チアノーゼ)、唾液分泌増加、口から泡を吹くなどの自律神経徴候も伴います。また、発作直後に括約筋が弛緩し、尿失禁することもあります。間代相の後半では、非同期性や非対称性がみられることもあり、通常30秒から1~2分続きます。咬舌が起こることもあります。
間代が止まると発作は終了し、回復期に入ります。患者さんは昏睡状態となり、反応はなく脱力しています。ため息のような深い吸気で呼吸が再開され、口腔内分泌物の増加や筋弛緩の影響で、いびきのような呼吸を呈することもしばしばであります。
その後、徐々に反応性が戻り始め、このときに自動症がみられたり、不穏な様子を示すこともあります。放置するとそのまま寝てしまうか、目覚めても強い倦怠感、筋肉痛、頭痛などを訴える場合があります。
てんかん性スパズム
てんかん性スパズムは、特に乳児期にみられるてんかん発作(発作型)です。焦点性・全般性のいずれの場合もあります。
体軸(首や体幹)と上肢近位筋の突然の短い収縮(多くは1~2秒)が特徴です。発作時に「点頭」という頭部の前屈する動きがみられることから、以前は点頭てんかんとも呼ばれていました。
てんかん性スパズムは短時間の間隔で繰り返し生じることが多く、群発あるいは一連の発作を「シリーズ」と呼ぶことがあります。頭部の前屈は座位をとるとみられやすくなり、スパズムが生じると泣き始める子も少なくありません。
筋収縮の強さや、巻き込まれる筋肉の範囲は同一患者さんでもさまざまであり、微細な発作の場合は動きだけで判断しづらいため、脳波検査で確認する必要があります。
小児てんかんの診断と鑑別
小児てんかんは、年齢や発達段階によって症状の現れ方が異なるなど、さまざまな発作症状がみられます。また、小児特有の疾患や発作と紛らわしい症状も多く存在するため、鑑別が不可欠です。
小児てんかんの診断・検査方法
小児のてんかんも、診断の進め方は成人と基本的には変わらず、問診、脳波検査、MRIなどの画像診断、血液検査が基本です。なお、小児は成人よりも脳波検査で異常が検出されやすい傾向にあります3)。
また、小児の発作は、低血糖や電解質の異常が原因となっている場合もあります。そのため、血液検査は、こうした要因による急性症候性発作かどうかを見極めるうえで重要です。
診断においては、特に発作の様子の詳しく把握することが重要であり、保護者が撮影した動画や発作時の様子の記録が有力な手がかりとなります。問診は、発作の頻度や持続時間、症状に加え、発達状況や学校での様子、生活環境の変化、保護者の育児上の悩みなど、背景となる情報もあわせて確認します。
鑑別すべき疾患
小児では、てんかん以外にもけいれんや発作様症状を示す疾患が複数あり、慎重な鑑別が重要です。以下は、小児てんかんと鑑別が求められる代表的な疾患とその特徴です(表3)。
表3 小児てんかんと鑑別すべき主な疾患
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| 熱性けいれん | 38℃以上の発熱に伴う発作 主に生後6カ月から60カ月までにみられる通常38℃以上の発熱に伴う発作(けいれん性、非けいれん性を含む)で、ほかに明らかな発作の原因がみられないもの |
| 憤怒けいれん(泣き入りひきつけ) | 激しく泣いた後に急に息を止め、意識消失や脱力がみられる(てんかん発作ではない) |
| 軽症胃腸炎関連けいれん | ウイルス感染(例:ロタウイルス)に伴う軽度の下痢や嘔吐、脱水により生じる発作(急性症候性発作) |
| 睡眠時ミオクローヌス | 入眠時あるいは睡眠中にみられる筋肉のピクつき(生理的現象) |
| 夜驚症・睡眠時遊行症 | 睡眠中に突然叫んだり、立ち上がったりする 覚醒させようと思っても目覚めず、本人に記憶はない(てんかん発作ではない) 動きは、てんかん発作ほどステレオタイプではないが、区別のためにはビデオ脳波モニタリングが必要になることもある |
このほかに、非てんかん性の無呼吸、身震い発作(shuddering attack)、チック、神経調節性失神、心因性非てんかん発作、マスターベーション、急性代謝障害なども、てんかんとの鑑別が必要となる場合があります。
小児てんかんの治療
小児てんかんの治療は、まず薬物療法が基本です。一方で、近年では薬剤抵抗性が明らかな場合など、早期の外科的治療も積極的に検討されるようになっています。小児の脳は発達段階にあり、発作の早期抑制が神経発達を含めた予後に影響することがあります。成人と同様に、小児でも初回の非誘発性発作で治療を開始せず、2回目の発作で治療を開始しても長期的な予後は変わらないといわれています4)。
例えば、発作頻度が少なく自然終息性が見込まれるてんかん症候群では、治療を開始せずに経過をみることも選択肢にあります。一方、乳児てんかん性スパズム症候群では、早期の治療が予後改善と関連することが示唆されており、患者さんに応じて早期治療の推奨される状況もあります5)。
発作型・症候群に応じた薬物療法
小児てんかんの薬物療法では、発作型やてんかん症候群の分類に基づき、適切な抗てんかん発作薬が選択されます。以下は、小児の主な発作型および代表的なてんかん症候群に対する第一選択薬と追加薬を示したものです(表4)。
表4 小児の主な発作型・てんかん症候群の推奨薬
| 発作型 | 第一選択薬 | 追加薬 | |
|---|---|---|---|
| 全般発作 | 全般強直間代発作 | オクスカルバゼピン※、カルバマゼピン、バルプロ酸、ラモトリギン | クロバザム、トピラマート※、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム |
| 強直発作 脱力発作 |
バルプロ酸 | ラモトリギン | |
| 欠神発作 | エトスクシミド、バルプロ酸、ラモトリギン | エトスクシミド、バルプロ酸、ラモトリギン | |
| ミオクロニー発作 | トピラマート※、バルプロ酸、レベチラセタム※ | トピラマート※、バルプロ酸、レベチラセタム※ | |
| 焦点発作 | オクスカルバゼピン※、カルバマゼピン、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム | オクスカルバゼピン、カルバマゼピン、ガバペンチン、クロバザム、トピラマート、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム | |
| てんかん症候群 | 第一選択薬 | 追加薬 | |
| 小児欠神てんかん 若年欠神てんかん |
エトスクシミド、バルプロ酸、ラモトリギン | エトスクシミド、バルプロ酸、ラモトリギン | |
| 中心・側頭部に棘波を示す良性小児てんかん | オクスカルバゼピン※、カルバマゼピン、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム | オクスカルバゼピン、カルバマゼピン、ガバペンチン、クロバザム、トピラマート、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム | |
| 若年ミオクロニーてんかん | トピラマート※、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム | トピラマート※、バルプロ酸、ラモトリギン、レベチラセタム | |
| West症候群 | 専門施設に相談・紹介 ACTH、ステロイド、ビガバトリン |
||
NICEガイドライン2012より引用改変
「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:小児・思春期のてんかんと治療.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.49-50.より引用
外科的治療と早期介入の重要性
小児期発症の薬剤抵抗性の焦点てんかんには、海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかんや、限局性皮質異形成をはじめとする外科的治療の有効性が確立されている病因があります。
さらに、小児(乳幼児期)は神経機能の可塑性が高く、言語野などの部位を含む手術でも、対側の大脳半球が機能を補う可能性もあります。成長してからは後遺症の懸念からできない手術が、若年だと実施できる可能性があるということです。
進学や就職などの今後の社会生活を見据え、発作を早期に抑制することは、将来のQOL向上にも繋がります。薬物治療に加え、外科的治療も早期から検討すべき選択肢のひとつといえます。
食事療法(ケトン食療法)
てんかんの治療法のひとつに食事療法があります。なかでも、主に小児に用いられているのが「ケトン食療法」です。これは、炭水化物を制限し脂質を多く摂ることで体内にケトン体を産生させ、それを脳のエネルギー源とすることで発作を抑える効果があるとされています。
ケトン食療法では、脂肪・タンパク質・炭水化物の比率が一定になるよう毎食を計算し、医師や管理栄養士の指導のもとで行います。あらゆる発作型に有効である可能性がある一方、家族と同じ食事ができなかったり、準備の負担が大きいという課題もあります。導入にあたっては、低血糖や体重減少などの副作用に注意をしつつ、安全に食事療法を行えるよう定期的な副作用モニタリングを行います。
ケトンフォーミュラという特殊ミルクを使うことで、効率の良い治療が行えます。ただし、ミルクだけの食事となるため、対象は乳児や経管栄養を使用している小児などに限られます。一方で、主に学童以降の小児や成人向けには、糖質制限を緩めた「修正アトキンス食」という食事療法もあります。
これらの食事療法は効果がみられた場合、数年後に制限を緩めても効果が持続する場合があり、薬物療法に代わる治療の選択肢として注目されています。West症候群やグルコーストランスポーター1欠乏症などでは、ケトン食の有効性がより高く期待されています。
小児てんかんの看護・支援のポイント
小児てんかんの看護では、発作前、発作時の対応に加え、発作間欠期における日常生活や心理面への支援も重要です。安全確保はもちろん、子どもの生活環境や発達段階に応じて、継続的な観察と個別性の高い支援が求められます。
発作に備えた観察と環境整備
年齢にもよりますが、小児は成人よりも意識がある発作(前兆)を把握しにくいことがあります。成人は症状や前兆をある程度言語化できますが、子どもは母にしがみついたり泣いたりなどの行動で表現することがあります。発作前の言動や行動を見逃さず、その後に起こる可能性がある意識のない発作時を察知とすることが重要です。
また、小児は自ら危機回避するのが難しいことも多いため、周りの環境を整えることが重要です。机や洗面台の角を保護、クッションマットの使用、できる限り座って行えるように声掛けするなどの準備や工夫を行います。
一方で、子どもは遊びや活動を通じて成長発達するため、安全対策に偏りすぎると発達の妨げになる可能性があります。発作の種類や頻度を踏まえ、家族や主治医と連携しながら、安全と成長発達のバランスを考慮した対応が求められます。保育園・幼稚園や学校と情報共有することも大切です。
さらに成人と同じく、発作の特徴を事前に把握しておく必要があります。どこから始まるのか、転倒の仕方や方向はどうかを知り、どの側に立って介助するか、どのように支えるかを状況に応じて判断するためです。必要に応じて保護帽の着用を検討し、ファッション性の高いものなど、形状は本人や家族と相談して選びます。
小児てんかんは年齢や発達段階に応じて発作型が多様に変化するため、発作の種類や起こりやすい状況を正確に把握することが、発作時の適切な対応やその後の支援に繋がります。
発作時の対応
発作時はまず安全確保を最優先とし、意識消失や転倒を伴う発作では頭部外傷のリスクを避けるために身体を支え、平らな場所に寝かせ、周囲の危険物を取り除きます。
安全が確保できたら、発作の経過や動き、意識の有無などを詳細に観察・記録します。時間経過とともに発作の変化を記録し、左右差(偏視、力の入り具合、伸展、屈曲など)も確認します。
子どもの年齢や発達によっては、意識の有無や回復状況の確認が難しい場合もありますが、ありのままを観察して記録に残しましょう。これらの情報は、今後の診断・治療方針の決定や看護計画に重要な手がかりとなります。
成長発達を考慮した支援
発作や抗てんかん発作薬は成長発達に影響を与えることがあります。また、発達障害を併せもつ子どももいます。治療はてんかん発作の減少や消失に注目されがちですが、患者さんは常に成長し、発達しているため、大きな妨げにならないように十分考慮しながら、多職種で情報共有して支援していくことが大切です。
日常生活における支援
てんかんのタイプや発作の誘発要因を踏まえ、個別性の高い生活支援の計画が求められます。退院後の家庭や学校生活に対応するため、保護者から以下のような生活状況について幅広い情報を聞き取ります。
・発作の傾向(時間帯・場面)・日常の過ごし方
・食事中の様子
・自宅の間取り(浴室・トイレ・寝室などの)
・通学経路や手段
・所属する部活動
これらの情報をもとに、発作時の事故リスクを減らすための対策を検討します。
具体例として
・調理は包丁の代わりに先端の丸いハサミを使う
・通学方法は発作の種類・頻度に応じて決める
安全を確保しつつ、子どもの意思を尊重した支援が必要です。保育士やリハビリ、院内学級などと連携して情報共有し、入院時から退院後も含めた成長発達を考慮した計画を入院時から意識します。退院後、家族だけでなく、保育園・幼稚園や学校と連携することも大切です。
こうした支援を通じて、本人と保護者が日常生活での安全対策を理解し、自信をもって生活できるよう支援していくことが重要となります。
保護者への支援と心のケア
保護者への支援も、てんかん看護での重要な役割のひとつです。例えば、発作時の対応や食事療法をする場合の毎日の食事管理、知的障害を併存する子どもの介助など、保護者が抱える身体的・精神的な負担は少なくありません。
家族の困難は多岐にわたりますが、主に以下のようなものがあります。
・社会的にてんかんへの偏見があり、受容しにくいこと
・成長発達に目を向けることやリハビリを始めることが難しいこと
・同じ状況の家庭が少なく孤独になりやすいこと
こうした状況に陥りやすい家族に対して、看護師は悩みや不安に寄り添いながら、支援策を一緒に考え、保護者自身QOLの維持・向上を図ることが求められます。
スティグマの解消に向けた取り組み
てんかんには社会的なスティグマ(偏見や誤解)が存在します。また、患者さん自身がてんかんに対してスティグマを抱き、自己嫌悪に陥っていることも少なくありません。てんかんをもつ子どもにかかわる人々がてんかんへの理解を深め、正しい情報を周囲に伝えることで、患者さんを取り巻く環境を変え、スティグマを減らしていくことが求められます。
例えば、学校生活をほかの子と同じように過ごすためには、学校側の理解が不可欠です。医療者が教員に対して直接発作時の対応などを伝えるなど、理解を促すための取り組みが重要となります。
てんかんを理由に制限を決めるのではなく、本人の興味や希望を実現するために、主治医・家族・本人が共によく考え、医師の判断を基づきできることを検討することが、患者さんのQOL維持・向上に繋がります。
また、患者さんも自身も一緒に考えることは、今後自分で考えて判断する力を育む大きな一歩となります。保護者、主治医、看護師だけでなく、患者さんも一緒に歩むことを忘れないように心がけながら支援することが大切です。
引用・参考文献
1)Berg AT,et al:Classification of childhood epilepsy syndromes in newly diagnosed epilepsy: interrater agreement and reasons for disagreement.Epilepsia 1999;40(4):439-44.2)Robertson J,et al:Prevalence of epilepsy among people with intellectual disabilities: A systematic review.Seizure 2015;29:46-62.
3)「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかん診療のための検査.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.17.
4)「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:小児・思春期のてんかんと治療.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.43.
5)O’Callaghan FJK,et al:The effect of lead time to treatment and of age of onset on developmental outcome at 4 years in infantile spasms: Evidence from the United Kingdom Infantile Spasms Study.Epilepsia 2011;52(7):1359.
・公益財団法人 日本てんかん協会:てんかんについて.(2025年7月14日閲覧)https://www.jea-net.jp/epilepsy
・日本てんかん学会分類・用語委員会,編:ILAEてんかん発作型・分類2017:日本語版.「てんかん研究」 2019;37(1):6-14.
・ 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかんの診断・分類,識別(REM睡眠行動異常症を含む).てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.2-16.
・川上康彦:小児てんかん.日本医科大学医学会雑誌 2022;18(4):333-8.
・日本てんかん学会分類・用語委員会,編:ILAE による特発性全般てんかん症候群の定義:ILAE 疾病分類・定義作業部会の公式声明.「てんかん研究」 2024;41(3):703-31.
・日本てんかん学会分類・用語委員会,編:小児期に発症するてんかん症候群の国際抗てんかん連盟(International League Against Epilepsy)の分類と定義:ILAE 疾病分類・定義作業部会の公式声明.「てんかん研究」 2024;41(3):616-65.
・日本てんかん学会分類・用語委員会,編:新生児・乳児期に発症するてんかん症候群の国際抗てんかん連盟の分類と定義:ILAE 疾病分類・定義作業部会の公式声明.「てんかん研究」 2024;41(3):561-615.
・てんかん情報センター:てんかん症候群.静岡てんかん・神経医療センター(2025年7月12日閲覧)https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/news/n15-2/
・てんかん情報センター:意識が短時間とぎれる発作.静岡てんかん・神経医療センター(2025年7月12日閲覧)https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/news/n2-5/
・難病情報センター:年齢依存性てんかん性脳症(平成21年度).(2025年7月14日閲覧)https://www.nanbyou.or.jp/
・難病情報センター:ウエスト症候群(指定難病145).(2025年7月14日閲覧)https://www.nanbyou.or.jp/entry/4414
・Christian K,et al:Do generalized tonic-clonic seizures in infancy exist?. Neurology 2005;65(11):1750-3.
・ 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかん診療のための検査.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.17-24.