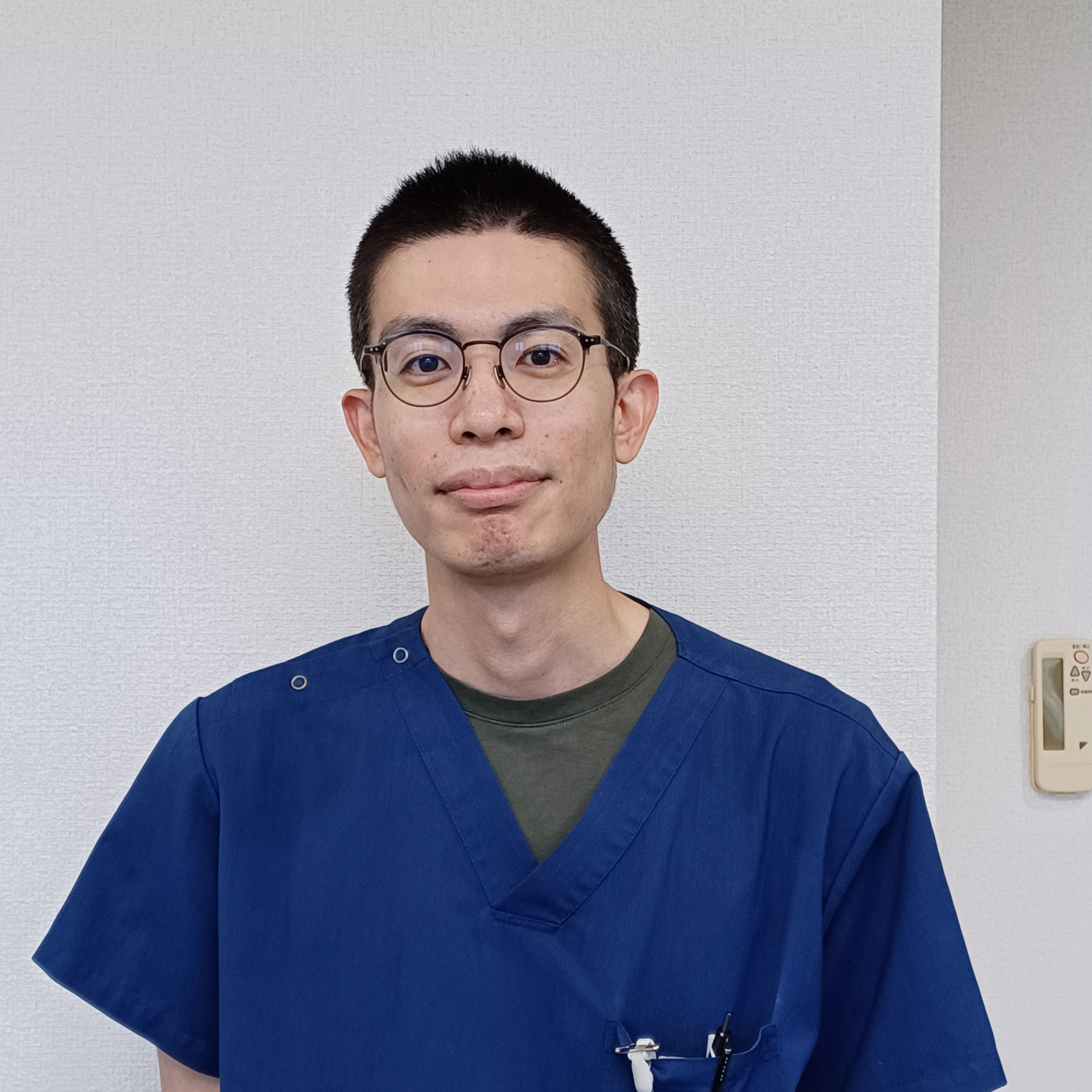【連載】てんかんケア完全ガイド|基礎から応用知識を現場で活かす!
 高齢者てんかんの看護│原因、症状、診断、治療、看護ケアのポイント
高齢者てんかんの看護│原因、症状、診断、治療、看護ケアのポイント
- 公開日: 2025/10/1
高齢者てんかんとは
2010年に発表された日本てんかん学会の「高齢者のてんかんに対する診断・治療ガイドライン」では、WHOの高齢者の定義(65歳以上)に準じ、65歳以上を対象としたてんかんを「高齢者のてんかん」として取り扱っています1)。
小児期にてんかんを発病した人が高齢になった場合と、高齢期に新たにてんかんを発病した場合には、その原因は大きく異なります。本稿では、主に高齢で「発症」したてんかんを対象に、「高齢者てんかん」という用語で説明します。
てんかんは大脳の神経細胞が過剰に興奮することでてんかん発作を起こす慢性の脳疾患です。発症年齢は小児期(特に3歳以下)に多いとされていますが、その後はいったん減少し、中年から高齢になるにつれて再び増加する傾向があります。現状、65歳以上でのてんかん有病率は一般人口の1%を超えることが報告されています2)。特に75歳以上は、すべての年齢層のなかで、最もてんかんの発症が多く、てんかんは子どもだけの疾患というイメージは正しくありません。
高齢者てんかんの原因
高齢者のてんかんの多くは、脳の疾患や損傷などに起因する「構造的病因」に分類されます。また、脳卒中の後遺症に加え、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病を併せもつことや、認知機能の低下がみられることも少なくありません。
以下に高齢者てんかんの代表的な原因を解説します。
脳卒中
高齢者のてんかんの原因のなかで最も多いのが脳卒中であり、全体の約30~50%を占める3)4)との見解があります。特に、急性症候性発作(脳卒中発病7日以内の発作)を起こしたり、重症度が高かったり、出血を伴う脳卒中や皮質に損傷がある場合、てんかんの発症リスクは高まる傾向にあります。
例として、心房細動などの不整脈により心臓内に形成された大きな血栓が脳の太い動脈を閉塞して発症する心原性脳塞栓症は、広範囲かつ重度の脳障害を引き起こしやすく、その結果、麻痺などの後遺症に加え、てんかんを合併する可能性が高くなるようです。
なお、脳卒中のタイプ別にみると、出血性脳卒中(脳出血・くも膜下出血)が最もてんかんを発症しやすく、次いで心原性塞栓症、血栓性脳梗塞の順でリスクが高いとされています。
神経変性疾患、外傷性脳損傷(TBI)など
原因不明のものを除くと、脳卒中の次に多い原因は神経変性疾患であり、次いで外傷性脳損傷、脳腫瘍が続きます。神経変性疾患の代表例としてアルツハイマー病が挙げられますが、認知症患者さんにみられる行動の変化や記憶障害とてんかん発作の鑑別が難しく、発症率は文献により5~64%5)と幅がありますが、概ね10~20%との報告が多い6)です。一方、高齢者に多いパーキンソン病は、てんかんを発症することは多くないといわれています。
そのほか、原因不明のてんかんも全体の25~40%を占めており5)、側頭葉を起始とする焦点発作として発症する例などがみられます。
高齢者のてんかん発作にみられる特徴
高齢者のてんかんは、若年者とは異なる原因で発症することが多く、その発作型や症状(発作症候)にも高齢者特有の特徴がみられます。以下に、高齢者てんかん発作にみられる主な特徴をまとめました。
高齢者てんかんに多い発作タイプ
高齢になって発症するてんかんの多くは、脳卒中や脳腫瘍などの脳の構造的異常に起因するため、主な発作のタイプは焦点発作になります。
なかでも「焦点意識減損発作」が多くみられたという報告もあります。また、焦点起始発作が脳の広範囲に広がり、全身のけいれんを引き起こす「焦点起始両側強直間代発作」がみられることもあります。
焦点意識減損発作とは
高齢者に多い焦点意識減損発作は、普通に会話していたのに急にぼーっとしたり、動作が突然止まったりしたかと思うと、すぐに元に戻るといった症状が特徴です。
このときに、口をもぐもぐ、あるいは舌をぺちゃぺちゃと鳴らす口部自動症や、衣服や周囲のものを無目的に触る手の自動症がみられることもあります。ただし、自動症を含む運動症状は、若年者に比べて高齢者の焦点発作では頻度が少なく、非運動症状の発作が多いため、発作に気づかれにくい傾向にあります。
さらに、この発作はたとえ異変に気づいても、加齢や認知症によるものと受け取られやすく、家族や周囲がてんかんの発症に気づかないケースも少なくありません。その結果、医療機関を受診せず見過ごされてしまうことが課題となっています。運転中に生じると、交通事故につながりかねません。
高齢者で注意すべき「てんかん重積状態」
てんかん重積状態とは、てんかん発作が5分以上続く、あるいは意識が回復しないまま次の発作が生じる状態のことを指します。高齢者ではてんかん重積状態の頻度が高く、元々のフレイルや併存症によって生命にかかわる、または重度の後遺症を残す可能性があります。
ここで重要なのは、てんかん重積状態は「てんかん」の名前がついていますが、半数以上は急性症候性発作である7)ということです。すなわち厳密には、慢性のてんかんではありません。
高齢者はてんかんの頻度が高いことを先に述べましたが、急性症候性発作も多いことがわかっています。急性症候性発作の場合、抗てんかん発作薬の治療だけではしばしば不十分で、原因となる疾患の治療が重要になってきます。また予後も原因疾患に左右される要素も多くあります。
また、高齢者は非けいれん性てんかん重積状態(NCSE)の割合も高く8)、軽度の意識障害や行動異常、精神症状として出現することもあり、そもそもてんかん発作が疑われなかったり、脳波検査が必要なので、診断が難しい傾向にあります。
高齢者の急性の意識障害、認知機能低下、異常行動が原因不明の場合には、速やかに脳波検査を実施する、NCSEと診断・除外できる医師・医療機関へ相談するなど、背景となる病態や全身状態も踏まえたうえで、適切な治療方針を検討することが重要です。
高齢者てんかんの診断と治療
高齢者のてんかん診療も、基本的な診断・治療の流れは若年者と共通しています。しかし、高齢者は加齢に伴う身体機能の変化や併存症の影響に加え、薬効や副作用の出方が若年者と異なるため、診断や治療にあたっては注意が必要です。
高齢者てんかんの診断・検査と留意点
高齢者のてんかん診断も、基本的には問診、脳波検査、MRIなどの画像診断、血液検査を組み合わせて総合的に評価します。ただし、高齢者特有の課題があり、以下の点に留意が必要です。
初回の非誘発性発作の再発率が若年者よりも高い
高齢者では、初回の非誘発性発作の場合、再発率が高い傾向にあるため、1回目の非誘発性発作でもてんかんと診断することがしばしばあります。
例えば、過去に大脳の心原性脳塞栓症の既往があり、1年後にてんかん発作を起こした場合、仮に脳波が正常であっても再発率が高いことがわかっているので、その時点で「脳卒中後てんかん」と診断し、薬物治療を開始することはよくあることです。
脳波異常が検出されにくい傾向にある
高齢者では、非特異的な異常所見があっても、てんかん特有の脳波異常がみつからないことがあり、短時間の脳波検査では診断が難しくなる場合があります。
このような場合には発作の様子と長時間の脳波を同時に記録できる「長時間ビデオ脳波モニタリング」が有効です。特に、明らかな原因がないケースでは、診断の精度を高める手段として推奨されます。
多様な疾患や薬剤の影響の鑑別が必要
高齢者は複数の疾患を抱えていることが多く、発作の原因がてんかん以外の疾患や、服用している薬剤の副作用による可能性もあります。
そのため、診断では多くの疾患や薬剤による影響を見極めることが求められます。正確に診断できれば、適切な治療によって症状が改善するケースも少なくありません。
高齢者てんかんと間違えやすい疾患
高齢者では、てんかん発作と似た症状を示す疾患も多く、鑑別が必要です。以下に、誤認されやすい疾患例を挙げます。また、急性症候性発作も多いので、症状の診断だけではなく、原因の診断も重要といえます。
認知症
高齢者のてんかんでよくみられるぼーっとするなどの症状は、認知症と誤認されることがあります。認知症やその原因となる脳血管障害は、てんかんの発症リスクにもなるため、適切な診断が必要です。
失神
失神は高齢者にもよくみられる症状で、てんかん発作と間違えられることがあります。なかでも心原性失神は、重篤なリスクを伴うため早期発見と治療が重要です。てんかんと類似する症状も多いため、脳波検査に加え心電図検査などもあわせて行う必要があります。
また、起立性低血圧による失神も多くみられます。糖尿病やパーキンソン病などによる自律神経障害や、高血圧や前立腺肥大症の治療薬などが原因となることがあります。
一過性全健忘
ある時間帯の記憶が完全に抜け落ちる一過性全健忘も、てんかんと間違えられやすい疾患のひとつです。普段通りの行動や会話をしていても、後でその記憶がなくなる特徴があり、数時間から1日の記憶がなくなる場合もあります。
精神的・身体的ストレス、シャワーやプールといった水への接触や温度変化などがきっかけになる場合があり、MRIの拡散強調画像(DWI)で海馬に小さな異常信号が認められることがあります。症状が改善した発病2日後くらいに陽性になるケースもよくみられます。
記憶だけが障害されるのみで、患者さんは不安がって同じことを何度も聞くなどの行動がしばしばみられます。症状が回復した後も、思い出せない数時間の記憶の空白が残り、てんかん発作と比べて持続時間(数十分から数時間)が長いのが特徴です。基本的には良性の疾患です。
高齢者てんかんの治療法と薬剤選択のポイント
高齢者てんかんの治療は、薬物療法が基本です。比較的少量の抗てんかん発作薬で発作を抑えられることが多く、外科治療が適応となる例は限られます。
ただし、高齢者は薬剤の有効性が高い一方で、副作用が生じやすいため、少量の投与から開始し、発作への効果と副作用をみながら徐々に増やしていく必要があります。薬剤の選択にあたっては、発作型に加えて、併存症や他剤との相互作用なども考慮する必要があります。
以下に、高齢者てんかんに使用されている主な抗てんかん発作薬の特徴をまとめました。
表1 主な抗てんかん発作薬の特徴
| 薬剤 | 主な特徴 | 高齢者に使用する際の注意点 |
|---|---|---|
| ラモトリギン | 焦点発作、強直間代発作、定型欠神発作に有効 精神症状の副作用リスクが低い 導入初期を副作用なく過ごせれば、長期的な忍容性は高い |
若年者よりも多いとはいえないが、重症薬疹のリスクに注意が必要 添付文書のとおり、またはそれよりも少量で緩徐な導入が推奨される 不整脈の副作用も起こりうるので、心疾患がある場合は、特に注意を払う |
| ガバペンチン | ほかの薬剤で効果不十分な焦点発作に対し、併用療法として使用される 薬物相互作用がほとんどない |
高齢者てんかんでの一定の有効性・忍容性のエビデンスはあるが、腎機能による用量調整が必要 ガイドライン上は、推奨されているが、単剤での保険適応がなく、明確な利点がないため、実際に処方されることは少ない |
| レベチラセタム | 焦点発作、またはほかの薬剤で効果不十分な強直間代発作に対する併用療法として使用される 効果発現が早く、薬物相互作用が少ない 不整脈の副作用は少なく、心疾患があっても使用しやすい |
内科的合併症のある高齢者の焦点発作に対して推奨される 腎機能障害では、用量調整が必要 攻撃性や抑うつといった精神症状の副作用リスクがある |
| カルバマゼピン | 成人の焦点発作の第一選択薬で推奨される 長年、その高い発作抑制効果は、ほかの新規薬剤に負けていない 薬価が安い |
合併症・依存症のない高齢者の焦点発作に有効だが、高齢者では、皮疹のリスクが高い 薬物相互作用も懸念されるため、合併症・併存症のある高齢者では、第一選択として推奨されていない |
| フェニトイン | 成人の焦点発作、全般強直間代発作の第二選択薬で推奨される 静注製剤があり、てんかん重積状態にも保険適応がある |
薬物相互作用に注意が必要 発作抑制効果は強いが、近年副作用から使用される機会は減っている 不整脈や血圧低下の副作用リスクがある |
| バルプロ酸 | 成人の全般強直間代発作や欠神発作の第一選択薬、焦点発作の第二選択薬として推奨される | 全般発作では推奨されるが、高齢者てんかんのほとんどが焦点発作であり、焦点発作への有効性は期待しづらい 振戦やパーキンソニズム、骨粗鬆症リスクにも注意が必要 |
| ラコサミド | 成人の焦点発作で、カルバマゼピンに劣らない有効性と忍容性が示された 忍容性はカルバマゼピンよりも優れているというデータもある |
副作用は少なめ ラモトリギンに比べて、皮疹の副作用も少なく、用量調整が容易で使いやすい 不整脈の副作用リスクには注意が必要 薬価は高い |
高齢者のてんかん治療においては、従来薬であるカルバマゼピン、フェニトイン、バルプロ酸よりも、副作用や薬物相互作用の少ないラモトリギン、レベチラセタムなどが選択される傾向にあります。眠気やふらつきは、抗てんかん発作薬の種類にかかわらず共通してみられる副作用です。
高齢者てんかんの看護|発作時の対応と発作間欠期のケア
ここでは、高齢者てんかんの看護において重要となる観察の視点や、発作時・発作間欠期の対応やケアについて整理します。
高齢者てんかんの看護におけるポイント
高齢者のてんかんに多くみられる焦点意識減損発作は、会話や動作の途中で突然停止し、ぼんやりとした状態になるのが特徴です。通常は短時間で自然に回復するため、発作と気づかれず見過ごされることも少なくありません。
このタイプの発作は薬物療法による改善効果が得られやすいため、早期発見と受診が重要です。日常の会話や入浴介助などのケアの際に、反応や動作が停止したり、会話が突然途切れたりといった異変がみられた場合は、認知機能の低下によるものと安易に判断せず、てんかんの可能性も念頭に置いて状況を観察・記録し、受診を検討することが求められます。
一方、高齢者で焦点起始両側強直間代発作のような大きい発作の場合は、発作後の意識障害や認知機能低下が遷延し、回復に数日から1週間ほどかかる場合もあります。また、てんかん発作にしては持続時間が長いという場合は、レビー小体型認知症の中核症状の1つである認知機能の変動や、高齢者に多いせん妄も鑑別にあがります。
発作時の対応
焦点意識減損発作が起きた際は、動作停止していることが多く、わかりにくいことも少なくありません。動作途中で停止していることもあるため、不安定な体位である場合、転倒転落を防ぐため、安全な状況に整えます。
そして、てんかん発作の観察(例えば、名前を呼んで返答できるか、自分の名前が答えられるか、何か簡単な単語を覚えられるか、簡単な指示を伝えてできるか、簡単なものを見せて何かわかるか、そのものはどのように使うものかわかるか、などの確認)をします。
多くの発作は短時間で自然におさまるため、無理に身体を動かしたり声をかけたりせず、発作が終わるまで見守ります。発作中や発作後の様子についての詳細な記録は、その後の診断や治療方針の検討に役立ちます。状況が許すならビデオ撮影も有効になります。
意識が戻ってきたら、発作中にお伝えした内容や発作前の状況(前兆はなかったか)を確認し、記録に残します。
発作間欠期のケア
日常生活における発作の誘発因子や発作パターンを把握するためには、日々の観察に加え、患者さんや家族、介護者からの聞き取りによる情報収集が重要です。具体的には、発作が出現しやすい場所や時間帯、前兆(焦点意識保持発作)の有無、発作症候の内容、発作の持続時間、生活リズム、服薬状況などが挙げられます。
得られた情報をもとに、発作による転倒や事故を防ぐための環境整備を行います。例えば、入浴時に発作が起きやすい場合は、シャワーチェアや滑り止めマットを設置し、長時間座る場合には体幹を安定させるためのクッションやベルトを活用するなど、個別性に応じた対策が求められます。
また、患者さんの体格や身体状況によっては複数人での介助が必要となる場合もあります。これらの対応は記録と評価を繰り返し行い、より安全なケア環境の構築につなげます。
動作停止してぼんやりしている焦点意識減損発作は、周囲からはわかりにくく、特に高齢者は難聴であったり、声掛けへの反応が鈍いこともあるため、てんかんと診断がつきにくい場合も少なくありません。
こうした背景から、患者さんの身近にいる看護師が高齢者のてんかんの特徴を理解しておくことは、診断の契機となり、早期治療につながる可能性もあります。てんかんと診断されていない高齢者に対する日常の観察や症状の発見も、重要な看護といえるでしょう。
引用・参考文献
1)日本てんかん学会ガイドライン作成委員会,編:高齢者のてんかんの診断・治療ガイドライン.てんかん研究 2010;28(3):510.2)Akihiro T,et al:Prevalence of adult epilepsy in a general Japanese population: The Hisayama study.Epilepsia Open 2019;4(1):182.
3)Leppik IE : Epilepsy in the elderly.Epilepsia 47 Suppl 1 2006:66.
4)Assis TR,et al:Etiological prevalence of epilepsy and epileptic seizures in hospitalized elderly in a Brazilian tertiary center – Salvador – Brazil.Arq Neuropsiquiatr 2015;73(2):85.
5) 日本神経治療学会治療指針作成委員会,編:高齢発症てんかん.標準的神経治療 ,2012,p.464.
6)Vossel KA,et al:Epileptic activity in Alzheimer’s disease: causes and clinical relevance.Lancet Neurol. 2017;16(4):312.
7) Chin RF,et al:A systematic review of the epidemiology of status epilepticus.Eur J Neurol 2004;11(12):800,807.
8) 吉村元:高齢者のてんかん重積状態.神経治療学 2019;36(4):483.
・ 日本神経治療学会治療指針作成委員会,編:高齢発症てんかん.標準的神経治療 ,2012,p.459-79.
・Aathmika N,et al:Incidence and risk factors of post-stroke seizures and epilepsy: systematic review and meta-analysis.Journal of International Medical Research 2023;51(11):1-18.
・Friedman D,et al:Seizures and Epilepsy in Alzheimer’s Disease 2011;18(4):285–94.
・赤松直樹:高齢者てんかんの診断と治療.日本老年医学会雑誌 2021;58:529-32.
・Pirgit ML,et al:EEG and semiology in the elderly: A systematic review.Seizure 2025;128:90-121.
・Werhahn KJ,et al:Epilepsy in the Elderly 2009;106(9):135-42.
・Hauser WA,et al:Incidence of epilepsy and unprovoked seizures in Rochester, Minnesota: 1935-1984 1993;34(3):453-68.
・日本てんかん学会ガイドライン作成委員会,編:高齢者のてんかんの診断・治療ガイドライン.てんかん研究 2010;28(3):509-14.
・Chin RF,et al:A systematic review of the epidemiology of status epilepticus.Eur J Neurol 2004;11(12):800-10.
・水牧功一,他:失神の診療.日本心臓病学会誌 2008;(2):2-18.
・Van Cott AC,et al:Epilepsy and EEG in the elderly.Epilepsia 2002;3:94-102.
・Tarun PJ,et al:Transient global amnesia: Diffusion MRI findings.Indian J Radiol Imaging 2018;28(1):6-9.
・中里信和:てんかん薬物治療の進歩と日本の特殊性.脳神経外科ジャーナル 2014;23(8):622-6.
・ 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:成人てんかんの薬物療法.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.25-38.