
HealthDay News編集部
記事数:232

記事数:232
15件/232件
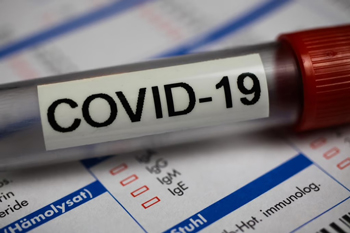
重症の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、心筋梗塞や脳卒中、全死亡などの主要心血管イベント(MACE)リスクを高め、その程度はCOVID-19に罹患していないが心疾患の既往歴がある人のリスクとほぼ同程度であることが、米クリーブランドクリニック・ラーナー研究所心血

喫煙習慣のある高齢者の中には、「今さら禁煙しても意味がない」と考えている人がいるかもしれない。しかし、実際はそんなことはなく、高齢期に入ってから禁煙したとしても、タバコを吸い続けた場合よりも長い寿命を期待できることが明らかになった。例えば75歳で禁煙した場合、喫煙を続けた人

厚生労働省(以下、厚労省)は、10月9日に開催された中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会で、2026年度診療報酬改定の基礎資料とする第25回医療経済実態調査の進め方について、調査実施小委員会を開催、調査設計に向けた議論を開始することを提案し、中医協に了承された。

厚生労働省(以下、厚労省)は、9月20日に開催された第6回「医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」(以下、検討会)で、2026年度医学部臨時定員の配分について、医師多数県では臨時定員地域枠を一定数削減していくなどの案を提示した。 今回の

厚生労働省(以下、厚労省)は9月13日付で、「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を地方厚生局などに事務連絡で周知した。内容は、2024年度診療報酬改定で設定された経過措置が9月30日で終了することを踏まえ、10月以降も継続算定する場合、

世界で初めて眼球移植と部分的な顔面移植を受けた男性が、手術から1年以上が経過した現在も順調に回復していることを、米ニューヨーク大学(NYU)ランゴン病院の医師らが報告した。同病院の顔面移植プログラムディレクターで形成外科部長でもあるEduardo Rodriguez氏らによ

眼圧と高血圧リスクとの関連性を示すデータが報告された。眼圧は基準範囲内と判定されていても、高い場合はその後の高血圧発症リスクが高く、この関係は交絡因子を調整後にも有意だという。札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座の古橋眞人氏と田中希尚氏、佐藤達也氏、同眼科学講座の

2040年ごろを見据えた新たな地域医療構想について検討している「新たな地域医療構想等に関する検討会」は9月6日、第8回検討会を開催し、入院医療について1回目の議論を行った。厚生労働省(以下、厚労省)は、現行の病床機能報告と併せて、新たに「医療機関機能」を設定した上で、その報

厚生労働省(以下、厚労省)は8月30日に開催された第181回「社会保障審議会医療保険部会」で、マイナ保険証の利用実績が著しく低い医療機関・薬局に対して個別に聞き取りを行う方針を示した。また、7月の利用率は前月比1.23ポイント増の11.13%と過去最大だったことも明らかにし

歳とともに体重が増えることによる血管への悪影響は60歳未満で顕著であり、60歳を超えると有意なリスク因子でなくなる可能性を示唆するデータが報告された。名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科の田野翔氏、小谷友美氏らの研究結果であり、詳細は「Preventive Medicine

新しいタイプのがん治療薬が、アルツハイマー病などの神経変性疾患の治療にも有用である可能性のあることが、米スタンフォード大学医学部神経学・神経科学教授のKatrin Andreasson氏らによるマウスを用いた研究で示された。詳細は、「Science」に8月23日掲載された。

脳梗塞で入院した時点の歯や歯肉、舌などの口腔状態が良くないほど、入院中に肺炎を発症したり、退院後に自立した生活が妨げられたりしやすいことを示すデータが報告された。広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学の江藤太氏、祢津智久氏らが、同大学病院の患者を対象に行った研究の結果であ

厚生労働省(以下、厚労省)は8月21日付で、「長期収載品の選定療養に関する疑義解釈(その2)」を都道府県等に発出、送付した。今回の内容は、10月1日に施行される長期収載品の選定療養について、処方箋の解釈や掲示事項、公費医療費などについて解説したものだ。 まず

新しい記憶を作るためには夜間の良質な睡眠が不可欠であることが、米コーネル大学神経生物学および行動科学分野のAzahara Oliva氏らによる新たな研究で示された。日中の記憶を保存したニューロン(神経細胞)は睡眠中にリセットされるのだという。研究の詳細は、「Science」

厚生労働省とデジタル庁は8月9日、「医療機関・薬局向けマイナ保険証利用促進セミナー」を共同開催し、医療費助成の受給者証・診察券とマイナンバーカードの一体化のためのレセコン改修の補助金や、医療機関・薬局への一時金、顔認証付きカードリーダーの増設支援の補助金の期間延長などについ