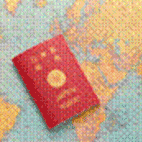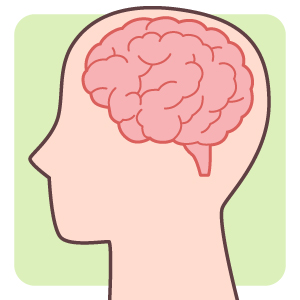第9回 麻痺・拘縮の観察とアセスメント
第9回 麻痺・拘縮の観察とアセスメント
- 公開日: 2012/11/5
麻痺・拘縮に伴ってさまざまな症状が引き起こされます。それを防ぐためにも、拘縮は早期に発見する必要があります。
今回はどんなところを観察すればよいのかを解説します。
拘縮は早期に予防、発見してリハビリにつなげる
麻痺や拘縮は、骨折や脱臼、褥瘡、肺血栓塞栓症といった二次的障害を引き起こすので、ADL評価によってどの程度動けるのかを評価し、二次的障害の発生リスクをアセスメントしていきます。
特に麻痺側は感覚がないため、体位変換などの際に麻痺した腕が身体の下に挟まっても、患者さん本人は気付かず、二次的障害を起こすこともあります。
また、移動時にどの部位を保護したらよいのかも重要になるので、どこに麻痺あるいは拘縮があるのかをきちんと確認することが大切です。
参考になった
-
参考にならなかった
-