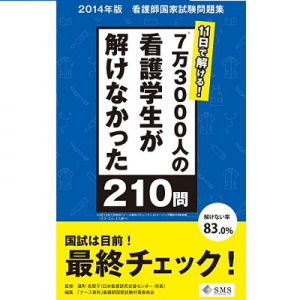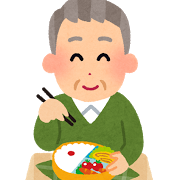 高齢者の栄養管理の現状を聞く!
高齢者の栄養管理の現状を聞く!
- 公開日: 2017/2/2
高齢者はさまざまな要因が重なって、十分な栄養を摂取できなくなるケースがみられます。
また、在宅で療養している患者さんの場合、きめ細やかに食事指導をしても、きちんと実践できるとはかぎりません。
今回は、高齢者看護に携わるみなさんにお集まりいただき、高齢者の栄養管理の現状をお聞きしました。

体調悪化で低栄養のリスクが高まる高齢者
日々の看護の中で高齢者の栄養管理についてどのように感じていますか。
●兼本 回復期リハビリテーション病院には、低栄養の高齢患者さんが多いです。低栄養のままリハビリを開始するとエネルギーを消費してしまい、かえって筋肉が落ちてしまうことがあります。患者さんの栄養状態をみながら、エネルギー消費の少ない運動に代えてもらったり、リハビリ内容をセラピストと検討しつつ低栄養が改善できるようアプローチしています。
●佐藤 入院してくる人の多くは、脱水状態です。水分補給をして少し元に戻ってはじめて、低栄養だったことがわかってきます。低栄養を改善する際には、入院前はどのような食生活をしていたのか、あるいは今後どのような生活を望んでいるかを知ったうえで、方針を考えるようにしています。
●四條 リハビリが視野に入ってきたころに、担当患者さんが入院している病棟を訪問して、患者さんが自宅でどのように過ごしていたかを病棟の看護師さんに伝えるようにしています。認知症がある場合、ただ口元にスプーンを持っていくだけでは、なかなか食べてくれず、食事量が増えないから退院ができないと医師から言われることがあります。感染等の問題がなければ、家族の協力を仰いで、いつも自宅で食べていた状態に近づけた食事を持参してもらうことも試みています。また訪問時には、今までと同じ介護の方法で誤嚥なく摂取できるのかどうかを評価したりもします。これは、院内で行ったほうが安全にできるためで、協力をお願いしています。
●佐藤 認知症患者さんは体調が悪くなると認知機能も低下し、入院直前まで食べることができていたのに、食べられなくなることがあります。そして直前までちゃんと食べていた患者さんはその状態に戻れる可能性が高いのです。自宅でどのような生活をしていたのかを知ることで、どこまでの回復を目指すのかがわかります。だからこそ、訪問看護や地域包括支援センターなど地域との連携が必要なんです。
●四條 退院指導の際には、どういう療養環境の中でどう暮らしているのかを見越して指導をしていただけると助かります。また、訪問看護の私たちもできるだけ情報を伝えていく努力をしなければいけないと思っていますが、病院で看ていた看護師さんに自宅を訪問していただけるのもありがたいです。
●兼本 嚥下機能からみると、義歯が合わなくて、嚥下機能に問題をきたしている患者さんが多いです。また、在宅療養中は家にいるため、咀嚼しなくてもよい軟らかな物を食べて義歯を使わなくなってしまうこともあります。食形態が軟らかくなればなるほど加水されるため、かさが増えてしまいます。そうすると、見かけ上同じ分量を食べても実際の栄
養摂取量は減少し、低栄養を引き起こしてしまうことにつながるという悪循環が生じるのです。

大切なのは高齢者の状況に応じた栄養管理
食べやすい食形態や栄養を補う食品についても、患者さんや家族にお知らせする機会があると思いますが、どのように行っていますか。
●兼本 栄養を補うための食品に関しては、回復期では退院後、老老介護の人が多いため、カタログを見せながらお勧めしています。とろみ剤は病院と似たようなものを使ったほうがよいので、それを紹介するようにしています。初回の注文をお手伝いすることもありますね。
●四條 私も注文をお手伝いすることがあります。あとは、ADLや認知症のためご自身で荷物を受け取れない方には、訪問看護ステーションに届けてもらって、訪問時にお渡しすることもあります。
●佐藤 カタログ、電話、ネットでの注文など、いろいろな入手方法があると、その人に合った方法をお伝えできるのでよいと思います。こういった食品をお勧めする際に考えなければならないのは、経済状況ですね。
●四條 そうなんです。安いものではないので、継続できそうかどうか、まずはサンプルを取り寄せて試してもらうようにしています。味にも好みがありますから、気に入ってもらえたら、購入をお勧めしています。
●佐藤 絶食状態が続いていた高齢者にいきなり高カロリー食品を摂取してもらうと、胃腸の調子が悪くなり、下痢や嘔吐などの症状が出ることがあります。急性期では、段階的に切り替えていって回復させるのですが、高齢患者さんの状態・回復状況に応じた選択ができるといいですね。

今回は味の素株式会社のメディミル®プチロイシンプラスを事前に試していただきましたが、どうでしたか。
●四條 コーヒー牛乳風味がおいしかったです。脂質が多くてもったりしていたり、薄味で油っぽさだけがある製品が多いのですが、これはコーヒー牛乳に似ていて飲みやすかったです。
●兼本 メディミル®プチロイシンプラスには分岐鎖アミノ酸(BCAA)が含まれていています。必須アミノ酸の中でも特に重要な働きをするロイシンも多く配合されていますし、カラダ作りや健康維持に大切なビタミンD等の栄養成分がしっかり含まれています。うちでは、こういった製品はリハビリ直後に飲んでもらうようにしています。
●佐藤 リハビリ中や、日常生活上で少し動ける患者さんに飲んでもらうのはよさそうですね。
●兼本 通院するような持病がなくとも低栄養になっている高齢者は多いので、まずは自覚していただき、補助食品を上手に活用してコンディションが維持できるようになるとよいと思います。コンビニなどで気軽に買えるようになるとよいですね。
●佐藤 介護をしている方にも、この食品は有用だと思います。忙しい介護生活では、食事も簡素になりがちのようです。自分の体力を維持するためにもよいでしょう。介護が必要になってからだけでなく、早い時期からの栄養管理をしていくことが大切だと思います。