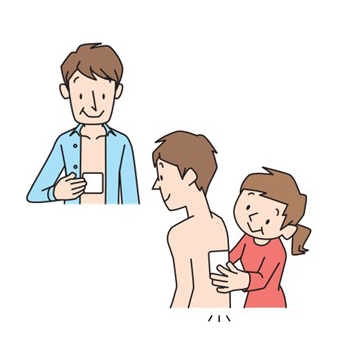与薬とは? 5R(6R)、剤形別特徴と投与の手順
与薬とは? 5R(6R)、剤形別特徴と投与の手順
- 公開日: 2018/3/22
【関連記事】
● 【服薬管理】ケア&対応の5つのワザ
● 今見直したい薬剤耐性(AMR)の現状と対策ー看護師に求められることを考えよう
● 【連載】安全・確実に実施する!与薬のポイント
与薬とは
与薬とは病気の程度やその症状に合わせて薬を与えることです。看護師は、医薬品を医師の指示のもと正しく与薬するための確認や管理、服薬指導、直接的な与薬の実施、実施後の観察など重要な役割を担っています。目的に合った効果が得られているか、また副作用がないかをしっかり観察し、治療にフィードバックしていくことが求められています。
注射法以外の主な与薬経路の種類としては、経口内服薬、口腔内薬、直腸内薬、点眼薬などで、そのほかに貼付剤、吸入剤、塗布・塗擦剤などがあります。
与薬時のエラーを減らすための対策として、指差し声出ししながら5項目(表1)についてRightつまり正しい事(5R)*を確認することが重要です。確認のタイミングは与薬指示受け時、与薬準備時(この間、更に3回)、与薬直前など各段間で確実に行いましょう。さらに準備時や施行直前などは2人以上の目で確認(ダブルチェック)を行うことも多くの施設で取り入れられています。そして、何かおかしいと感じたときは必ず立ち止り、確認や相談を行う意識を持つことも重要です。
*5Rだけでなく「正しい目的」、「正しい記録」などを含め6Rと言ったりもします。
表1 与薬の5R
| Right patient 正しい患者 |
患者氏名、生年月日、性別、病棟名、診療科 薬剤の作用と患者さんの病態 アレルギーの有無 |
| Right drug 正しい薬剤 |
薬剤名(商品名、一般名) 薬品区分(毒薬、劇薬、麻薬など) 薬剤の形状 使用期限、貯法および保管状況 |
| Right dose 正しい用量 |
薬剤の単位、用量、濃度 |
| Right route 正しい用法 |
与薬可能な方法、指示された投与経路 |
| Right time 正しい時間 |
処方日、与薬時間、注射速度 |
与薬の準備の共通事項
1 処方箋の記載内容と薬剤の記載内容について5Rを確認する。
2 これから使用する薬剤の作用と患者さんの病態が合っているか、年齢や性別、アレルギーの有無等も含めて総合的にアセスメントする。
3 患者さんへの説明と同意を得る。
剤形別特徴と投与の手順
1.経口内服薬
特徴
口から飲み込む与薬法ですので、基本的に食物と同じ経過をたどります。口腔を経て胃腸で消化された後、主に小腸で吸収され静脈血に入り、その後は門脈から肝臓へ送り込まれ、肝臓の働きによりさまざまな代謝を受けます。このように全身循環の前に肝臓で代謝処理されることを初回通過効果と言い、内服薬の体内動態の特徴として重要です。その後、血流によって全身を巡り、各種臓器や組織に分布し薬効を発揮します。消化、吸収、代謝に時間を要するため血中濃度の上昇、作用発現に時間がかかりますので、比較的病状が安定した場合に選択される与薬方法だと言えます。錠剤、丸薬、カプセル、粉末、液体などの形状が存在します。さまざまな目的で使用され与薬で取り扱う機会も最も多いのではないでしょうか。しかし、内服薬は飲み忘れや飲み間違いが効果に大きく影響するため、服薬管理が重要です。患者さんは内服薬の重要性を十分理解していない場合もあり、対象に合わせた服薬指導や管理を行うことも重要な看護師の役割です。嚥下や排泄状況も効果に影響するため、常に全身状態を観察、アセスメントし必要時に説明や援助を行なうことで患者さんのアドヒアランスを高め、安全な与薬を実施する事が看護職者に求められています。
表2 剤形の種類
| 裸錠 |
乳糖などと薬の成分を錠剤の形にしたもの |
| フィルムコーティング錠 |
裸錠を高分子化合物でコーティングした錠剤。苦味などをなくすことができます |
| 糖衣錠 |
裸錠を糖類または糖アルコールを含むコーティング剤でコーティングした錠剤。苦味などをなくすことができます |
| 腸溶錠 |
胃で溶けず、腸で溶けるように作られた錠剤 |
| 軟カプセル |
フィルム状の皮膜で、液状またはペースト状の薬を包んだもの |
| 硬カプセル |
粉末または顆粒状の薬をゼラチンなどを元にしたカプセルに入れたもの |
| 散剤 |
経口投与する粉末状の製剤 |
| 顆粒剤 |
経口投与する粒状に造粒した製剤 |
| 細粒剤 |
顆粒剤の中でも、粒の大きさが850μm以下で、30号(500μm)のふるいにかけたとき、残留するのが全量の10%以下の製剤をいう |
準備
1 経口摂取状況や消化器症状の有無を確認し、経口内服が可能かアセスメントする。
2 衛生学的手洗いをする。
3 使用物品として処方箋、薬剤、薬袋、吸い飲みやコップに水か白湯を準備する。
4 患者さんにこれから行う与薬方法、所要時間について説明し同意を得る。
5 患者さんを坐位が可能な場合は坐位に、坐位がとれない場合はギャッジアップ等で頭部を挙上し、嚥下しやすい姿勢に整えます。
手順
1 もう一度処方箋と薬剤の5Rを確認し、1回の指示量を包装シートから出す。
2 患者さんの嚥下状況に合わせて、1回に飲み込む量を調整する。
3 錠剤やカプセルの場合は舌中央部にのせて、薬が食道内に停滞しないよう水または微温湯100mL程度で服用してもらう。
4 口腔内に薬剤が残っていないか確認する。
この記事を読んでいる人におすすめ

第6回 「薬が飲みにくい」と言われたときの工夫
処方薬の多い現在、正しい服用のためには薬剤師、そして患者さんの最も近くにいる看護師の支援が必要になってきます。内服薬を中心に服薬支援のポイントを紹介します。 患者さんに「薬が飲みにくい」と言われたら 患者さんから薬が飲みにくいという訴えがあれば、飲みや

第8回 ナースが知っておきたい添付文書ナナメ読み(その1)
医薬品添付文書は医薬品情報の宝庫です。すべてに目を通すのは大変ですが、ポイントを押さえた添付文書の読み方をマスターすることで、薬を安全に、適正に使用する方法を確認しましょう。 与薬のプロセスごとに必要な情報を確認 医薬品に関する基本的情報が掲載されてい

第2回 投与方法と薬物血中濃度の関係
薬が体内でどのように作用し、どのように変化するのか、その基本を知ることで、患者さんの状態観察や服薬支援を効果的に行うことができます。まずは、薬の基礎知識のおさらいから始めましょう。 薬の効果を左右する「3つの領域」 「血中濃度」とは、ある成分が血液中に
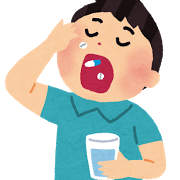
【高齢者への服薬指導】加齢がもたらす「6つの悪影響」
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下について解説します。今回は、「加齢がもたらす悪影響」です。 影響1 消化管の機能が低下する →内服薬(能動輸送)の吸収率低下 消化液の分泌、消化管の運動量・

第4回 服薬時間の理由と飲み忘れへの対応
処方薬の多い現在、正しい服用のためには薬剤師、そして患者さんの最も近くにいる看護師の支援が必要になってきます。内服薬を中心に服薬支援のポイントを紹介します。 用法(服用時間)を正しく理解してる? 薬の服用時間には、「食前」「食後」「寝る前」などさまざま