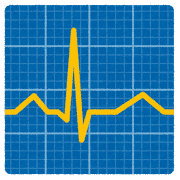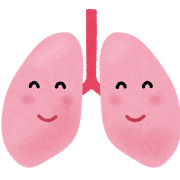食事介助の看護|観察項目・注意点・手順
食事介助の看護|観察項目・注意点・手順
- 公開日: 2020/4/23
【関連記事】
●図解】誤嚥を防ぐポジショニング
●ベッドアップ時に起きた下方へのずれを引き上げる!
看護師が食事介助を行う意義
私たちが食事を摂る意義は、栄養摂取だけではありません。好きなものを食べられる喜びが得られ、コミュニケーションを円滑にするための場でもあります。おいしい食事を楽しく食べたいという患者さんのニーズを理解し、個々の障害に応じた食事介助をすることが、看護師が食事介助をする意義だといえます。
自分で食事を摂ることができない状況は、配膳されている食事がわからない、自力で食事を口元まで運べない、姿勢保持が困難、嚥下障害のために誤嚥の危険性があるなど、さまざまな状況が考えられます。患者さんのニーズと障害の程度に合わせて、できるだけ自分で食事を摂れるよう食事介助することも求められます。
食事介助の目的
さまざまな障害によって自分の力で食事を摂取できない患者さんの障害の程度に応じて、必要な量を誤嚥せずに摂取できるようにします。また、食事を通して得られる楽しみや喜びも得られるようにします。
食事介助が必要な患者さんの例
・視覚障害のため食事内容がわからない
・脳卒中による麻痺があり姿勢の保持ができない
・治療や検査によりベッド上安静を強いられている、体力の低下のため座位が取れない
・脳卒中による嚥下障害、高齢による嚥下機能の低下がある
・脳卒中による麻痺や関節リウマチのため、箸やスプーンを握ることができない
食事介助の手順
1.患者さんの準備
①患者さんに手洗いを促します。
★POINT:手洗いに行けない場合は、おしぼりを配布します。
②誤嚥を防ぐために、頸部を前屈させ、足底をしっかり床につけた状態にして姿勢を保持します。

★POINT1:ベッド上で食事をする場合は、膝を軽く屈曲させ、膝下に枕やクッションを当てることで、安定した姿勢を維持します。

★POINT2:頭部に枕を当て頸部前屈位を保持し、誤嚥を予防します。

★POINT3:できる限り座位での食事介助が望ましいですが、上体が起こせない患者さんの場合、ファーラー位(半座位)で食事をすることもあります。座位と同様に、頸部が後屈しないように注意します。
③必要に応じて、うがいなどで口腔内を清潔にします。義歯の患者さんには、義歯の装着を促します。
④嚥下機能障害がある場合は、食事前に嚥下訓練(頸部、肩の運動、口唇の周りの運動、舌の運動)をします。
2.配膳
①テーブルの位置を調整します。
★POINT:患者さんが食事内容を見ることができて、食事を口元に運ぶために上肢を動かしやすい高さにします。
②配膳します。
★POINT1:視覚障害のある患者さんでは、トレーを時計の文字盤に見立てて食事を配置します。