 高血圧ゼロを目指す、循環器疾患予防の最新トレンド!―家庭と地域での取り組みー
高血圧ゼロを目指す、循環器疾患予防の最新トレンド!―家庭と地域での取り組みー
- 公開日: 2025/11/12
2025年10月1日、日本心臓財団主催のメディアワークショップ「高血圧ゼロを目指す、循環器疾患予防の最新トレンド」が開催されました。当日は、帝京大学医学部 衛生学公衆衛生学講座 教授の浅山敬先生より、家庭でできる循環器病予防(一次予防)について、東京脳卒中・心臓病等総合支援センター 副センター長の磯部光章先生より、地域ですすむ循環器病予防(二次予防)についての講演がありました。今回はその様子をレポートします。
家庭でできる循環器病予防 ―「血圧朝活」などデバイスを用いた血圧・不整脈管理診療
帝京大学医学部 衛生学公衆衛生学講座 教授/大学院医療データサイエンスプログラム
浅山 敬先生
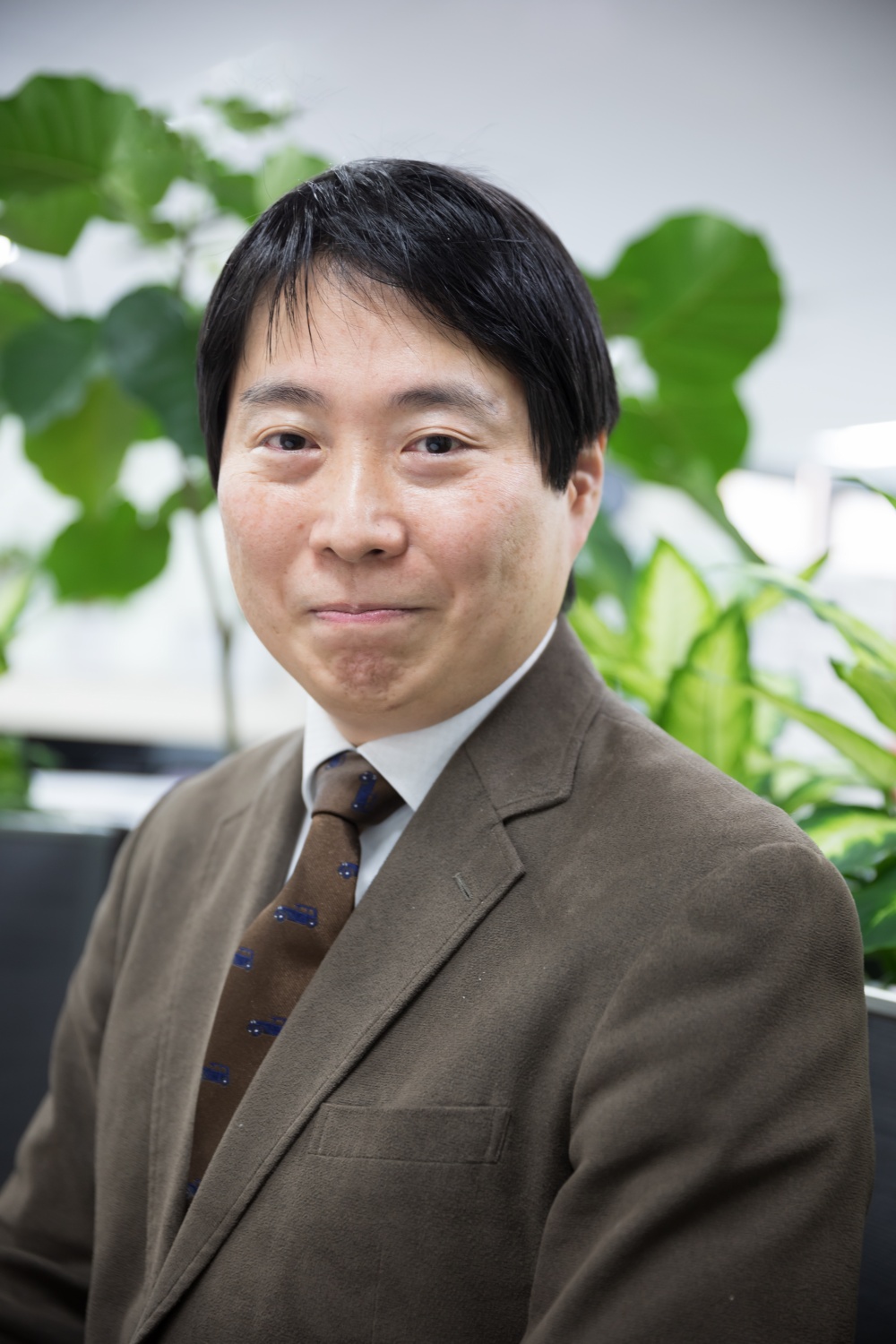
日本の健康課題と家庭血圧測定の重要性
日本は世界有数の長寿国である一方、「健康寿命」と「平均寿命」の間には男性で約10年、女性で約12年の差があります。この期間、人々は何らかの障害や疾患を抱えながら生活することになります。そのため、健康寿命をいかに延ばし、平均寿命との差を縮めることが今後の重要な課題のひとつであり、その解決には発症前の段階から生活習慣を見直す一次予防が不可欠です。
高血圧は、脳卒中や心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の主要なリスク要因であり、正しい血圧コントロールがこれらの予防に繋がります。一方で、国内の高血圧有病者は約4,300万人に上ると推定され、うち約半数が未治療です。また治療中であっても、半数以上の患者さんは血圧が十分に管理されていません。
このような現状は「ハイパーテンションパラドックス」と表現されており、この解消に向けた取り組みが進められています。こうした背景から、日常生活で簡単に取り入れられる「家庭血圧測定」の重要性が注目されています。
家庭血圧のメリットと臨床的意義
家庭血圧は、日常生活の安定した環境下で測定できるため再現性が高く、さらに朝晩の測定を継続することで長期的な血圧変動も把握できます。そのため、循環器リスクの評価や治療方針の決定に役立ちます。また、ドクターの前では血圧が高くなる白衣高血圧や、特定の条件下で血圧が上昇する仮面高血圧の評価にも有効です。
高血圧管理・治療ガイドライン2025では、診察室血圧と家庭血圧に乖離がある場合、家庭血圧を優先して診断や治療を決定することが推奨されています。具体的に、診察室血圧では140/90mmHg以上、家庭血圧では135/85mmHg以上が高血圧と定義され、正常血圧は診察室120/80mmHg未満、家庭115/75mmHg未満と設定されています1)。
家庭血圧の基準値はやや低めに設定されていますが、家庭血圧を適切に管理することで循環器リスクの低減に繋がると考えられています。また、家庭血圧を目安に薬剤調整をすることで、血圧コントロールが良好に保つこともできるなど、家庭血圧測定は、疾患予防や治療に重要な役割を果たします。
家庭血圧測定の方法と注意点
家庭血圧は正しく測定しなければ診断や治療の根拠にならないため、測定方法と注意点を守ることが重要です。家庭血圧測定の方法と主なポイントを以下にまとめました(表1)。
表1 家庭血圧測定の方法とポイント
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 測定方法 |
・原則1日2回(朝・晩)測定する ・1機会に原則2回測定し、その平均をとる ・できる限り長期間測定する |
|
| 測定機器 | 上腕カフ式(オシロメトリック法)の家庭血圧計を推奨 | |
| 測定タイミング | 朝 ・起床後1時間以内 ・排尿後 ・朝食・内服前 |
夕 ・就寝前 |
| 測定のポイント |
・静かで適温の室内で測定する ・半そで、または薄手のシャツで測定する ・測定前の喫煙・飲酒・カフェイン摂取は避ける ・測定前に1~2分安静にし、測定中は会話しない ・原則として背もたれのある椅子に座り、脚を組まない ・腕帯(カフ)を心臓の高さに維持し、ピッタリと巻く(斜め巻きもOK) ・肘を台などに置き、力を抜く ・測定値はすべて記録する |
|
家庭血圧を正しく活用するためには、適切な測定条件や環境の統一が欠かせません。例えば、室温が極端に低い・高い場合や騒音などは血圧値に影響するため、静かで適温の室内で測定することが大切です。
測定回数は朝・晩の2回、1機会に2回測定を原則とし、その平均をとります。良い値だけでなくすべての測定値を記録し、季節変動などを影響も把握できるよう、長期間にわたって測定記録を続けることも重要です。
なお、家庭血圧計は手首式では姿勢や測定位置の影響を受けやすいため、特別な場合を除いて上腕カフ式の自動血圧計(オシロメトリック法)が推奨されています。
キオスク血圧測定の活用
キオスク血圧測定とは、スポーツジムや薬局、自治体施設、健診・検診会場など、自宅外に設置されている自動血圧計を用いて、自分自身で血圧を測定する方法です。
医療機関にかかっていなくても、自分の血圧を知る機会となり、高血圧のスクリーニング(早期発見)としての意義があります。また薬局で測った場合、薬剤師が医師へフィードバックできるなどのメリットもあります。
一方で、血圧測定機器の設置環境や測定方法が標準化されていないのが課題です。そのため、医療従事者がキオスク血圧測定値を評価する際は、測定時刻、服薬状況、場所を記録し、必要に応じて家庭血圧や医療機関での再測定を促すことが大切です。
今後の血圧測定と普及に向けた取り組み
現在の血圧管理の分野では、さまざまな新技術が開発されています。例えば、腕帯(カフ)を使わず脈波や血流量から血圧を推測するカフレス血圧計、アプリなどのデジタル技術を活用し、治療支援や患者さんとのコミュニケーションを図るプログラム医療機器など、先端技術を高血圧の管理や治療に取り入れる試みが行われています。しかし、臨床的な精度や標準化の面で課題が多く、医療現場での本格的な導入にはまだ至っていません。
一方で、血圧測定は循環器病予防の第一歩として重要です。日本高血圧学会では「血圧朝活キャンペーン」を展開し、朝の血圧測定を習慣化することで、予防意識の向上を図っています。また、地方自治体では、独居老人や孤立世帯等を対象に、遠隔家庭血圧管理を用いた見守り事業を行っているところもあるなど、血圧測定の普及と高血圧の早期発見・一次予防に繋げるさまざまな取り組みが進められています。
これからの心臓病の患者支援 ―脳卒中・心臓病等総合支援センターの活動
東京 脳卒中・心臓病等総合支援センター 副センター長
榊原記念病院 院長
日本心臓財団 常任理事
磯部 光章先生
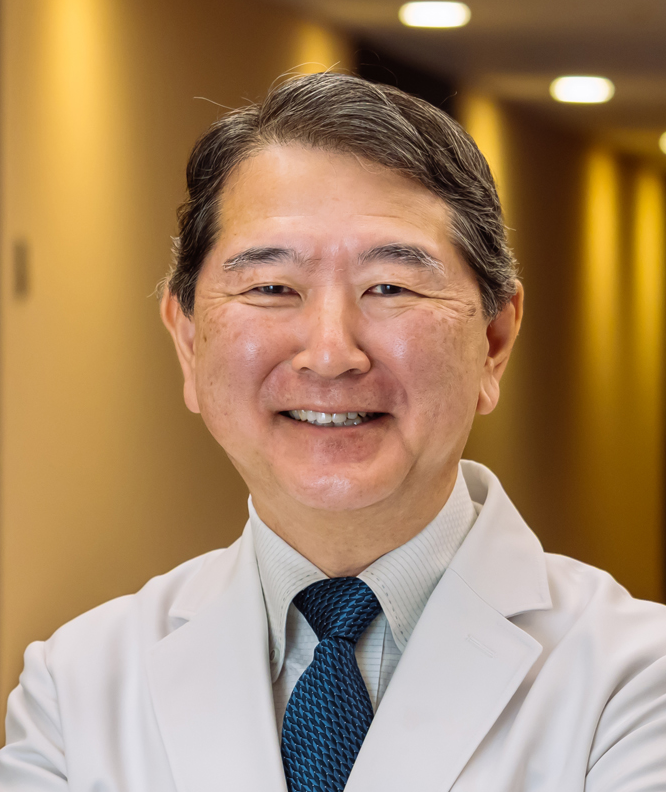
日本における循環器疾患の現状
日本の死亡率を主要死因別でみると、同じ循環器疾患でも、1960年代まで1位を占めていた脳卒中は近年減少傾向にある一方、心疾患は増加傾向にあります。また、東京都の令和元年の主要死因は、心疾患が悪性新生物に次いで第2位となっています2)。
また、脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患は、介護が必要となる主要な原因でもあり、平均寿命と健康寿命の差にも影響しています。さらに、循環器疾患の治療には多くの医療資源が費やされており、高齢化に伴う治療の長期化が医療経済にも大きな負担をもたらしています。
循環器疾患(心不全)の理解と包括的な予防・管理
循環器疾患のうち、心不全は虚血性心疾患や弁膜症などあらゆる心疾患の最終段階で現れる病態です。進行段階に応じた一次予防や二次予防の取り組みが重要であり、心臓機能だけでなく、高齢者の認知機能や併存疾患、生活背景も考慮した包括的な医療が求められます。
心不全のステージ分類と一次予防・二次予防
心不全には、器質的心疾患のないリスクステージのAから難治性・末期心不全のステージDまでの4段階があります。
高血圧などの危険因子のみのステージAや、器質的心疾患がありながらも心不全の症候がないステージBは、一般的に心不全と捉えられていません。しかし、自覚症状がなくても心不全は進行するため、一次予防として高血圧や糖尿病などの危険因子をコントロールし発症を防ぐことが重要です。症状があるステージC・Dでは、二次予防として増悪防止やQOLの向上を目指した対応が求められます。
包括的な治療の新たな視点
心不全をはじめとする循環器疾患は高齢者に多くみられ、認知機能の低下や併存疾患を抱えていることが少なくありません。また、フレイルや社会的背景も病態や治療に影響を及ぼします。
そのため、近年では心機能の改善だけでなく、患者さんがその人らしく生活できるように支える医療が重視されるようになっています。その実現には、医療・介護を越えた多職種連携や地域連携、早期リハビリの介入、セルフケアの充実などが必要です。
また、患者さんの意思を尊重した治療計画(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)を取り入れ、個々にあった医療の提供が求められます。
循環器医療を支える「脳卒中・心臓病等総合支援センター」
脳卒中・心臓病等総合支援センターは、2018年に制定された健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法に基づき策定された、厚生労働省の循環器病対策推進基本計画に沿って、各都道府県に設置された施設です(東京都に3施設、そのほかの道府県に各1~2施設)。
支援センターの目的と役割
患者さんと家族を包括的に支援することを目的とし、検診、救急、リハビリ、緩和ケア、就労・両立支援など、循環器疾患の予防から治療、社会復帰までの切れ目ない支援を提供します。さらに、循環器疾患に関する知識の普及啓発や研究推進も重要な役割のひとつです。
また、地域医療機関やかかりつけ医、多職種との連携の中心的役割も担い、医療・介護・福祉が一体となって、循環器疾患の理解促進と再発予防に取り組みます。
支援センターの現状と具体的な取り組み
東京都では、榊原記念病院・武蔵野赤十字病院・日本医科大学付属病院の3施設が共同で東京脳卒中・心臓病等総合支援センターを運営し、行政と協働しながら活動を展開しています。
現状では、改善の余地がある分野もあり、これらの課題に対応するため、支援センターでは以下のような多面的な取り組みを進めています。
地域連携
支援センターでは、地域医療機関との連携強化と地域全体の支援体制向上を目指し、都内の病院を対象に「東京心臓病連絡協議会」を設置しました。現在20病院が参加しており、今後も活動を拡大し、地域連携の強化を図ります。
また、オンラインを活用した多職種(医師・看護師・訪問看護師・管理栄養士など)による退院支援カンファレンスの開催や、在宅医療機関へのポータブル心エコー貸与と研修、病院医師との情報共有、外来での心臓リハビリテーションの新たな導入施設の増加を目的とした研修会の実施など、地域連携を基盤とした支援を推進しています。
相談支援
支援センターの3病院はそれぞれに相談窓口を設置し、病状や生活に関する相談を受け付けています。
榊原記念病院では、外来看護師が初期対応を担い、必要に応じて医師・ソーシャルワーカー・臨床心理士へ連携するワークフローを確立しています。年間約1万件(1,000件超/月)におよぶ相談のうち、半数が病状に関する内容です。これにより、早期受診や業務改善に役立っており、約7%では緊急対応が必要と判断され早期受診につながっただけでなく、緊急性の低い救急受診が大きく減少しました。
両立支援
心血管疾患は、外見からはわかりにくいですが完治が難しいため、就労世代の心筋梗塞・心不全患者さんは、治療と就労(学業)の両立が大きな課題です。
榊原記念病院では、支援スタッフ・患者さんと家族・会社の上司・人事・病院スタッフ(ソーシャルワーカー、リハビリスタッフ)が参加するカンファレンスを開催し、心機能や運動耐容能の評価に基づいて、患者さんに合った働き方を提案するなど、個別性の高いサポートを実施しています。その結果、年間500件以上の両立支援のうち、約9割が復職・再就職を達成しています。
啓発活動
東京の支援センターでは、都民への啓発活動として、小中学生とその保護者を対象に「親子心臓教室」を開催し、心臓の仕組みや働きの学習、病院での診療の体験を通じて心疾患の理解と予防意識を高めています。
また、成人先天性心疾患(ACHD)患者さん向けのピアサロン(交流会)や、心疾患患者さん向けのお料理教室、運動教室、薬教室などを開催し、情報の共有や日常生活での栄養管理・運動・薬剤の正しい使い方を学べる機会を提供しています。
循環器病予防における地域・社会連携の重要性
心疾患を含む循環器疾患は、患者さんの生活や就労、介護などに影響を及ぼすだけでなく、日本人の健康寿命や医療経済にも関わる社会的な課題です。
今後は、医療従事者だけでなく、地域や社会全体で患者さんの生活を中心に据えた支援体制を構築する必要があります。一次予防から二次予防、在宅ケア、ACPを取り入れた包括的な支援まで、地域全体で連携して切れ目のない支援を進めることが重要です。
引用・参考文献
1)日本高血圧学会高血圧管理・治療ガイドライン委員会,編:第5章 血圧測定と臨床評価.高血圧管理・治療ガイドライン2025.ライフサイエンス出版,2025,p.45-7.2)東京都保健医療局:第3節死亡統計 第20表 死亡数・率、年次・主要死因(死因簡単分類) 人口動態統計.(2025年10月31日閲覧)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/r01pdf-3-pdf
・厚生労働省:令和5年簡易生命表の概況.(2025年10月14日閲覧)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/index.html
・日本高血圧学会高血圧管理・治療ガイドライン委員会,編:高血圧管理・治療ガイドライン2025.ライフサイエンス出版,2025
・厚生労働省:人口動態調査.(2025年10月14日閲覧)https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html
・厚生労働省:国民生活基礎調査.(2025年10月14日閲覧)https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21kekka.html








