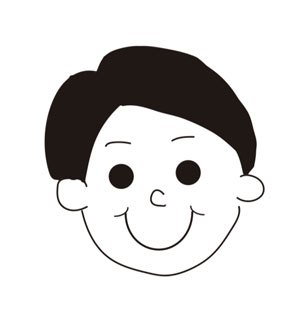抗菌薬に関連した薬剤耐性(AMR)について知ろう
抗菌薬に関連した薬剤耐性(AMR)について知ろう
- 公開日: 2025/11/6
抗菌薬の使用や薬剤耐性(AMR)についての現状や医療従事者の認識などを国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター 情報教育支援室長の藤友結実子先生と特任研究員の佐々木秀悟先生が解説するメディア向けラウンドテーブルが開催されました。ここでは、その模様をレポートします。
AMRとは/AMRの現状と課題
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター 情報教育支援室長 藤友結実子 先生
風邪に抗菌薬処方は適切?
日常診療の際に、患者さんから「抗菌薬をください」と言われることがあります。抗菌薬を飲んだ後に風邪が治ると、患者さんは抗菌薬が効いたと思います。すると、次に風邪になったときも、前回効いたので、抗菌薬を処方してくださいという発言につながります。
そもそも、風邪の原因となるのは、さまざまなウィルスです。病原微生物は、ウィルス、細菌、その他に分けられます。抗菌薬が効くのは細菌だけであり、ウイルスには効きません。抗菌薬は細菌の細胞壁合成やたんぱく質合成、核酸合成を阻害するといった、細菌の仕組みに働きかけるものです。ウイルスが原因になっている疾患の場合、抗菌薬を飲んでも働いてほしいウイルスには効かないばかりか、耐性菌を保菌する可能性につながります。
抗菌薬自体が悪なのではなく、使わなければ命にかかわることもあります。つまり、必要なときにはしっかりと使い、不適切な使用はやめるというのが、抗菌薬使用の大切なポイントなのです。ちなみに、抗菌薬のうち、細菌や真菌などの生物から作られるものを抗生物質と呼びます。抗菌薬・抗生物質、抗生剤はほぼ同じと考えてもらってかまいません。
一般の知識と医師の対応
一般の方を対象にした調査では、4割ほどの方がインフルエンザや風邪には抗菌薬が有効だと思っていることがわかりました(図1)。また、風邪の症状で受診したときに抗菌薬が処方されていると思っている方は半数いました(図2)。医師が実際に抗菌薬を処方している割合は2割ほどなので、一般の患者さんが抗菌薬自体を誤解している可能性があると考えています。
図1 抗菌薬・抗生物質が有効な病気としてあてはまると思うものをすべてお応えください。(複数回答、n=727)

図2 かぜ症状で受診した際に処方された薬の中に抗菌薬が含まれていると思うか(n=400)

医師へのアンケートでは、風邪と診断した際に患者さんから抗菌薬の処方を希望された場合、2018年には32.9%、2022年には39.2%が「説明して処方しない」と回答しています。しかしながら、「説明しても納得しなければ処方」「希望通り処方する」と回答している医師が6割ほどいます。患者さんの気持ちに立って考えると、抗菌薬がほしいと思って受診しているのに、この症状には効きませんと言われて素直に帰るわけにはいかないのかもしれません。そこを医療従事者が意識し、しっかりと説明して患者さんに納得していただくことが大切だと思っています。
AMRの今後の課題と取り組み
2023年に策定された「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)」では、計画全体を通した成果指標を設定しています。これらの数値は、これまでの数値を踏まえて具体的に設定しており、決して厳しい目標とはなっていません。また、耐性率を調べる検体を絞って数値を見ていくこととしています。
AMRの問題は世界中で注目されており、2024年9月に行われた国連総会ハイレベル会合で、取り上げられた3つの議題のうちの1つがAMRについてでした。また、2025年の2月にも東京AMR会議があり、アジアの国々が集まって各国での取り組みや問題を話し合いました。AMRはヒトだけの問題ではありません。抗菌薬は、畜産や水産、農業、ペットなど幅広い分野で使われているため、すべての関係機関で対策に取り組んでいく必要があるのです。
一方で、新規抗菌薬の開発はなかなか進んでいません。新しい抗菌薬を作っても次の耐性菌のために残しておきたいため、どんどん使うわけにはいかない、開発は進めなければいけないのに投資しても、その費用をすぐに回収できないという課題があります。そこで、プル型インセンティブという仕組みを利用し、継続的な研究開発を進めていこうとする取り組みが日本でも少しずつ始まっています。
また、抗菌薬に限らず、薬剤の安定供給ができなくなっていると言われており、薬剤が確保できなければ適正使用を進めることが難しくなってしまいます。厚生労働省が医療用医薬品供給状況を毎週更新していますが、どの地域でどの薬剤が足りないのかはわからない状況です。これはまだまだ解決していかなければいけない問題だと感じています。
薬剤耐性対策の基本は、抗菌薬の適正使用を進めること、そして感染対策を十分に行うことです。感染しなければ病院に行く必要がなく、抗菌薬が処方される機会も減ります。感染対策をしっかりと行い、自分自身が感染症にかかわる場面を減らすことがとても重要なのです。
知っておきたいWHOのAWaRe(アウェア)分類
WHOが定めた医療に必須の医薬品のうち、薬剤耐性の影響を考慮して抗菌薬の適正使用を推進するためのツールが「AWaRe(アウェア)分類」です。第1選択薬・第2選択薬となる抗菌薬を「Access」、耐性化した際に取りうるほかの選択肢が少ないため限られた疾患や適応にのみ使用が求められる「Watch」、最後の手段として使用する「Reserve」の3つに分けられています。WHOではAccessの割合を全体の60%以上、国連総会のハイレベル会合では7割以上にすることが目標になっています。日本はAccessの使用割合が他国に比べると低く、データ上の76カ国の中で最小になっています。これは、日本が広域の抗菌薬を使う傾向にあるからだと考えられます。
AMR臨床リファレンスセンターメディア向けラウンドテーブル
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター 特任研究員 佐々木秀悟 先生
看護師におけるAMRに関する課題
病院に勤務する看護師を対象に行った調査では、抗菌薬がウイルスに効果があると思っている、風邪やインフルエンザに効くと思っている人が3割ほどで、約7割の人は効かないと認識していることがわかりました。一般の方に比べ知識はあるとはいえ、まだ改善の余地がありそうです。
また、実際の業務の中で患者さんに抗菌薬が処方されたとき、あまり理由を把握できていないという人が4割ほどいました。医師や薬剤師に投与理由や投与量などを確認している人は半数ほどであり、コミュニケーションが不十分だと言えます。
さらに、患者さんやその家族から抗菌薬の使用について質問されても、適切に説明ができない、自信がないという方は約4割で、「抗菌薬の適正使用について教育を受けたいと思うか」という質問にたいしては、約9割の方が「はい」と答えています。今後、啓発活動をしていかなければならない点だとも感じています。
歯科で処方される抗菌薬
歯科では、抜歯などの処置の際に感染を予防する目的で抗菌薬が使用されることがあります。口の中にも薬剤耐性菌が増えていること、不適切な抗菌薬の使用が行われていることが課題です。
虫歯や歯周病などによって起こる感染を「歯性感染症」と言います。起炎菌となるのは口腔内レンサ球菌や嫌気性菌であり、好気性菌と嫌気性菌の複数の菌による感染が起こることが特徴です。また、抗菌薬は血液に乗って身体の中を運ばれますが、口の奥に溜まっている膿の周りには血管がないため抗菌薬が移行しにくく、治りが遅くなってしまいます。特にプレボテラという菌には効きにくく、消炎処置が必要になることもあります。
一般的に歯科で抗菌薬を使う場面は限られているので、全体の使用量は医科の10%ほどと少なくなっています。その中でも使用している薬剤の種類を見てみると、ペニシリン系は医科が29.2%あるのに対し、歯科での使用割合は5.5%です。一方で、第3世代セフェムであるセファロスポリン系の抗菌薬は、医科で23.1%、歯科で65.1%であり、よく使われていることがわかります。セファロスポリン系抗菌薬は広域に効く抗菌薬ですが、歯周病患者さんにおける抗菌薬適正使用のガイドライン2020で推奨されている第1選択の薬はペニシリン系です。ペニシリンアレルギーがある場合にはクリンダマイシンが挙げられ、第3世代セフェム系の薬は推奨されていないのが実際のところです。
表1 第3世代セフェムが推奨されない理由
| 歯科の起炎菌は、口腔レンサ球菌および嫌気性菌であり、第3世代セフェムがよく効くとは言い難い |
| グラム陰性菌までカバーする広域抗菌薬(第3世代セフェムもこれに含まれる)は不要 |
| 吸収率が低い薬剤は使用しない(第3世代セフェムは吸収率が低いものが多い) |
薬剤耐性菌を増やさないためには、抗菌薬を使い過ぎない、必要以上に長く使わないことが歯科に限らず重要です。加えて、守備範囲が狭い薬剤、必要な菌だけを標的としている抗菌薬を選ぶことが原則であり、歯科においては第3世代セフェム系の薬剤は避けるべきだと言えます。
薬剤耐性と急性中耳炎
子どもは大人に比べて耳管が太く・短く・水平に近いため急性中耳炎になりやすく、就学前に3・4回かかることもあると言われています。
急性中耳炎は本来、自然治癒する疾患です。抗菌薬が必要になるのは原則として重症例のみで、軽症であれば抗菌薬を使用せず、経過観察が推奨されています。しかし、抗菌薬を使えば早く治るのではないかと処方を希望される方が多いのが実情です。抗菌薬を使えば薬剤耐性菌を増やすリスクにつながるので、必要以上に使用しないことが重要です。
ニキビ治療と抗菌薬使用
ニキビの治療はここ10年ほどで大きく変わってきました。そもそも、面皰と呼ばれる毛穴の詰まりがニキビの始まりです。ここにアクネ菌が増えてくると、炎症を起こしたり腫れたりします。元々は抗菌薬しか選択肢がなかったために、炎症が起きてから治療することしかできませんでしたが、アダパレンや過酸化ベンゾイルなどの新たな外用薬が登場したことで毛穴の詰まりを取り除く治療が可能になりました。
ニキビの原因になるアクネ菌の抗菌薬耐性菌が増えてきています。クリンダマイシンやクラリスロマイシンの抗菌薬に対し、多い年で5、6割の耐性が見られるような状況です。
これらの対策として、ニキビ治療を症状がひどい「急性炎症期」とそれ以外の「維持期」に分け、抗菌薬を使用するのは「急性炎症期のみ」「中等症以上」「3カ月を上限」にすると日本皮膚科学会 尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023に示されています。ニキビだけでなく他の皮膚常在菌や皮膚科領域以外の感染症にも影響するため、抗菌薬を適切に使用することが推奨されています。
抗菌薬点眼と結膜炎
結膜炎とひと口に言っても、花粉症に代表されるアレルギー性のもの、アデノウイルスなどが原因になるウイルス性のもの、細菌性のものがあり、アレルギー性とウイルス性の結膜炎に抗菌薬は必要ありません。基本的に充血や眼脂だけでは抗菌薬の点眼を投与してはならないと言われています。
抗菌薬を点滴や内服で使用したとき、血中濃度は10μg/mLほどです。しかし、点眼の場合は3,000~15,000μg/mLほど。目のまわりに大きな影響を与えていると言えます。
また、抗菌薬点眼の販売量を見ると、全体の9割以上がキノロン系です。内服に比べると点眼の種類は限られているために偏りが出てしまうという面もありますが、キノロン系は「AWaRe分類」でWatchに分類されるため、慎重に使うべきなのです。
しかし、慢性結膜炎でキノロン点眼を長期使用している人が多く、この疾患は、高齢者や乳幼児によく見られます。そして、結膜炎を起こすコリネバクテリウムは高度のキノロン耐性があり、キノロン系の抗菌薬が効かなくなっています。長期でキノロン点眼を使用していると、MRSAが検出されやすいとも言われています。つまり、対象とした菌は耐性化し、別の耐性菌が増えてしまうという悪循環を生んでいるのです。
これらの問題を解決するためには、やはり抗菌薬は必要なときだけ使用すること、推奨されていない抗菌薬の使用は減らしていくことが重要です。