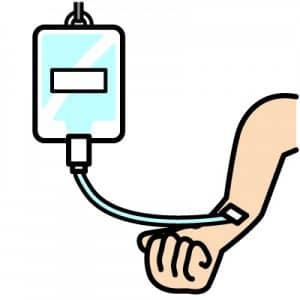 第6回 輸液剤の使い分け
第6回 輸液剤の使い分け
- 公開日: 2009/7/29
輸液剤の使い分け
今回のタイトルは『輸液剤の使い分け』としました。
しかし、『これって、ナースにとってそれほど必要な知識なの?』と思われる方もおられるのではないでしょうか。 確かに、輸液を処方するのはドクターです。ナースではありません。 だから・・・?
しかし、輸液を輸液ラインに接続して投与するのは、ほとんどの場合、ナースです。そうなんです。 実際に輸液を投与するのはナースなのです。 それなのに、輸液剤についての知識がないということは、かなり危険です。 輸液の中身を知らずに投与するって、医療のプロとしてはかなり寂しいと思いませんか?
輸液剤の分類
輸液剤の使い分けは、本当はむずかしいのですが、高度に電解質バランスがくずれている場合や腎機能に異常がある場合以外は、体が自然に調節してくれますので、それほど厳密に考えなくても大きな問題は起こりません。 とにかく、体液の電解質濃度を健常域内に保つために輸液は行われます。 ということは、体液の電解質濃度を知っておく必要があることは言うまでもありません。

輸液剤は、電解質輸液剤、栄養輸液剤、血漿増量剤に大きく分類することができます。

電解質輸液剤は血漿の浸透圧との関連で等張性と低張性に分けられることを覚えてください。
しかし、血漿の浸透圧はいったいどのくらいなのか、ご存知ですか?







