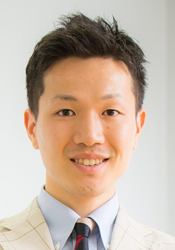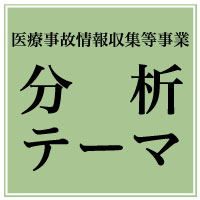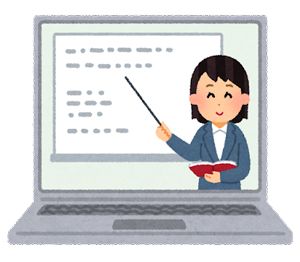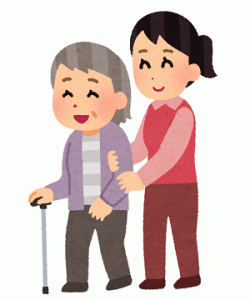 看護師による外出支援へ高まるニーズ
看護師による外出支援へ高まるニーズ
- 公開日: 2021/5/5
医療従事者による外出支援が求められる背景
病院や施設に加え、居宅でのケアが発展し、地域で療養する基盤が徐々に整ってきました。しかし、生命を維持することのみが人生の目的ではありません。病や障害があっても、施設や自宅を飛び出して、その人らしく自由に、好きな場所で好きなことができる環境を整えることも大切です。
とはいえ現実には、病や障害によって外出できない交通弱者と呼ばれる人たちが多く存在します。また、核家族化や独居により身内のサポートが得られにくいケースが少なくないほか、新型コロナウイルス感染症の収束も見通せず、都市部に至っては東京オリンピック・パラリンピックの影響で混雑も予想されるなど、交通弱者の外出は今まで以上に難しくなる可能性があります。
外出支援の現状
医療従事者による公的または自費の移動支援サービスは、これまでも存在していました。ただ、「急変対応が怖いという理由でヘルパーに断られた」「外出中に吸引や経管栄養、インスリン注射などをお願いしたい」「同行援護や介護保険の公的支援は、通勤や趣味を目的とした外出には使えない」「ボランティアでは事故のリスクが大きい」「自費の移動支援サービスは高い」といった声が利用者さんやスタッフからよく聞かれます。
従来の移動支援では、外出目的、依頼内容、利用者さんの状態によって支援を受けられないケースや金銭面においても制限があり、真に自由とはいえないのが現状です。
このような状況を受けて、最近では、一般的な自費の移動支援サービスよりも安価で、かつ目的に関係なく利用可能なサービスが登場してきています。
また、外出時にケアが必要な人と外出支援をする医療従事者をつなぐウェブアプリで、顔なじみの看護師や介護士などへ依頼することができたり、利用者さんがスマートフォンを操作できない場合は家族や友人が代わりに申し込めるなど、気軽に安心して使ってもらえるよう工夫されているものもあります(図1)。
図1 ケアプロ株式会社が運営する外出支援アプリ「ドコケア」の場合

看護師が外出支援を行う意義とメリット
医療と生活の両面を全人的にみることができる看護師が付き添うことで、外出に対する心理的・身体的サポートができます。
また、「看護師が付き添ってくれれば安心して外出できる」「自費のため、外出の種類や目的を制限されない」などの価値提供や、家族の介護負担の軽減につなげられる点も、看護師が外出支援を行う意義といえます。
介助者となる看護師側にもメリットがあります。看護師の資格や個人の強みを活かせるのはもちろん、家事や育児の合間のすきま時間を有効に活用することができます。なにより、利用者さんの願いを自分の力で叶えることに大きなやりがいを得られます。
事例紹介
ALSのOさんが外出支援を利用したケースを紹介します。Oさんは学生の頃、農業をしながら大学の農学部へ通っていました。Oさんは以前から、大学時代の友人が経営している農場を見に行きたいと思っていたものの、なかなか自分たちで行く機会がもてなかったそうです。
そうしたなか、看護師同行のうえ、行きたい所に行ける外出支援サービスがあると知り、顔なじみの訪問看護師の付き添いのもと、友人と久しぶりに再会するために数年ぶりの遠出をすることにしました。
当日は外出前に健康状態を確認し、介護タクシーに乗って目的地まで移動しました。OさんはALSで筋肉が動かせなくなってきているため、車中でも枕のポジショニングなどを看護師が実施し、2時間かけてOさんの友人が経営する農場に行きました。20年ぶりの再会に話は尽きず、楽しい時間はあっという間に過ぎていきました(図2)。
図2 友人と久しぶりの再会したOさん(前列中央)
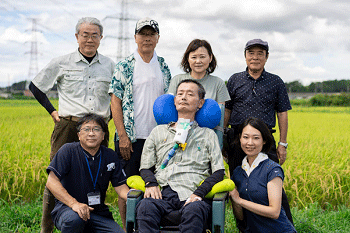
帰宅後は、「次は何月に田んぼに行こうか?」「久しぶりに温泉旅行もいいかもね」と、次の外出について目をキラキラさせて話すOさんの姿が印象的でした。また、介助者である看護師も、「皆さんが安心して外出できるように、事前の準備など大変な部分はありましたが、無事にお友達にも会えて、Oさんの喜ぶ顔を見ることができたのでよかったです」と笑顔で話してくれました。
このように、たった1回の外出が、利用者さんだけでなく、家族や介助者である看護師の自信にもつながっていることがうかがえます。今後も医療従事者による外出支援を通して、一人でも多くの人に出かける喜びを経験してもらえればと思っています。