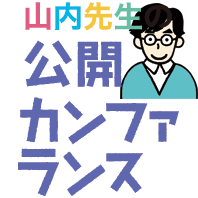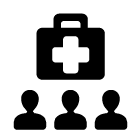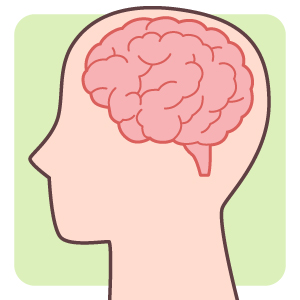第8回 麻痺・拘縮はなぜ起きる?
第8回 麻痺・拘縮はなぜ起きる?
- 公開日: 2012/10/29
麻痺・拘縮は、ほかの廃用症候群等を招く要因にもなることから予防に努め、ADLを維持・向上させる支援が大切です。最初に、なぜ起こるのかを解説していきます。
どんな症状?
麻痺の症状と種類
脳・神経系に何らかの障害が生じ、随意運動ができなくなる状態が麻痺です。
運動神経に障害が生じた場合は運動麻痺、知覚神経に障害が起これば知覚麻痺となります。
しかし、一般的に麻痺といった場合には、筋収縮の低下による運動麻痺を指します。
運動麻痺には、次のような種類があります。
1. 失調性麻痺
平衡障害、協同運動障害によりバランスを崩しやすく、身体の姿勢保持が難しくなります。
2. 弛緩性麻痺
筋緊張や腱反射が低下あるいは消失してしまった状態で、身体の姿勢保持が難しくなります。
3. 痙性麻痺
筋緊張と腱反射が異常に亢進した状態で、弛緩性麻痺の後に多く出現します。
動作時に筋緊張が高まり、意に反した動きになったり、異常な姿勢になったりします。
参考になった
-
参考にならなかった
-