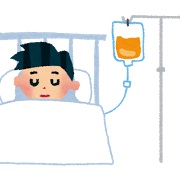【連載】看護学原論に立ち戻って考える!KOMIケアで学ぶ看護の観察と看護記録
 第3回 看護にとって「病気」とは?―看護のものさし②⽣命体に害となる条件・状況を作らない援助(1)
第3回 看護にとって「病気」とは?―看護のものさし②⽣命体に害となる条件・状況を作らない援助(1)
- 公開日: 2015/9/15
そもそも「看護」って何だろう?何をすれば看護といえるのだろう?本連載では、看護とはどのようなことであり、どのような視点で患者を観察し、また記録するのかについて、ナイチンゲールに学びながら解説します。
本連載の第2回で、「病気は回復過程の表れ」というナイチンゲールの指摘から、本来の看護とは「身体内部の回復システムが働きやすいように、最良の状態=ベスト・コンディションを創ること」というお話をしました。
では、具体的にそれはどんな状態のことを指すでしょう。
⽣命体に害となる条件
ナイチンゲールが“病気”と呼んでいる「回復過程」は、看護という援助行為が適切に行われないと順調に進まなかったり、中断したりしてしまいます。 それが生命体にとって害になります。
その結果、患者さんは病気そのものがもたらす苦痛以上に「不適切な看護や看護不足がもたらす苦痛をこうむる」ことになり、そのために回復が遅れたり回復しなかったりするのです。
ここから看護は「自然の回復過程を助ける」ように、その援助の方向性を定めなければならないという原理が出てきます。
具体的な方法としては、病室の空気を新鮮に保つ、室温を適切に保つ、食事を適切に選んで提供するなどであり、看護は患者の「日常生活のあり方」を整えることを通して実現されるということです。
このテーマを理解するためには「人間が病気になった時に、いちばん辛いことは何か?」と、患者さんの立場で考えることが重要でしょう。