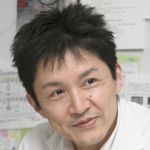第29回 乳がんホルモン療法の副作用発現に関する患者と医療者のギャップ
第29回 乳がんホルモン療法の副作用発現に関する患者と医療者のギャップ
- 公開日: 2016/3/3
- 更新日: 2021/1/6
医療者が患者の治療・ケアを行ううえで、患者の考えを理解することは不可欠です。しかし、看護の現場では、複数の患者への治療や処置が決められた時間に適切に実施されなければならないことが日常的です。また、心身が辛い中で療養している患者は、忙しそうに働いている看護師に対して、自分から治療や生活上の悩みや困難を訴えるのも勇気のいることでしょう。
そこで、患者の病いの語りをデータベースとして提供しているDIPEx-Japanのウェブサイトから、普段はなかなか耳にすることができない患者の気持ち・思い・考えを紹介しながら、よりよい看護のあり方について、読者の皆さんとともに考えてみたいと思います。
「化学療法に比べてホルモン療法の副作用は発生率も低く、重症度も低い」―多くの医療者がこのような認識を抱いていると思います。しかしながら、命に別状はなくとも、エストロゲンの減少に起因する更年期様症状で生活の質が著しく損なわれてしまう患者は少なくありません。
どんな体調変化でも、患者が気軽に話しやすい雰囲気作りを
43歳で乳がんの診断を受けた女性(インタビュー時50歳)
こちらからご覧ください
あとのホルモン療法のほうですけども、これはもう本当になんか激しくって。まだ(年齢的には)更年期、更年期障害になってないんですけども、まあいわゆるこれが更年期障害と言われるものに近いもんだなと思ったのは、汗が異常に出てくるんですね。
もともと汗っかきなんですけども、私の中での一番いい例えは、プールから上がった状態っていうのが(笑)、まさにもう、本当にもう額からもうザーッと流れ落ちる、滝のように流れ落ちるという、まさにそんな感じなんですけども、それが激しくて、ホットフラッシュ状態。
「NPO法人 健康と病いの語り ディペックス・ジャパン > 乳がんの語り」より
42歳で乳がんの診断を受けた女性(インタビュー時47歳)
こちらからご覧ください

しんどかったですね、そのホルモン剤に替えてからは。書いてある通りの動悸がしたりとか、ホットフラッシュっていうんですかね。汗が出たりとか、むくみが出たりとか。あとすごく太り出して、何が嫌だったって12キロぐらい太ってしまって。(中略)
いわゆる更年期障害の症状ということで、イライラが出たりするっていうのがあって。イライラしてるときに、「あ、これー、もしかして副作用?」ぐらいの余裕のあるイライラだったからよかったんで、自分を抑えられないほどでもなかったですけど。
何か、症状というには不快なんだけど決め手がないような症状が続くっていう、随分しんどかった覚えがあります。
「NPO法人 健康と病いの語り ディペックス・ジャパン > 乳がんの語り」より
ホルモン療法による更年期様の副作用には、ホットフラッシュや頭痛、イライラ感、気分の落ち込み、不眠、関節痛、骨粗鬆症、体重増加などがみられます。
滝のように流れ落ちる汗であれば異変と気づきますが、この女性が話しているように、症状と言うには不快だけれど決め手がないために、自分の身体の変調を医療者に話しづらいと感じる人もいます。
東京理科大学で行ったパイロット調査1)では、ホルモン療法実施患者(n=148)が副作用と感じた体調変化が平均62%、副作用と判断のつかない体調変化は57%、副作用は経験しなかったと答えた人が20%いました。
医師(乳腺科医師,n=25)が把握する副作用の発現率は37%、薬局薬剤師(n=205)の場合には31%。ちなみにDRUGDEXというデータベースによると、タモキシフェンののぼせ・ほてりの発現率は用量にもよりますが、41〜80%でした。
副作用発現率に関する認識のギャップはどこから生まれるのでしょうか。前述した副作用自体が加齢やストレス等に伴う体調変化なのか、副作用なのかの区別が付きづらいことや、副作用よりもがんの再発防止を優先して患者自身が体調変化を医療者に話さないこともその一因でしょう。
そしてもう一つの要因が、添付文書やインタビューフォームの報告にありそうです。最も訴えの多かったのぼせ・ほてりに関しては、ノルバデックス錠の添付文書には0.1〜5%の発現率と記載されています。
こうしたデータが、ホルモン療法の副作用発生率は低いという医療者のイメージ形成に影響をもたらし、副作用の聴き取りを十分にしていない可能性が考えられます。
データから先入観を持つことなく、くすりにはリスクがつきものだということを忘れずに、まずは解釈や分析を加えることなく患者の訴えに耳を傾けましょう。
そして、不快な症状を持ちながらどうやって生活したらよいか看護師として助言や、緩和の方法についても相談に乗ってあげましょう。
引用文献
1)土田隼之祐 平成26年度東京理科大学薬学総合研究論文要旨集