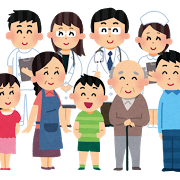精神科病棟における下剤に頼りすぎない排便コントロールの試み【PR】
精神科病棟における下剤に頼りすぎない排便コントロールの試み【PR】
- 公開日: 2018/7/9
目的
小曽根病院は557病床を有する精神科病院です。新館4階病棟は、精神科一般病棟で、患者数は55名。平均年齢は70歳代と高齢化が進み、長期臥床の人が約半数を占めています。
精神科病棟では、抗精神病薬の副作用や長期臥床での運動量の低下などによる便秘が切実な問題で、便秘が原因のイレウスを発症する患者もいます。下剤による排便コントロールが必須と考えられ、これに伴う下痢症状は仕方のないこととされてきました。そのため、多くの場合日常的に緩下剤が使用され、本来頓用である刺激性下剤が継続的に使用されることも少なくありません。本院においても、各種下剤の使用量は多く、下痢状態が継続している患者が散見されました。それらの患者は、水様便によって寝具や寝衣が汚染され、皮膚トラブルが生じやすい環境となり、身体的苦痛、経済的負担が増し、看護師のケア負担増にもつながっていました。さらに、ベッドサイドでの独特の便臭にも問題を感じていました。また、刺激性下剤であるアントラキノン系下剤の長期使用による大腸メラノーシスを発生するリスクが指摘されており(図1)、懸念事項となっていました。

「日本消化器病学会関連研究会慢性便秘の診断・治療研究会 編: 慢性便秘症診療ガイドライン 2017,p.36.2017.南江堂」より許諾を得て転載
こうした状況の中、改善策を模索していたところ、ある流動食の情報を得ました。この流動食には、食物繊維のグアーガム分解物(PHGG)が多く配合されています。PHGGは下痢を防ぐものとして欧州静脈経腸栄養学会(ESPEN)のコンセンサス会議にて推奨度Aの評価を得ています。また、PHGGは高発酵性であり、発酵により生じた短鎖脂肪酸が、下痢も便秘も改善するだけではなく、腸管全体の健全性を高めるといわれています。これを踏まえ、下剤に頼りすぎることのない排便コントロールを試みるためPHGG配合流動食を用いた栄養療法に取り組むことにしました。
試験方法
対象は、多量の水様便が続いている長期療養患者6例。実施期間は、2017年7~9月までの3カ月間。使用したPHGG配合流動食は、本来は経鼻胃管や胃ろうから摂取するものですが、経口摂取も可能であることから、管理栄養士との相談のもと、日々の食事と置き換える形で取り入れることにしました。全粥や流動食など、PHGG配合流動食1パック(400kcal)に相当するエネルギーの食事と置き換え(被験者に応じて1~2パック/日)、これまでと同様の食事時間に摂取してもらいました。
試験結果
排便のたびに、便性状と便臭を観察。さらに、1日ごとの下剤投与量、浣腸回数と排便周期、オムツ代についても記録しました。
便性状はブリストルスケールを用いて観察しましたが、便臭に関してはスケールがなかったため、独自に「おぞね便臭スケール」(表1)を作成しました。便臭に着目したのは、同室の患者や面会家族への影響が大きく病棟内で問題視されていたこと、目視できない腸内環境を評価する1つの基準になると考えたためです。
表1 おぞね便臭スケール
| 評価 | 状態 |
|---|---|
| 5 | 廊下にいても感じられる不快な臭い |
| 4 | 部屋に入ると感じる不快な臭い |
| 3 | オムツを開けた時点で感じる不快な臭い |
| 2 | オムツを開けた時点で感じるやや不快な臭い |
| 1 | 正常な便臭 |
便臭は、取り組み開始約2週間から改善し始め、便臭スケールでは、1例を除きほぼ正常な便臭となりました(表2)。
表2 おぞね便臭スケール評価
| 対象者 | 開始前 | 開始後 |
|---|---|---|
| Aさん | 3〜1 | ほぼ1 |
| Bさん | 3〜2 | ほぼ1 |
| Cさん | 3〜2 | 1 |
| Dさん | 5 | 3〜2 |
| Eさん | 3〜2 | ほぼ1 |
| Fさん | 3〜2 | 1 |
便性状をみると、導入開始から3カ月後の9月のブリストルスケールの平均値は、導入直後の7月と比べて全例「普通便4」に近づく傾向がみられました(表3)。水様便が泥状便以上になったことで、寝衣やシーツなどの汚染が減少しました。
表3 便性状の変化(ブリストルスケール月平均値*)
| 対象者 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん | Fさん |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.2 |
| 9月 | 4.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.0 |
刺激性下剤使用量は、全例で減少していきました(図2)。排便回数は水様便の改善に伴い減少し、下剤ではなく浣腸で
の排便が増えました。

オムツ交換の頻度も減り、オムツ代は、1例を除き、平均して月約5,250円減となりました。

考察
以上の結果により、食事の一部をPHGG配合流動食に置き換える栄養療法は、精神科病棟入院患者の排便コントロールに役立つことが示唆されました。
さらに、病棟スタッフ全員で便性状や排便周期などを観察したことで、下剤に頼りきりだった排便コントロールから、腸内環境改善による排便コントロールへと意識の変化がみられ、栄養療法への関心も高くなりました。
長期臥床の患者の場合、水様便によって背部まで汚染されることが多く、寝衣からシーツまで交換していましたが、PHGG配合流動食によって便が泥状便以上になることで、オムツだけあるいは防水マットだけの交換で済むようなりました。これにより排便ケアの時間が40 ~ 50分/日程度短縮されたと実感しています。その時間を、患者とのコミュニケーションやケアプランの作成など使うことができるようになり、ゆとりあるケアが展開できるようになりました。
また、血液検査の結果、多少ながら対象者のアルブミン値が改善していました。これは下痢の回数が減少したことで、栄養素の流出や体力の消耗が抑えられたためと推察されました。全身状態の改善も期待できるかもしれません。
おわりに
対象者6例のうち、5例は現在もPHGG配合流動食を継続しており、排便コントロールは良好です。今回の結果を受けて、新たにこの栄養療法を開始した患者さんもおり、期待をもって経過をみています。
今後は、PHGG配合流動食摂取の有無による比較検討を行い、栄養療法の有用性をさらに検証していきたいと考えています。