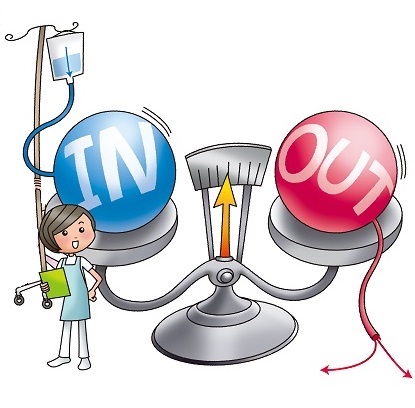介護施設等において重要な役割を担う看護職員の評価・処遇|第50回日本看護学会ー在宅看護ー学術集会
介護施設等において重要な役割を担う看護職員の評価・処遇|第50回日本看護学会ー在宅看護ー学術集会
- 公開日: 2019/11/6
2019年9月13日〜14日、宇都宮市文化会館/宇都宮市総合コミュニティセンターにて第50回日本看護学会ー在宅看護ー学術学会が開催されました。学術集会のメインテーマは「創造と実践力で支える在宅看護〜あらゆる世代・あらゆる場所で、あらゆる機会に〜」で、特別レポート企画では、「介護施設等において重要な役割を担う看護職員の評価・処遇」をテーマに講演が行われました。介護施設や在宅領域で働く看護職を取り巻く現状と、看護職がケアの質的整備を担っていくために必要な処遇改善のあり方について、3人の講師による講演が行われました。座長は公益社団法人日本看護協会 常任理事 熊谷雅美先生です。
はじめに、岡戸順一さんから看護職員の処遇・評価の現状について講演が行われました。
遂行している業務が多いほど看護職員のモチベーションは高い
2016年、日本看護協会は、介護施設などで働く看護職を対象に職場で実施している業務について調査を行いました1)。それによると、役割は「看取り」「感染」「安全管理」「多職種連携」「生活支援」の5つのカテゴリーと30業務が分類され、「働きがいがあるか」「継続して勤務したいか」という質問に対して看護職は役割が明確で、その業務の実施割合が高いほど、「はい」と答える方の割合が多くなっています。
介護施設の離職率は病院の2倍
一方、2014年に行われた調査では、看護職員の退職率は病院が10.8%であるのに対し介護施設は21.5%となっています。賃金面をみると、介護施設が病院よりもやや低い状況です。
これらの調査を踏まえ、2019年3月に日看協は「看護職のキャリアと連動した賃金モデル」の冊子を発行しました2)。複数のキャリアコースに区分された「複線型等級制度」を骨格とした賃金モデルを紹介しています。この賃金モデルを参考に処遇改善を行うことで、介護施設においても看護職のモチベーションの維持と職場への定着が期待できます。
次に、社会福祉法人和光会介護事業本部 本部長 田口将人さんがケース紹介を行いました。
看護職には全国共通の評価基準がない
介護職の評価基準には、平成24年に内閣府が開始し平成27年に厚労省が引き継いだ「介護プロフェッショナル段位制度」があります。一方、看護職にはそのような評価制度が整っていません。それぞれの上司による判断に任されているところがあり、グループ内にある3つの特養でも評価基準は統一されていませんでした。そのため、和光会でも看護職が病院から介護施設へ異動をする際、職能を客観的に評価することが難しい状況にありました。
法人独自の評価システムを構築、公正な賃金制度を運用
そこで、和光会では2013年から2年の期間をかけ、病院・高齢者施設・在宅領域で働く看護職員を公平に評価できるシステム作りに取り組みました。評価するポイントは、「わかる」「できる」「指導ができる」の3点です。このシステムを通し、配属先である病院や施設の職務に応じて評価基準をどの程度達成しているか適切に評価しています。
続いて、聖隷福祉事業団介護付き有料老人ホーム浜名湖エデンの園 前副園長 吉村浩美さんによるケース紹介です。
なかなか進まない人材の移行
2025年を目前に、看護職は社会保障制度改革を進めていく役割を求められています。ただ、大規模病院から地域への優秀な人材の輩出は依然として間に合っていません。急性期病院の在院日数が短縮されたことで介護施設や在宅に医療依存度の高い方が戻る、さらに認知症の方に対する生活支援といったケースが増えていくなかで、ケアを行う人材の確保が難しい現実があります。
人材確保につながる人材育成、5つの取り組み
聖隷福祉事業団は、病院や介護福祉施設、訪問看護ステーションなど、さまざまな施設があります。そのため、以下のような人材確保のためのシステムを整備し、人材の定着に役立てています。
・コース別雇用管理制度:聖隷福祉事業団の勤務地は奄美から千葉まで広範囲に及び、職員は勤務地域を広域か地域かを選択できる
・等級制度:9等級に分類
・コンピテンシー評価:昇格昇進の評価に活用
・施設・在宅看護職ラダーレベルⅠ~Ⅳ:日本看護協会のクリニカルラダーを参考にし、ラダーに応じた研修を実施
・外部研修の活用:地域ごとに研修を実施するほか、e-ラーニング研修を活用し、実践能力の向上を図る
これらの取り組みにより確保定着が促進されています。
最後に、会場の参加者とのディスカッションが行われました。
施設看護師の処遇改善に関する提言は初
会場からは、「介護施設のなかには、マニュアルや手順書がきちんと揃っていなかったり、免許が脅かされる可能性のあるところでは働きづらい」「入居者が求めているのは、安心した医療・安心した看護がある場だということを働きながら実感している」という意見が上がりました。座長の熊谷雅美先生は、「国が量的整備を行っている状況で、質的整備は看護職に期待されているのではないかと感じています。介護施設に入られている方が安心して生活できる場を提供しなければならず、それには看護職が担う役割に見合うような処遇改善を進めていかなければならないという課題を本日いただきました」と締めくくりました。
引用・参考文献
1)介護施設等における看護職員に求められる役割とその体制のあり方に関する調査研究事業(2019年10月16日閲覧)https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/report/2017/kaigoshisetsu_kangoshoku.pdf
2)看護職のキャリアと連動した賃金モデル~多様な働き方とやりがいを支える評価・処遇~(2019年10月16日閲覧)https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/fukyukeihatsu/wage_model.pdf