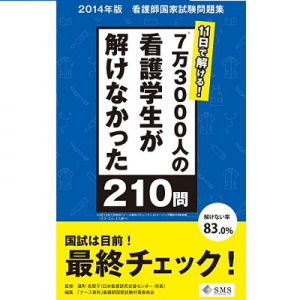小児の口腔ケアのコツ
小児の口腔ケアのコツ
- 公開日: 2014/3/20
動いたり泣いたりする小児のケアのコツ
小児には、遊びの要素を取り入れて、一緒に楽しくケアするのがコツです。
児との信頼関係を築く努力が必要
小児がんの患児の場合、粘膜が傷つきやすく、免疫が低下して菌が繁殖しやすく、出血しやすいので、口腔ケアを行う際には注意が必要です。出血傾向のある患者さんへの口腔ケアに準じて行います。
重症心身障害児の場合は、自分の意思で口が開かない児もいます。また、医療者と接するときだけ口を開かないというケースもあります。これは本能的に自分を守ろうとする気持ちの表れです。無理に開けようとすると噛みつくこともあるため、できるならお母さんに協力を仰ぎます。同時に、児との信頼関係を築く姿勢が大切です。
発達段階に合わせたケアの工夫が大切
歯の生え始めた頃から、発達段階によってケアのポイントも変わります。自分でやりたがる患児もいるため、家から柔らかめの歯ブラシを持参してもらい、「食事のあとに一緒にゴシゴシしようね」と声をかけて歯磨きをすることもあります。歯磨きが終わったら「できたねシール」を貼るなどの工夫も大切です。お母さんにも参加してもらったり、キャラクターものの歯磨きDVDを見ながら一緒に歯磨きをすると、楽しくできます。
■歯が生えてない頃
水で湿らせたガーゼなどで口の周りや中を拭いて、口に触れられることに慣らしていく
■乳歯が生えてきたら
生後7~8カ月頃、下の前歯から乳歯が生えてきたら、歯みがきを始める
■上の前歯が生えてきたら
1歳頃になると上下の前歯がそろってくる。生えて間もない歯は、石灰化が低い、唾液で食べかすや汚れが洗い流されにくい、糖分の多いものを食べたり飲んだりする機会が増えるなどの理由で、むし歯ができやすい環境にある
■奥歯が生えてきたら
自立心が芽生えてくるとともに、歯みがきをさせてくれなくなる傾向がある。ただし、汚れが唾液で取れず、菌が定着しやすい、上の前歯の間や奥歯の溝に汚れがたまりやすくなる。子どもだけでは十分に汚れを落とすことができないため、保護者の仕上げ磨きが必要
(ナース専科マガジン2014年4月号より転載)