記事一覧
15件/4045件

服薬コンプライアンスが低下した患者さんに関する看護計画|認知症により認知機能が低下している患者さん
認知機能が低下して服薬コンプライアンスが低下した患者さんに関する看護計画 認知症は脳の機能障害によって日常生活に支障をきたす疾患です。記憶障害や失行、失認など認知機能が低下することも知られており、服薬コンプライアンスに影響することも考えられます。そのため、今回は認知症で認

ヘルスケア・イノベーションフォーラム「認知症の早期発見・診断・治療の実現に向けて求められる変化」
2024年10月11日、東京・帝国ホテルの会場とオンラインのハイブリッド形式にて、日本イーライリリー株式会社と米国研究製薬工業協会(PhRMA)が共催する「第7回ヘルスケア・イノベーションフォーラム」が開催されました。 当日は、神戸市長の久元喜造先生による「認知症神戸モデル」の

医療機関機能の考え方について具体案を提示――新たな地域医療構想
厚生労働省(以下、厚労省)は10月17日に開催された第10回「新たな地域医療構想等に関する検討会」で、新設する「医療機関機能」の報告に関する考え方について案を提示し、おおむね了承された。具体的には「救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能」については、救急医療の実績や構想

認知症で誤嚥性肺炎が生じている患者さんに関する看護計画
嚥下機能が低下して誤嚥性肺炎が生じている患者さんに関する看護計画 認知症は脳の機能障害によって社会生活に支障をきたす疾患です。脳の機能障害から活動低下が生じてさまざまな症状をきたします。今回は認知症で嚥下機能が低下しており誤嚥性肺炎が生じている患者さんに関する看護計画を立

日本人の認知機能にはEPA/DHAに加えARAも重要―脳トレとの組合せでの縦断的検討
パズルやクイズなどの“脳トレ”を行う頻度の高さと、アラキドン酸(ARA)やドコサヘキサエン酸(DHA)という長鎖多価不飽和脂肪酸(LCPUFA)の摂取量の多さが、加齢に伴う認知機能低下抑制という点で、相加的に働く可能性を示唆するデータが報告された。また3種類のLCPUFAの

酸素療法を実施している患者さんに関する看護計画|肺炎の患者さん
肺炎で酸素療法を実施している患者さんに関する看護計画 肺炎とは細菌やウイルスなどに感染し、肺に炎症を起こす疾患です。既往歴のない若年者から病院や介護施設にいる高齢者までさまざまな人に発生する可能性があり、呼吸機能が障害されるため酸素療法が必要になることもあります。そのため

うっ血性心不全で入院している患者さんに関する看護計画
うっ血性心不全で入院している患者さんに関する看護計画 心不全とは何らかの要因によって心臓のポンプ機能が低下してさまざまな症状がみられる臨床症候群です。心臓のポンプ機能が低下して、全身に血液が送り出せなくなると血液の渋滞が生じてうっ血が起こります。今回はうっ血性心不全で入院
気管挿管の看護|目的、適応、手順、合併症、看護計画
*2024年10月25日改訂 気管挿管とは 何らかの原因で気道に閉塞が生じている、または生じる可能性がある患者さんや、人工呼吸管理が必要となった患者さんに対し、気管内にチューブを挿入・留置し、気道を確保する方法です。気管挿管には、「経口気管挿管」と「経鼻気管挿管」の大き

小児用医薬品の開発計画の策定を努力義務化、健康サポート薬局は認定制へ
改正された薬機法の施行後5年をめどとした見直しに向けて議論している厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(以下、制度部会)は、10月3日、医薬品の安全かつ迅速な承認制度、薬局・医薬品販売制度などを議題として、2024年度第7回部会を開き、医療用医薬品の承認申請時に小児用医薬品

体脂肪だけを減らせる持久力運動
高強度の持久力運動により、体脂肪だけを効果的に減らせることを示す研究結果が報告された。中年男性が7日間で1,440kmのロードサイクリングを行った結果、全身の体脂肪は9%減少、内臓脂肪は15%減少して、血圧や血清脂質にも良い影響が生じ、一方で体重はわずか1%しか減らなかった
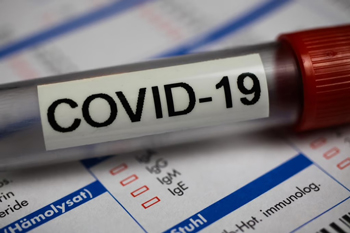
重症の新型コロナ感染者の心臓リスクは心疾患既往者のリスクと同程度
重症の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、心筋梗塞や脳卒中、全死亡などの主要心血管イベント(MACE)リスクを高め、その程度はCOVID-19に罹患していないが心疾患の既往歴がある人のリスクとほぼ同程度であることが、米クリーブランドクリニック・ラーナー研究所心血

禁煙開始が「遅すぎる」ことはない
喫煙習慣のある高齢者の中には、「今さら禁煙しても意味がない」と考えている人がいるかもしれない。しかし、実際はそんなことはなく、高齢期に入ってから禁煙したとしても、タバコを吸い続けた場合よりも長い寿命を期待できることが明らかになった。例えば75歳で禁煙した場合、喫煙を続けた人

がんで緩和ケアを実施している患者さんに関する看護計画
がんで緩和ケアを実施している患者さんに関する看護計画 がんとは、細胞の中にある遺伝子に何らかの要因によって異常が生じて、その異常な細胞が無秩序に増えていく疾患です。周囲の組織に浸潤したり、血液やリンパを介して他の場所に転移したり、局所あるいは全身にがんによる症状が出現する
下痢の看護|種類・観察項目・看護計画など
*2024年10月24日改訂 下痢とは 下痢とは、何らかの原因で便の水分量が多くなり、液状に近い便を排出する状態をいいます。『便通異常症診療ガイドライン2023―慢性下痢症』では、「便形状が軟便あるいは水様便、かつ排便回数が増加する状態」と定義しています1)。一般的

2026年度診療報酬改定に向けた医療経済実態調査の議論開始へ、歯科用貴金属価格改定も
厚生労働省(以下、厚労省)は、10月9日に開催された中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会で、2026年度診療報酬改定の基礎資料とする第25回医療経済実態調査の進め方について、調査実施小委員会を開催、調査設計に向けた議論を開始することを提案し、中医協に了承された。


