記事一覧
15件/4060件
【急変対応まとめ】みんなの不安、一気に解決!
急変に対する不安は、多くのナースが持っているようです。 そこで、より的確に迅速に動くために役立つ情報をまとめました。 さぁ、いざというときに慌てず動ける、急変に強いナースになりましょう。 急変を予測する!見極める! 【急変に結びつく危険な徴候と
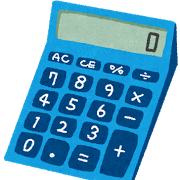
【問題19】抗生剤と生食50mlを、小児用ルート 60分間で投与する時、1分間の滴下数は?
問題 小児用ルートを使用して、●●抗生剤を、50ml生理食塩水で溶解して、60分間で投与する指示を受けました。 1分間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 50滴 解説

緩和ケアに求められる3つのスキル
緩和ケアというと終末期というイメージがありますが、現在は「がんと診断されたときから開始する」という考えもあり、より早期から行うことが求められています。 その中で、看護師はどのような役割を求められているのでしょうか。今回は、緩和ケアをキーワードに解説します。
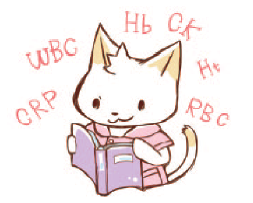
糖尿病性ケトアシドーシスとは?
糖尿病性ケトアシドーシスについて解説します。 糖尿病性ケトアシドーシスとは? 高血糖によりケトン体が血中に増加し、血液が酸性に傾くことを「糖尿病性ケトアシドーシス」といいます。 糖尿病性ケトアシドーシスの原因 ● インスリン注射の中止

【血液ガス】酸・塩基とは?
難解用語によって、血液ガスの理解にハードルに感じてしまっていませんか? 今回は、血液ガスを理解するために必要な用語、「酸」と「塩基」について解説します。 酸とは? 酸は「H+を放出する物質」と定義されています。 物質の代謝によって生じ
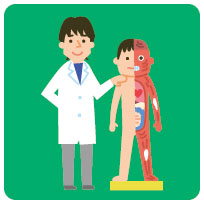
第6回 生理食塩水の0.9%という濃度
今回は、身近な生理食塩水とナトリウムの関係について解説します。 ナトリウムについてまとめて読むなら ■ 電解質-ナトリウム ■ ナトリウムと水は切っても切れない関係 ■ 抗利尿ホルモンとアルドステロン 生理食塩水の0.9%という濃度を実感する

サラッと復習!【糖尿病とは?】
糖尿病についてカンタンに解説します。 糖尿病とは? 糖尿病は、すい臓から分泌されるインスリンの働きが低下し、慢性的に高血糖が持続する疾患です。 糖尿病の症状 軽度では、自覚症状はあまりありません。 中等度になると、口渇、多飲、多尿、体重減

【問題18】500m×3本を、24時間 小児用ルートで投与する時、1秒間の滴下数は?
問題 小児用ルートを使用して、●●輸液500m×3本を、24時間で投与する指示を受けました。 1秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約1滴 解説 小児用ルートは1m

第12回 ジェネリック医薬品の今さら聞けないQ&A
外来や病棟でも、近年使用が増えてきたジェネリック医薬品。患者さんからの問い合わせも多く、「どう答えていいかわからない」という声もきかれます。そこで、ジェネリック医薬品の素朴なギモンについて解説します。 Q. ジェネリック医薬品ってどんなもの? A. ジ

【看護倫理・事例】第11回<問題編>個人情報の取り扱いに悩んだケース
日々の看護のなかに意外に多く潜んでいる倫理的問題。 それらの解決のためには、まず、倫理的な違和感に気づくセンスが大切です。 今回は、患者さんの個人情報の保護と共有に関するケースをもとに、センスを磨く練習をしてみましょう。 今回の患者さん

【問題17】抗生剤と生食50mlを、成人用ルート 60分間で投与する時、1分間の滴下数はいくつ?
問題 成人用ルートを使用して、●●抗生剤を、50ml生理食塩水で溶解して、60分間で投与する指示を受けました。 1分間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約17滴 解説
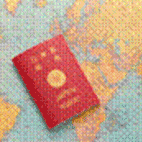
第17回 海外正看護師資格取得を有利にする“コツ”
「あーまた今日もサービス残業か・・・」 と今思っていませんか? デートの約束をしていても残業で遅くなり、彼氏と喧嘩となることも・・・ 合コンの約束をしていても間に合わず、結局不参加で出会いも広がらず・・・ 「どうにか残業が少ないところで働けないのかなぁ・・・」

Q.誤嚥を防ぐために行うとよいとされていることは?
メルマガ限定で配信中の大人気コンテンツ「クイズマラソン」。その中でも、特に解答者が多かった問題を公開! 今回は食事介助についてです。 Q.嚥下障害のある患者さんの食事介助をする際、誤嚥を防ぐために行うとよいとされていることは次のうちどれ? [1
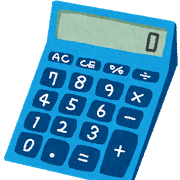
【問題16】抗生剤と生食100mlを、60分間 小児用ルートで投与する時、1秒間の滴下数は?
問題 小児用ルートを使用して、●●抗生剤を、100ml生理食塩水で溶解して、60分間で投与する指示を受けました。 1秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約2滴 解説
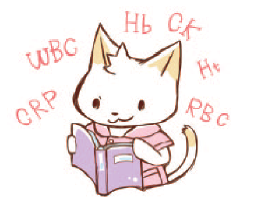
【貧血】検査値を組み合わせてアセスメント
関連する検査データを組み合わせて読むと、病態を正しくとらえることができます。 今回は、事例を使って「データを組み合わせて読む方法」を解説します。 事例 Bさん 71歳 男性 主訴:全身倦怠感、動悸 現病歴:最近、身体がだるくふらつく感じ


