記事一覧
15件/4065件

口頭指示による薬剤量間違い
口頭指示の際、薬剤の単位や量、希釈の条件を明確に伝えなかったため、薬剤量を間違えた事例が2件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年11月30日、第13回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 口頭指示の際、薬剤の単位や量、希釈
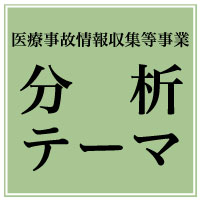
個別テーマについての検討状況|第6回報告書(2006年4月〜6月)②
【2】医療機器の使用に関連した医療事故 平成18年4月1日から平成18年6月30日の間に報告された医療機器の使用に関連した医療事故のうち、人工呼吸器の使用に関連した事例4件について分析を行った。 (1)医療機器の使用に関連した医療事故の現状
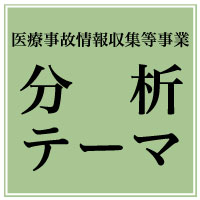
個別テーマについての検討状況|第8回報告書(2006年10月〜12月)③
【3】医療処置に関連した医療事故 平成18年10月1日から平成18年12月31日の間に報告された医療処置に関連した医療事故のうち浣腸に関連した事例は1件であった。また平成18年7月1日から平成18年12月31日の間に報告された医療事故事例のうち経鼻栄養チューブやPEG
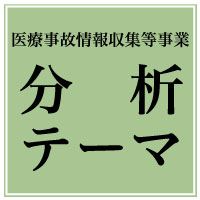
個別テーマについての検討状況|第6回報告書(2006年4月〜6月)
【1】薬剤に関連した医療事故 平成18年4月1日から平成18年6月30日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例20件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 本報告書において分析対象とした医療事故事例の概要は図表Ⅲ-
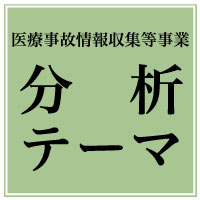
個別テーマについての検討状況|第8回報告書(2006年10月〜12月)②
【2】医療機器の使用に関連した医療事故 平成18年10月1日から平成18年12月31日の間に報告された医療機器に関連した医療事故のうち、人工呼吸器に関連した事例と輸液ポンプ等(シリンジポンプを含む、以下省略)に関連した事例について分析を行った。 (1)人工呼吸
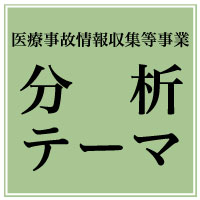
個別テーマについての検討状況|第5回報告書(2006年1月〜3月)③
【3】医療処置に関連した医療事故 第3回報告書(注1)では「グリセリン浣腸により腸管穿孔を生じたと考えられる事例」を分析班において広く共有すべき事例であると考え、情報提供を行った。社団法人日本看護協会は平成18年2月「立位による浣腸実施の事故報告」を、緊急安全情報とし
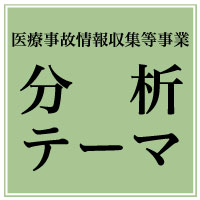
個別テーマについての検討状況|第9回報告書(2007年1月〜3月)
【1】薬剤に関連した医療事故 平成19年1月1日から平成19年3月31日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例15件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 本報告書において分析対象とした医療事故事例の概要は図表Ⅲ

伝達されなかった指示変更
関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指示が実施された事例が2件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年4月30日、第10回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指

2008年に提供した医療安全情報
2008年1月~12月に医療安全情報No.14~No.25を毎月1回提供いたしました。今一度ご確認ください。 医療安全情報提供後に報告された主な類似事例 No.14 間違ったカテーテル・ドレーンへの接続 患者には末梢静脈ライン、透析用

未滅菌の医療材料の使用
誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例が3件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2007年12月31日、第11回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例が報告されています。

診察時の患者取り違え
外来診察の際、口頭で行った患者氏名の確認が不十分であったため、患者を取り違えた事例が3件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年8月31日、第13回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 診察時、口頭で患者氏名を確認したにもかか

処方表記の解釈の違いによる 薬剤量間違い
処方表記の解釈の違いによる薬剤量の間違いが3件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年3月31日、第11回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 「3×」や「分3」の表記を3倍と解釈したことによる薬剤量の間違いが報告されています。

輸液ポンプ等の流量の確認忘れ
輸液ポンプ等(輸液ポンプ及びシリンジポンプ)を使用して、別の薬剤に変更する際に、流量の確認を忘れた事例が2件報告されています。(集計期間:2004年10月1日~2007年6月30日、第8回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 輸液ポンプ等を使用し

湯たんぽ使用時の熱傷
「療養上の世話」において湯たんぽを使用した際、熱傷をきたした事例が6件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年2月29日、第10回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 身体に湯たんぽが接触し、熱傷をきたした事例が報告されています。
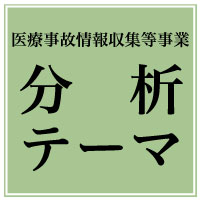
個別テーマについての検討状況|第8回報告書(2006年10月〜12月)
【1】薬剤に関連した医療事故 平成18年10月1日から平成18年12月31日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例20件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 本報告書において分析対象とした医療事故事例の概要は図


