記事一覧
15件/4065件
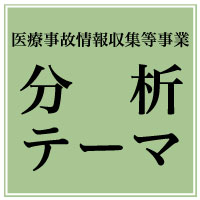
個別テーマについての検討状況|第12回報告書(2007年10月〜12月)
【1】薬剤に関連した医療事故 平成19年10月1日から平成19年12月31日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例35件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 薬剤に関連した医療事故事例の概要は図表Ⅲ-1の通りである。

ウォータートラップの不完全な接続
人工呼吸器回路のウォータートラップのカップの接続が不完全であったため、患者の呼吸状態が一時悪化した事例が4件報告されています。集計期間:2006年1月1日~2009年5月31日、第16回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載) 人工呼吸器回路のウォータート
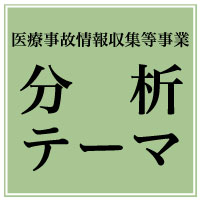
個別テーマについての検討状況|第9回報告書(2007年1月〜3月)④
【4】検査に関連した医療事故 平成19年1月1日から平成19年3月31日の間に報告された臨床検査に関連する事例は2件であった。 (1)臨床検査に関連した事故の状況 分析対象とした医療事故事例の概要を発生段階別に見ると、2名の患者の採取スピッツを取り違えた事
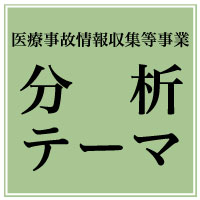
個別テーマについての検討状況|第9回報告書(2007年1月〜3月)③
【3】医療処置に関連した医療事故 平成16年10月1日から平成19年3月31日の間に報告された医療事故事例のうち「事故の概要」のコードの中から「ドレーン・チューブ」のコードで選択されていた事例、及びそれ以外のコードの中から、その報告内容がドレーンの挿入・留置および管理
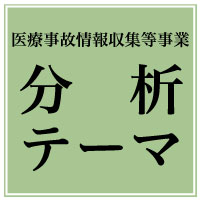
個別テーマについての検討状況|第9回報告書(2007年1月〜3月)②
【2】医療機器の使用に関連した医療事故 平成19年1月1日から平成19年3月31日の間に報告された医療機器に関連した医療事故のうち、人工呼吸器に関連した事例と輸液ポンプ等(シリンジポンプを含む、以下省略)に関連した事例について分析を行った。 (1
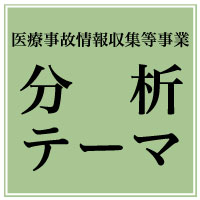
個別テーマについての検討状況|第10回報告書(2007年4月〜6月)
【1】薬剤に関連した医療事故 平成19年4月1日から平成19年6月30日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例27件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 本報告書において分析対象とした医療事故事例の概要は図表Ⅲ-1の通りで

小児への薬剤10倍量間違い
小児に対する処方の際、薬剤量を10倍間違え、過量投与した事例が8件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年12月31日、第13回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 小児に対する処方の際、薬剤量を10倍間違え、過量投与した事例が8

2006年から2007年に提供した医療安全情報
2008年にも類似事例が発生しています No.1 インスリン含量の誤認~バイアルの「100単位/mL」という表示の誤認に起因した事例~ 2件 看護師Aは医師の指示により、「生食39ml+ヒューマリンR100単位」を準備した。その際看護師Aは、インスリンのバイアルに表
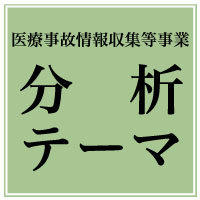
個別テーマについての検討状況|第7回報告書(2006年7月〜9月)
【1】薬剤に関連した医療事故 平成18年7月1日から平成18年9月30日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例16件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 本報告書において分析対象とした医療事故事例の概要は図表Ⅲ-1の

血糖測定器の使用上の注意
イコデキストリンを含む透析液を投与中の患者の血糖測定に、グルコース脱水素酵素(GDH)法のうち補酵素にピロロキノリンキノン(PQQ)を用いた血糖測定器を使用したことにより、実際の血糖値より高値を示し、その値をもとにインスリンを投与した事例が1件報告されています。(集計期

化学療法の治療計画の 処方間違い
化学療法の際、治療計画の実施間違いが25件報告されています。そのうち、処方間違いにより非投与日に腫瘍用薬を投与した事例が5件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年7月31日、第11回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載)。 処方間違
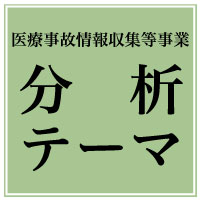
個別テーマについての検討状況|第6回報告書(2006年4月〜6月)④
【4】患者取り違え、手術・処置部位の間違いに関連した医療事故 平成18年4月1日から平成18年6月30日の間に報告された医療事故事例のうち、患者取り違え、手術・処置部位の間違いに関連した事例は9件であった。 (1)患者取り違え、手術・処置部位の間
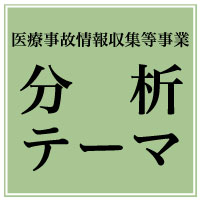
個別テーマについての検討状況|第5回報告書(2006年1月〜3月)④
【4】患者取り違え、手術・処置部位の間違いに関連した医療事故 平成16年10月1日から平成18年3月31日の間に報告された医療事故事例のうち「事故の概要」の中から「患者取り違え」、「部位間違い」のコードで選択されていたもの、及びそれ以外のコードが選択されていたものの中
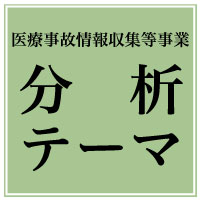
個別テーマについての検討状況|第8回報告書(2006年10月〜12月)④
【4】検査に関連した医療事故 平成18年10月1日から平成18年12月31日の間に報告された臨床検査に関連する事例は3件であった。 (1)臨床検査に関連した事故の状況 分析対象とした医療事故事例の概要を発生段階別に見ると、採血実施後、痛みや痺れを感じた事例
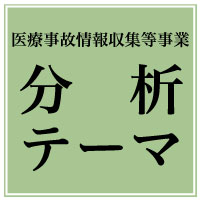
個別テーマについての検討状況|第6回報告書(2006年4月〜6月)③
【3】医療処置に関連した医療事故 平成16年10月1日から平成18年6月30日の間に報告された医療事故事例のうち「事故の概要」のコード情報の中から「ドレーン・チューブ」が選択されていた事例、及びそれ以外のコードが選択されていたが、その報告内容が経鼻栄養チューブやPEG


