記事一覧
15件/4077件
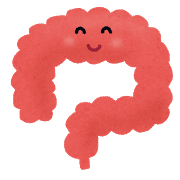
第3回 経管栄養剤による「排便コントロール」改善への取り組み【PR】
▼経腸栄養について まとめて読むならコチラ 経腸栄養(経管栄養)とは|種類・手順・看護のポイント 職員全員が高い意識をもち、自然に近い排便を目指す 排泄部会の活動を通して、排泄ケアの改善に取り組んできた竹川病院ですが、今後の目標として、田

第36回 セカンド・オピニオンを求めたい患者の気持ち
医療者が患者の治療・ケアを行ううえで、患者の考えを理解することは不可欠です。 そこで、患者の病いの語りをデータベースとして提供しているDIPEx-Japanのウェブサイトから、普段はなかなか耳にすることができない患者の気持ち・思い・考えを紹介しながら、よりよい看護のあり

負担の少ない体位変換の方法・手順
患者さんの体位変換は重要なケアであるとともに頻繁に行われるケアです。今回は、患者さんにも看護師にも負担が少ない体位変換の方法を解説していきます。 Q 患者さんにも看護師にも負担の少ない体位変換の方法を教えてください。特に拘縮や片麻痺のある患者さんへの楽な体位変換につ

第9回 授乳中の不安・母乳育児ができない不安にお答えします!⑥乳腺炎にならないために
本連載では、医療人として、母親として理解しておきたい母乳育児について、第一人者である水野克己先生が解説します。 乳腺炎は遭遇しがちな疾患 乳腺炎は、授乳中の女性でしばしば遭遇する疾患です。産後3ヵ月までに10人に約1人、全授乳期間では3-4人に1人はか
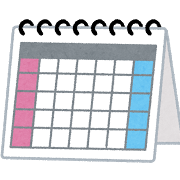
医療従事者向けセミナー2016「肺がん薬物療法の最前線」開催のお知らせ
肺がん医療向上委員会・肺癌学会は、療従事者に対する継続的な情報発信と肺がん医療向上のための連携強化を目的にがん医療に携わるすべての医療従事者に向けたセミナーを開催します。 プログラム 肺がん薬物療法の最前線 1.化学療法・分子標的治療薬・免疫療法の最前線

内視鏡治療でSpO2が低い場合の注意点
▼サチュレーション(SpO2)について、まとめて読むならコチラ サチュレーション(SpO2)とは?基準値・意味は?低下の原因と対応 Q. 内視鏡治療時には、患者さんは2~3時間にわたって左側臥位の状態のままですが、特にSpO2の値が低い場合に気をつ

手術前の除毛は必要ですか?
Q 術前の除毛は必要ですか。 A SSI予防の観点から基本的には行わない方向ですが、どうしても必要な場合は術直前に除毛を行います。 かみそりによる除毛が感染巣となる可能性がある 当院では、除毛は手術部位や周辺の体毛が手術に支障を及ぼす場合にのみ行っており

【マンガでわかる!】JCSの具体的な付け方
JCS(ジャパン・コーマ・スケール)は、患者の意識レベルを9つに分類(大分類:3パターン × 小分類:各3パターン)する測定手法です。意識レベルのアセスメント法についてマンガで詳しく解説します! 【大分類】 Ⅰ:覚醒している Ⅱ:刺激すると覚醒する Ⅲ:刺激し

「SHARE」とは?がん患者さんとのコミュニケーショントレーニングツール
▼看護師のコミュニケーションとマナーについて、まとめて読むならコチラ 看護師のコミュニケーションとマナー 伝え方の工夫でバッドニュースの影響が軽減 難治がんの発症や再発・悪化、抗がん剤治療の中止など、いわゆる「バッドニュース」を患者さんに伝
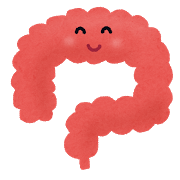
第2回 経管栄養剤による「排便コントロール」改善への取り組み【PR】
▼経腸栄養について まとめて読むならコチラ 経腸栄養(経管栄養)とは|種類・手順・看護のポイント 経管栄養剤切り替え後、下剤の使用量は減少傾向に 竹川病院の療養病棟では、入院患者さんの排便日誌をもとにした下剤の使用量調査が、これまでに2回

ヒヤリ・ハットの報告、書き方のポイント
当事者でない事例も一歩踏み込んで読み込む 医療事故やヒヤリ・ハットの記事を読んで、「造影剤の事故か。目新しい事故ではないな」「気をつけよう」で終わってしまっては再発防止にはなりません。自分の職場では、造影剤を準備して担当医に手渡すまでの流れの中で、どの時点で、誰が、

臓器提供に携わるとき、看護師が感じることとは
移植医療に変化をもたらした改正臓器移植法 2010年7月に施行された改正臓器移植法は、移植医療にとって大きな契機となりました。これまでは、本人の書面による意思表示があるときのみ認められていた脳死下での臓器提供が、本人の意思が不明であっても家族の承諾があれば可能になっ

リハビリテーションで看護師にしかできないこと
リハビリテーションの現状と課題 リハビリテーション(以下、リハ)は、生活機能障害を対象とした当事者のQOLの向上を目指す包括的な活動です。医学的リハ、職業リハ、教育リハ、社会リハの大きく4つに分類され、これらを統合して提供することを総合リハといいます。私たち医療者が

DIPEx-Japan 公開シンポジウムのお知らせ
病気や障害を持っても安心して暮らせる社会を目指して〜患者体験学の創生Part2~ 英国オックスフォード大学で作られているDIPExをモデルに、日本版の「健康と病いの語り」のデータベースを構築し、それを社会資源として活用していくことを目的として作られた特定非営利活動法

第15回 エンゼルメイク実践編 (3)蒸しタオルと乳液による整肌
前回のクレンジング・マッサージからの続きを実践していきます。今回のエンゼルメイクはクレンジング・マッサージにより皮膚の汚れがとれた後、蒸しタオルと乳液で整肌をします。(今回は女性をモデルとしていますので、男性の髭そりをする場合は「ナースのためのエンゼルケア(学研メディカル


