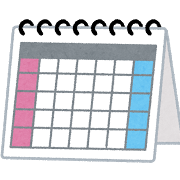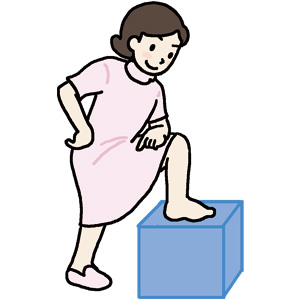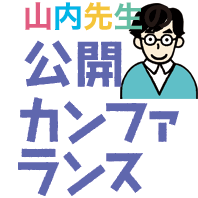 第24回 看護師が知っておきたいアセスメントのコツ
第24回 看護師が知っておきたいアセスメントのコツ
- 公開日: 2016/2/15
- 更新日: 2021/1/6
今回は、アセスメントするときに念頭においておきたいことを解説していきます。
ゴールがどこなのかを認識しよう
アセスメントは入り口もゴールもバラバラで、ものすごく幅があります。求められる程度は、在宅か病棟かなど看護の現場によっても違います。
疾患名に結びついた処置が必要な職場であれば、より端的に表せたほうがよいでしょうから疾患名まで落とし込んでいったほうがよいのでしょう。
しかし、訪問看護なら、疾患名がなんであれ、その人が自分の暮らしができるかどうかの評価を優先しますから、疾患名の重要性は前者よりも薄まるでしょう。
アセスメントの加減をどうすればいいのかは、ゴールがなんなのかをしっかりと認識することで決まります。例えば、前述した訪問看護の場合のゴールは、この人が自宅にいていいか、病院へ行ったり医師にすぐに報告したりしたほうがいいかを判断することです。
これを判断するために必要な情報を集めるのがアセスメントです。
アセスメントの目的をはっきりさせる
アセスメントを行う際には、どうしたいのか、何のためのアセスメントなのかをしっかりと考えて、どこまでアセスメントすることが必要なのかを見極めていってほしいと思います。
アセスメントの話になると、疾患名が気になる人が多いようです。例えば、呼吸をするときにヒューヒューといった呼吸音が聞こえると「これは喘息ですか?」とすぐに疾患に結びつけようとしてしまいがちです。
確かに喘息でもそういった状態になるけれど、誤嚥でもなる可能性はあるでしょう。疾患名が明らかにならなくても、空気の通り道が狭まっていて苦しそうだ、ということはわかりますよね。
これでけでも十分アセスメントといえると思うのです。疾患名がわからなくたって、その患者さんの状態を知ることはできるでしょう。
今、こういう状態にある人ですと明らかにするのも一つのゴールです。疾患名を知ることが何より大事なのではなく、疾患名という手掛かりがあったほうが、その人を捉えやすい、活用できる情報の一つだと思えばよいでしょう。
かもしれないリストってなに?
みなさんは、あまり意識的に行っていないかもしれませんが、患者さんの状態をアセスメントするときには、「今、患者さんにはこのようなことが起こっているのではないか」ということを考えていると思います。
「○○かもしれない」→「アセスメントをする」→「ほぼ間違いなさそう」→「ケアを実施」という手順を踏んでいるはずです。1回で「ほぼ間違いなさそう」に進めることもあれば、「違った」となり、また「○○かもしれない」に戻ることもありますよね。
このとき、1つしか「かもしれない」というのが思い浮かばず、さらに「違った」場合には、行き詰まってしまいます。
ですから、アセスメントするときは、どれだけ「かもしれない」をリストに上げることができているかが大事になります。
この「かもしれないリスト」は、基本的にはみなさんのこれまでの経験から「こういうことが考えられるのではないか」と患者さんの状態を推察し、リストアップしてできていると思います。
そうなると、より経験を積んだ人のほうがリストアップできて、経験の浅い人にはできない、となってしまいます。しかし、実際はそうではありません。
経験はあっても自分の中である程度体系化されていなければ、とっさに思い浮かべることは難しいでしょう。
そこで体系化するには日々の看護の中でなぜそのような状態になっていたのかと振り返っておくこと。特に失敗してしまったことに対しては、自分がなぜそこでつまずいてしまったのか、間違ってしまったのかを考えてみることが大切です。
また、経験が少なければ知識で補う、ということもできます。症状や疾患についての知識を得ることはもちろん、この連載のようにカンファランスなどで、他の人が体験したものを自分の経験として取り込むこともできるでしょう。
そうすることで「かもしれないリスト」の内容を増やすことができます。ですから、こういったカンファランスの場も大切にしてほしいと思います。