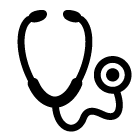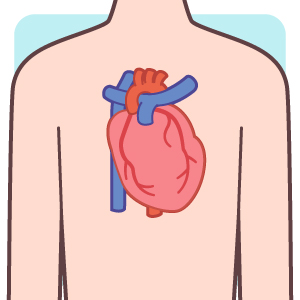検査説明における看護師の役割について
検査説明における看護師の役割について
- 公開日: 2013/12/16
外来でも入院中でも患者さんはさまざまな検査を受けます。特に、よく使用されるCTやMRI、超音波などの検査について知っておくとよいことを解説します。
第1回は、検査説明における看護師の役割について考えます。
【この連載の記事】
* 検査にかかわる注意事項 ― 検査前・中・後
* CT検査とは?|看護師の役割と検査説明のポイント
* MRI検査(MRCPやMRAなど)|看護師の役割と検査説明のポイント
* 超音波検査(心エコーや腹部エコーなど)|看護師の役割と検査説明のポイント
* 血管造影検査|看護師の役割と検査説明のポイント
* 内視鏡検査(上部内視鏡検査・下部消化管内視鏡検査)|看護師の役割と検査説明のポイント
検査説明における看護師の役割って何だろう
外来・入院にかかわらず、検査における看護師の役割は、患者さんに必要な検査や治療が安心・安全、そしてスムーズに実施できるように環境を整え、身体的・精神的な侵襲を最小限にすることです。
検査が決まると、医師から検査目的や実施方法について説明されますが、それでも多くの患者さんは検査に対して不安を抱いています。看護師には、説明の終了後に内容の理解度を確認し、必要に応じて補足あるいはあらためて医師からの説明を求めるなど、検査への不安が少しでも軽減され、信頼関係が深まるような支援が求められます。
それには実施される検査について、十分な知識を得ておくことが不可欠です。特に侵襲性の高い検査では、そのリスクについても十分理解した上で検査に臨んでもらうことが必要になります。
また、患者さんと接する中で、既往や服用している薬剤、アレルギー歴、患者さんの全身状態など、検査・治療に必要な情報を得た場合には、医師や他の医療従事者に報告し、連携を図ることも大事な役割です。時には患者さんの希望などを聴取しながら、診療に合わせた治療計画が円滑に進められるよう調整役としての役割を担いましょう。
検査説明を始める前に検査の目的を知っておこう
患者さんに適切なケアを提供するためには、ただ検査の案内をするのではなく、病名や経過を知り、何を目的に検査を行うのかを理解しておくことが重要です。検査の目的には、主にスクリーニング検査、確定診断・重症度判定のための検査、治療効果の判定・経過観察のための検査などが挙げられます。
スクリーニング検査
患者さんの健康状態を把握するための基本的な検査。一般的に行われている人間ドッグや地域の成人検診などもこれに該当します。
確定診断・重症度判定のための検査
スクリーニング検査などによって異常が認められた患者さんに対して行う検査。確定診断とともに、その検査結果によって治療方針も決定されることになります。
治療効果の判定・経過観察のための検査
治療効果を評価することを目的としたフォローアップの検査。個人差なども考慮しながら、定期的に行われます。
検査順序の決まりごとを知っておこう
同日に複数の検査が組まれることはよくありますが、必要な検査を安全に行うことができるようその順番は決まっています。
例えば、胃の内視鏡検査と超音波検査を同日に実施するとします。内視鏡検査は腹部に空気を送りながら内部を観察するため、その後に超音波検査を受けるとなると残った空気が邪魔になり、得られる画像が不鮮明になってしまいます。
従って、この2つの検査が同日にオーダーされたら、超音波検査を先に実施することになります。また、侵襲の度合いの違いでみると、低侵襲の検査(単純)から高侵襲の検査(造影)という順序で行われるのが一般的です。
検査スケジュールの適切な調整のためにも、検査の方法や特徴について理解しておくことは大切なのです。
検査に使われる薬について知っておこう
検査によっては造影剤のほかにも前投薬が使用されることがあります。内視鏡での局所麻酔薬や鎮静薬、大腸検査での下剤などです。薬によっては副作用が起こったり、検査終了後に安静が必要になるなど、活動を制限される場合があるので、どのような薬が使用されるのか十分に知っておく必要があります。

ここを伝えたい検査説明のキーワード
検査に使われる薬について知っておこう
検査を開始する前に全体像をイメージしやすいよう、検査前縲恁沚ク中縲恁沚ク後での注意点を明確にしておくことは重要です。
検査前の主な説明事項としては、食止めや内服薬の休薬、下剤の使用といった前処置など、検査中では、造影剤による副作用の徴候、不安感や同一体位による苦痛の申し出など、検査後では、検査による影響や遅発性副作用の徴候、食事・活動制限の有無、安静の必要性などがあります。
次に挙げるキーワードを参考にしながら、患者さんにわかりやすい言葉・方法で伝えましょう。
※次回は、検査前・中・後に分けてどんなことを説明するとよいかを解説します。
(『ナース専科マガジン』2011年8月号より転載)